『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
③ 成功する支援関係とは?(その2)
今日のところは「③ 成功する支援とは?」の”その2“である。”その1“では、支援状況の基本的ダイナミズムが説明された。支援の状況ではクライアント側はワン・ダウンの位置となり、支援する側はワン・アップの位置を得る。そのため人間関係のダイナミズムの綾を理解しないと、支援が失敗してしまう。最初はクライアントも支援者も、何を期待すべきか、何を与えるべきかわからず、互いに不安と緊張が起こり支援は難しくなる。そして、その状態で感情的な罠が潜んでいる。今日のところ”その2“では、クライアントが陥りやすい感情的な罠が取り扱われる。それでは、読み始めよう。
クライアントが陥りやすい五つの罠
①.最初の不信感
クライアントからはその支援者から受け入れられ支援を受けられるかが問題となる。そのためそれが真の問題を隠す原因ともなりうる。
クライアントが真の問題を隠し仮定の問題で支援を求め、支援者がどんな反応を示し、どの程度同情的になるかを判断することがある。そのような場合に支援者は、行動を急ぎすぎないことが大切である。仮定の問題に助言を与えたり指導したりする結果、真の問題を知る機会が失われることがある。
②.安堵
クライアントが助けてくれる支援者に出会い安堵した場合、過剰に支援者への依存や従属する感情を示すことがある。しかし、クライアント自信の努力が必要な場合は、その感情が罠になる。クライアントが依存状態を強めると、クライアントが主体的になることを妨げる。
支援の大半の状況では、問題がふたたび起きたときにクライアントが解決できるようにしてやることが目的の一つである。(抜粋)
③.支援の代わりに、注目や安心感、妥当性の確認を求めること
クライアントが支援を求めながら、本当はまったく別なものを望んでいることがある。支援を頼めば、相手は返事をしなければならないため、支援をいう行為を利用して「私に注目して」と自分に注意を向けさせようとすることがある。このような場面では、クライアントが自ら今代の解決策を考えだしている場合もある。
このような状況のとき支援者は、無言で解決策に同意するようなことをせず相手を安心させる方法を見つける必要がある。示された解決策に問題があった場合は、争点をもう一度考え直すべきである。
④.憤慨したり防衛的になったりすること
クライアントが支援者を無能に見せる機会を探していることがある。支援が時期尚早だったり、不適切だったりした場合に起こることが多い。このようなとき、クライアントは支援者の助言を見くびり面目を失わせることにより、自分が支援者と対等な位置を占めようとする。
このような展開をしている関係で問題なのは、クライアントの能力を引き上げるのではなく、支援者の評判を落とすことによって立場のバランスが保たれる点である。(抜粋)
⑤.ステレオタイプ化、非現実的な期待、(対人)近くの移転
クライアントは過去にも支援者と関わった経験がるため、それがその人に感情や見解に影響することがある。クライアントが支援者のあらゆる行動を過去の経験に照らし合せて測り、それをもとに新たな支援の関係の質を判断する。そのため支援者はあらかじめクライアントに過去にどのような支援を受けたかを尋ねる必要がある。
最後に著者はクライアントが陥る罠のまとめとして次にように言っている。
要するに、助けを必要として求められれば、感情的な反応を引き起こす、落ち着かなくて不安な状況が生まれるのである。こうした反応に気づかない支援者は不適切な行動をとり、役割が明確でバランスがとれた人間関係を築くのがいっそう困難になるかもしれない。(抜粋)
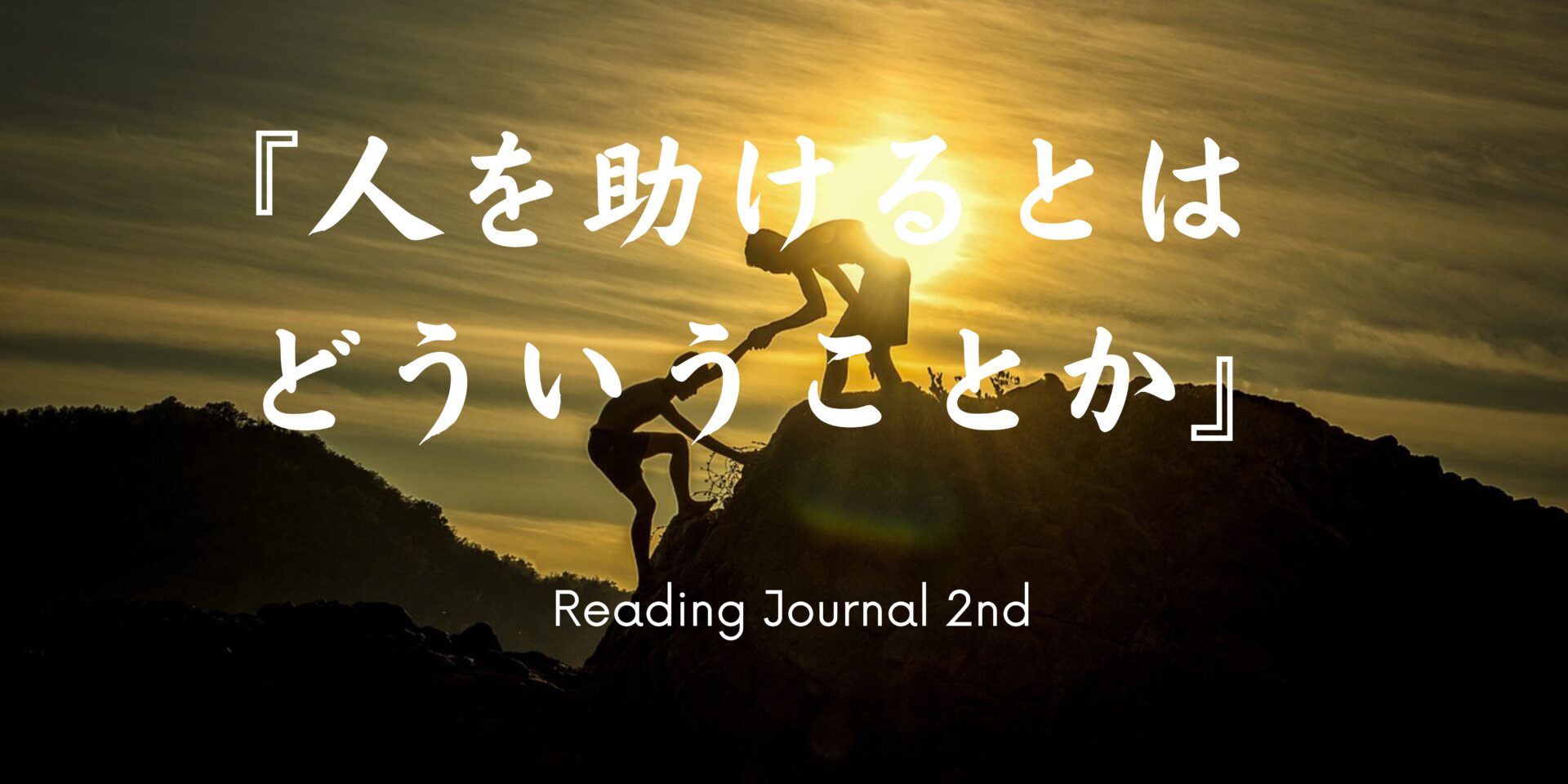


コメント