『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
解説 金井壽宏(前半)
この本の最後に監訳者金井壽宏による「解説」である。解説では、本書の内容(「支援学」)にとどまらず、エドガー・H・シャインの「シャイン経営学」や「シャイン組織心理学」の内容にも触れている。そしてシャインの研究歴を細かく書き記し、さらにシャインのエピソードが紹介されている。これは、シャインの愛弟子である金井ならではのことだと思う。また、金井による支援学と関係性・相互依存の問題、さらにその日本との関係にも触れられている。
この解説は”前半“と”後半“にわけてまとめ、まず”前半“は、本書の支援学と「シャイン経営学」「シャイン組織心理学」との関連と支援の3つのモードについての解説についてまとめる。それでは読み始めよう
本書について
難しいことを平易に語る。深いことなのに軽妙に語る。これは、普通なかなかできることではない。(抜粋)
金井はこのように解説を始めている。本書は著者が編み出したプロセス・コンサルテーションに関わる著書としては6冊目の本である。そして、精緻な理論モデルを提示して厳密な検証をするのではなく、(裏付けのある)持論が開陳されている本である。
これは、経営学を組織行動論の分野で開拓してきたシャインならではの叡智が、原理とコツという形で集大成されているものである。
プロセス・コンサルタントという持論
人を支援する方法として、シャインはプロセス・コンサルタントという支援方法を考えた。これはシャインの持論であるが、単なる経験からの持論ではなく、多数の諸理論により裏づけられている。
その理論として、「社会的経済学(社会学の交換理論)」(ココ参照)と「社会劇場」(ココ参照)である。ここで金井は、これらの理論は科学的で厳密な実証結果ではないが、豊かな経験から帰納され、そして文献の支持も得ている「実践的持論」であるとしている。そして、この「社会的経済学」と「社会劇場」との対比がこの本の特徴であると言っている。
シャインの経営学、組織心理学
本書はシャインの経営学、組織心理学の入門書としても役立つ。
経営学の中で「人」に焦点をあてたものが、「組織行動論」と「人材マネージメント論」である。この中で「組織行動論」は、主として組織心理学、組織社会学の影響を受けて生まれた経営学の分野である。そして、シャインはこの「組織行動論」の碩学として知られている。
本書は、組織行動論の碩学が、ともに生きる人々との関係を意味深く支援的なものにするうえで実践に役立つ書籍として上梓された。(抜粋)
シャインの経営学の系譜
ここで金井は、シャイン経営学の手引きとなるようにと、シャインの研究の系譜を詳しく紹介している。(ここでは、その項目のみ記する)
- 同調の研究
- 強制的説得(洗脳)の研究
- 組織社会化の研究
- キャリアの研究と診断
- プロセス・コンサルテーションの発明と実践
- 組織文化の研究と解読
支援実践の3モード
ここで金井は、シャインの支援実践の3モードについて、詳しい解説をしている。
専門家と医師と呼ばれるほかの二つのモードと区別することを通じて、プロセス・コンサルテーションとい独自の支援実践の様式がより明快になるであろう。(抜粋)
この3つのモードは次の3つである
- クライアントが必要としている具体的な知識や具体的なサービスという形で支援を与える専門家
- クライアントの状態を診断し、処方箋や専門的なサービスを与える医師
- 実際に必要なものを判断するため、共同で調べることによってクライアントを参加させ、情報をすべて打ち明けてもらえるほど信頼関係を築くプロセス・コンサルタント
モード① 情報やサービスを提供する専門家として役立つ人
これは、役立つ専門家としての役割である。クライアント側から見ると、専門知識を購入するというモデルであり、正解は専門家が持っているという思いこみがある。しかし実際の社会や組織の複雑な問題では、専門家だから正解を持っているとは限らない。そういうときには、プロセス・コンサルテーションを通じて共同で問題を解決する必要がある。
モード② 診断して処方箋を出す医師
これは、医師のように診断と処方箋をだすという役割である。このモードでは、支援者に権威がありクライアントは自分で問題を解決する気持ちが強くない。
支援学としてこれを見ると、専門家の助言を購入するというモード①のモデル以上に、プロセス・コンサルテーションという支援のモードからは最も遠いところに位置づけられる。(抜粋)
モード③ 公平な関係を築き、どのような支援が必要か明らかにするプロセス・コンサルタント
このモードの支援者はクライアントたちが解決にたどり着くプロセスを支援する。
シャインの支援をめぐる思考と実践では、内容が過程と対比され、内容の専門家(①のモード)と過程の促進者(③のモード)という二つがペアで説明された。
自らが、基本的には、相手の助けとなるように、ともにいるプロセスをうまく生み出してくれるという意味で、すぐれた過程促進者もしくはプロセス・コンサルタントであった。そして内容の専門家としてコメントされるときには、役割が③から①に移行していることを自覚して、そうなさっていた。(抜粋)
そして、ここで一番重要なことは、どの場面で内容の専門家としてクライアントに接し、どの場面で過程の促進者としてクライアントに接するかである。このモードをどういうタイミングでスイッチするかである。
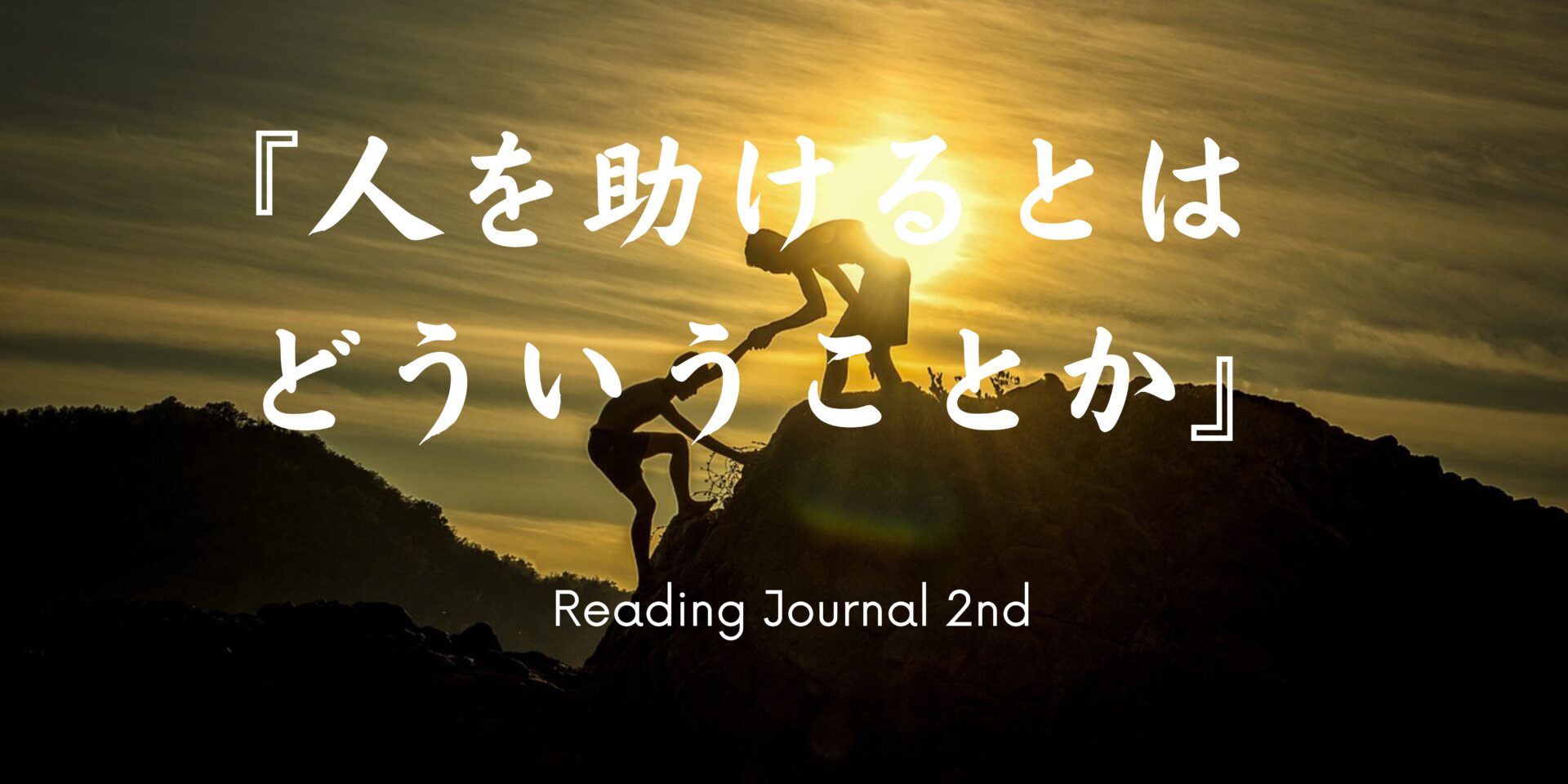
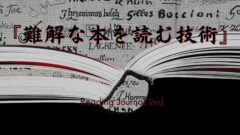

コメント