『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
① 人を助けるとはどういうことか
今日のところは、「① 人を助けるとはどういうことか」である。まえがきには「支援のさまざまな形を取り上げ、支援の概念の広さや深さについて明らかにする」と書いてある。まずは、導入ということであると思う。それでは読み始めよう。
役に立つ支援と役に立たない支援
支援には役立つ支援と役立たない支援がある。著者は、本書の目的を、この両者の違いを明らかにすることとしている。
本書での私の目標は、支援が求められたり必要とされたりするときに真の支援ができ、支援が必要だったり提供されたりするときに受け入れられるだけの充分な洞察力を読者に与えることだ。どちらも、われわれが願っているほど容易ではない。(抜粋)
ここで著者は、さまざまな状況で役に立たず、逆に相手を不快にさせてしまった支援などの例をあげている。そして、支援は見た目以上に複雑な人間的なプロセスを伴い、成功しない場合が多い、と言っている。
支援は重要だが、複雑な人間的なプロセスであるという前提から、本書は始まっている。(抜粋)
このような支援は、かなり広い範囲にわたっている概念である。ちょっとした支援からコンサルタントが組織相手に行うものまである。クライアント側から見ると、自分が求めたものだけでなく、必要としていることに気づいてくれた他者が自発的に行うものまで含まれる。このように支援は公式な状況から非公式な状況でも行われる。
では、このような広範囲の支援のプロセスに共通するものはあるだろうか?支援を成功させるために、支援者もクライアントも理解すべき文化的な意味はあるだろうか?支援のさまざまな形に共通点や相違点はあるだろうか?
公式な支援と非公式な支援
支援は、協力や協調、それ以外の他利的な行動を基盤となるプロセスである。このようなカテゴリーを「非公式の」支援と呼ぶことにする。そして、「準公式の」支援とは、さまざまなサービスを提供している専門家に、助けを求めるようなものをいう。最後に「公式な」支援は、医療サービスや法的支援の資格を持った人によって行われる。
支援の分析の大半がこの「公式の」支援についてであるが、実際には非公式の支援や準公式の支援の方がはるかに一般的である。
この公式な支援と非公式、準公式な支援との違いを考える必要がある。
支援は一つの人間関係だが、準公式の、あるいは公式の支援を申し出たり、与えたり、受けたりするプロセスは通常、個人の判断から始まる。われわれが理解しなければならないのは、支援者になる可能性がある人と、クライアントになる可能性がある人との最初の接触から、支援を生み出す関係へとどう発展していくかということである。(抜粋)
そのため、個人のイニシアティブをどのように人間関係につなげるか、関係を築くダイナミックスを理解しなければ、より効果的な支援関係は築けない。
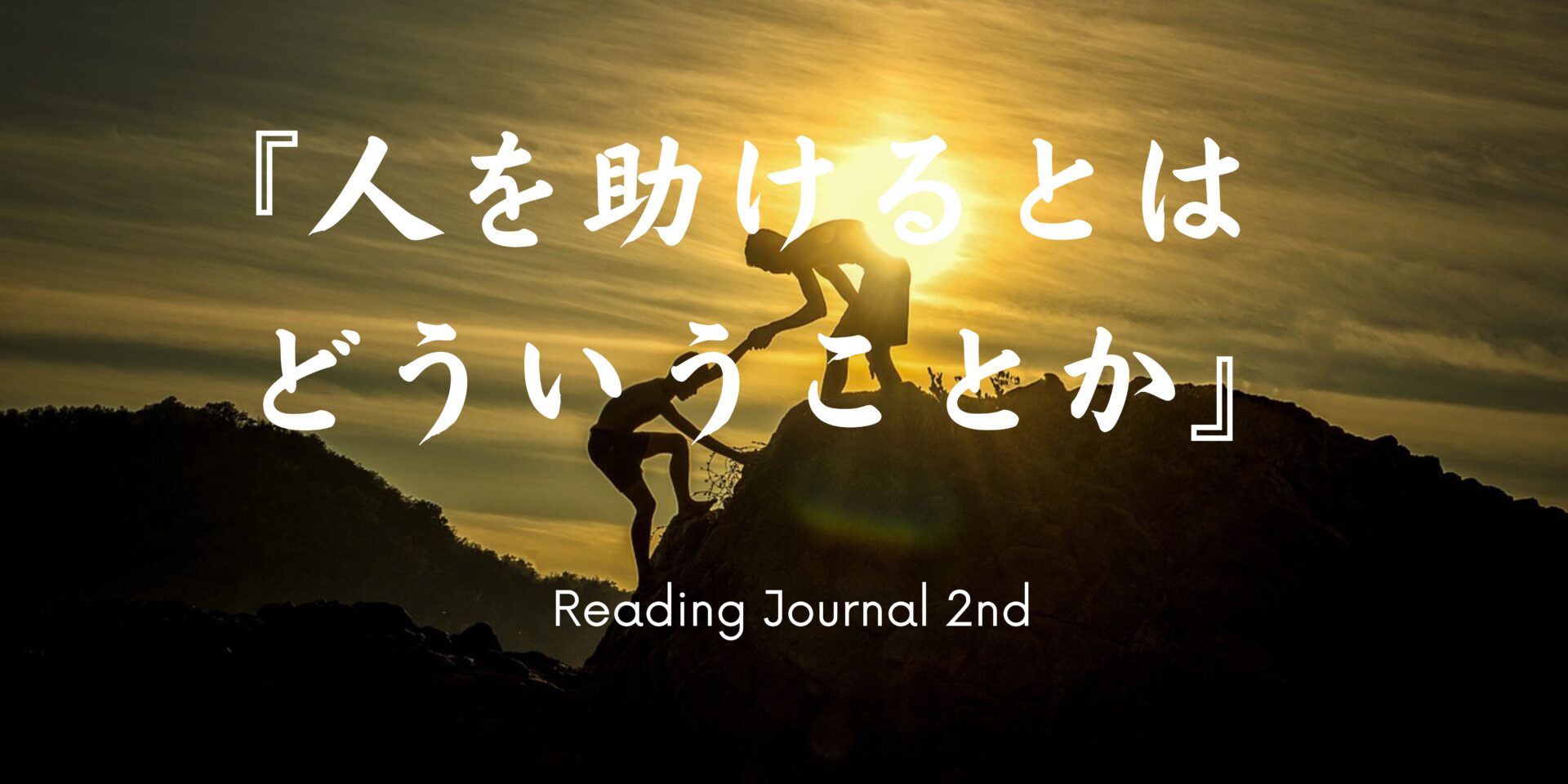


コメント