『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
⑤ 控えめな問いかけ(その2)
今日の部分は、「⑤ 控えめな問いかけ」の“その2”である。前回“その1”で、プロセス・コンサルタントの役割の中心の「控えめな問いかけ」の意義、役割について説明された。そして、プロセス・コンサルタントの役割の演じ方も支援者は選ぶことが出来き、その選択肢として四つの問いかけの種類があることが示された。今日のところ“その2”では、その問いかけの種類、つまり「純粋な問いかけ」「診断的な問いかけ」「対決的な問いかけ」「プロセス思考的な問いかけ」を一つ一つについて取り上げられる。そして“その3”は各問いかけをするタイミングについてである。それでは読み始めよう。
①.純粋な問いかけ
この純粋な問いかけには、
- クライアントの立場を確立し、自信を育てること
- クライアントが不安や情報、感情をさらけ出しても安心だと感じる状況を作ること
- クライアントの状況についての情報を集めること
- 診断や行動計画プロセスを通じてクライアントにかかわること
という目的がある。
この純粋な問いかけは、非公式な日常の支援では、あまり見られないが、公式な支援 — コンサルティング、カウンセリング、セラピーなど— の中心である。
矛盾しているようだが、純粋な問いかけは沈黙とともに始まる。支援者はボディーランゲージやアイコンタクトを通じて、話に耳を傾ける用意があることを伝えるべきだが、何も言ってはならない。(抜粋)
そして黙っていてもそれ以上有益な情報を引き出せそうにない場合は、
- 「続けてください・・・・」
- 「もっと話してください・・・」
- 「どうなっているのか教えてください・・・・」
などの、言葉で回答を促すと良い。質問は抽象的な内容を避けて、起きている事柄だけに集中してもっと詳しい例を求める。
重要なのは、問題を前提とした質問で話を促さないことだ。(抜粋)
この純粋な問いかけの場合、クライアントが述べ始めることへの対応としては、思いやりのある態度でうなずいたり、たまに小さく声を発したり、話を聞いていることを態度で示すことが必要である。クライアントにすべてを打ち明けるように励ましを与えることで、支援者は無知の領域を無くし理解を深めることができる。
いずれクライアントの話もペースが落ち、話すことを促しても続きがなじまらなくなるだろう。そして反対に支援者に「どうすればよいか」と質問してくるかもしれない。ここで重要なのは、質問に答えることにより、いきなり専門家になるという罠に陥らないことである。
クライアントが助言や提案を受ける準備が整っていないかもしれない。その場合には、さらにクライアントが情報を与える立場にとどまれるようにするために、次の段階、つまり、診断的な問いかけをする段階へと導くという選択肢がある。
要するに、クライアントには洗いざらい打ち明けてもらわなければならない。さもなければ、支援者はどんなことが起きているか、現実的に意味をつかめないからだ。また、純粋な問いかけは、クライアントが物事を診断的に考え始められそうな方向、現実的な観点から見られるような方向に持っていかなければならない。(抜粋)
なるほど、この「純粋な問いかけ」は、カウンセリングなどでは、支援の中心であると書いてあるが、確かに東山紘久の『プロカウンセラーの聞く技術』でも、東畑開人の『聞く技術 聞いてもらう技術』でも、うなずきながら相手の話をじっくり聞くということがカウンセリングの中心であると書いてある。どんな支援でもまずはここからなんだね。(つくジー)
②.診断的な問いかけ
この形式は、クライアントが話そうとしているものと違う話題にわざと焦点を当てて、相手の心理プロセスに影響を与え始める。内容に影響しないが、話の中にあるいくつかの要素に注目する。
ここで著者は、「道を尋ねられたときの例」として、
- 純粋な問いかけ:「どこへ行くつもりですか」
- 診断的な問いかけ;「どうしてそこにいくのですか」
などをあげている。
ここで大切なことは、この問いかけでは、支援者が権力やコントロールを主張していることである。そのため、正当な理由のため、支援者が意識的にそうした役割に移る場合のみに限る必要がある。
さらに著者は、この「診断的問いかけ」には四つの変化形があるとしてそれぞれについて説明している。
○感情と反応
これは、認識された問題に対してクライアント自身がどう感じ、どう反応したかに焦点を当てたもの。
(例)「それについてどう感じましたか」
この種類の質問は、クライアントが考えたくもない内容である場合があり、クライアントの不安をかきたてる可能性があるので注意が必要である。
○原因と動機
問題の原因や動機について焦点を当てる質問である。このような質問によりそのような状況になった理由を発見できる。
例)「どうやってここまできたのですか」(道に迷った運転手への質問)
この質問によりクライアントもどんな状況かを理解することになる。
○実行に移した行動、または検討中の行動
これはクライアントがしたことや、実行しようと計画していることに焦点を当てる。クライアントが行動を打ち明けていれば支援者はそれに基づいて事を進めればよいが、実際には過去や現在、未来の行為が打ち明けられることは少ない。
例)「それに対してあなたは、何をしましたか」
このような行動指向的な質問により、クライアントは、気づいてなかったこと、重要でないと考えていたこと、隠したいと思っていたことなどを考えることになる。そのためこの質問もクライアント心理プロセスに影響を与える。したがって支援者がプロセスの主導権を握る用意があるときのみ使う必要がある。
この質問により、クライアントはいくつかの出来事を別の観点から調べることになる。それは診断的視点から見ると望ましいかもしれないが、立場の均衡から言えば破壊的になる危険性がある。
○体系的な質問
最後は体系的な質問である。普通の場合、クライアントの話には、他の人が登場する。支援者は、他の人の反応や行動を、クライアントがどう見ているか知ることが重要な時がある。
したがって、家族療養士が体系的な質問とか円環的質問法と見なす問いかけをする可能性がある。(抜粋)
こうした質問は、クライアント自身の物事の判断力を育てて、治療行為からどんな結果が生れるかをはっきり考えられるようにするのが目的である。
最後に著者は、診断的質問の注意点について次のように言っている。
ここにあげた四種類の診断的質問は、クライアントの心理作用を促し、自己認識を助けてくれる。しかし、あくまでも質問であって、特に何かの解決策をほのめかすわけではない。(抜粋)
③.対決的な問いかけ
「純粋な問いかけ」「診断的な問いかけ」につづき、3つ目は「対決的な問いかけ」である。この対決的な問いかけの本質は、支援者がプロセスや内容に関して自分自身の発想を会話に差し込むことである。つまり、詳しく話すようにクライアントを促すだけでなく、支援者はクライアントが思いつかないような提案をしたり意見を述べたりする。
そうした介入のしかたは、専門家や医師の役割を強く帯びるので、有効なコミュニケーションを可能にするだけの信頼や公平さが、充分に関係の中で育ったと支援者が感じた場合に用いるべきだ。(抜粋)
例)「次のようなことはできませんか」(具体的な提案をあげる)
この問いかけは、クライアントが対処しなければならない新しい発想や概念、仮説、意見などものである。これが望ましいかどうかは、クライアントが一段低い位置にいることをさらに感じるかどうかである。
このような介入の仕方は、クライアントが自分の話を捨てて支援者の提供した枠組みで対処しようとすること、さらに、クライアントからの新たな情報が得づらくなることなどの危険性がある。
④.プロセス指向的な問いかけ
支援者は、クライアントの状況や内容から、その場で起きているクライアントと支援者の相互関係へ視点を移すことはいつでもできる。それがプロセス思考の問いかけである。その目的は、そこには相互関係が働いていて分析できるものだとクライアントに意識させることである。
例)「私たちはうまくいっているでしょうか」、「私の質問はあなたの役に立っているでしょうか」など
このプロセス指向の問いかけは、他の種類の問いかけと結びつけられる。
このような問いかけにより、クライアントが支援者をどのように見ているか、どれくらい信頼があるかを評価できる。
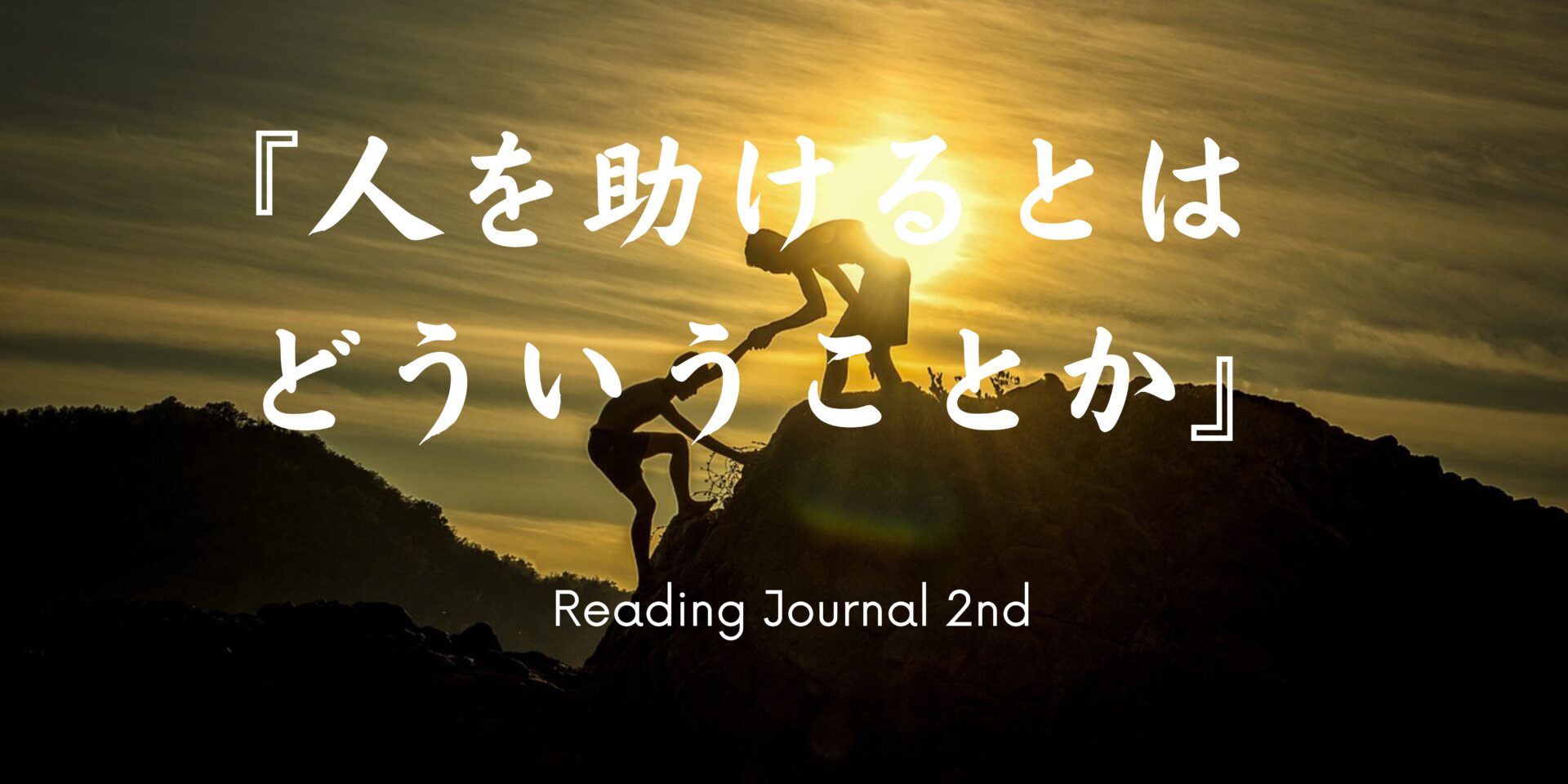
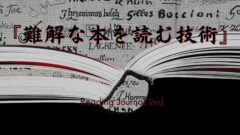

コメント