『ヘッセの読書術』ヘルマン・ヘッセ 著、思想社、2004年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『ヘッセの読書術』
メルカリを導入してみた。けっこういろんな本が売りに出されているなぁ~、と思ってみていると、この本、ずばり!『ヘッセの読書術』てのがあった。ヘルマン・ヘッセというと大作家中の大作家っていうイメージだし、かたいかな?と思ったので、買ってみました。それでは読み始めますかね。
『ヘッセの読書術』を読み終わりました。この本は、ヘルマン・ヘッセの読書に関するエッセイを集めた書、“Hermann Hesse:Die Welt der Bücher”の翻訳である。そして、訳者あとがきによれば、収録された六十一タイトルの内、十三タイトル(分量にして三分の一弱)を訳出したとある。
そういうこともあってか、収録されているエッセイは、長いものから短いものまで、内容も、ちゃんとしたもの?から、気軽なものまでさまざまでした。
おそらく本書の目玉は、一番長い「世界文学文庫/世界文学文庫リスト」である。脚注を入れないで本編が48ページ、リストが39ページもある。これは、「レクラム文庫」の依頼で書いた読書案内であり、レクラム文庫の一冊として刊行されたものとのこと。そして、そのリストは、日本の読者の便宜を考え“日本語で読める翻訳での形”でリストとなっている。
その内容は、このようなリストを作るのは困難としながら、ヘッセが古今東西の読むべき本をあげていくというものである。大作家で大読書かであるヘッセならではの精緻なものであるが、古代などはともかく、時代が新しくなるとほぼ知らない名前で埋め尽くされてしまって・・・・まぁ、ボク程度では、どうにもならん、って感じでした。読者の方にもドイツ文学、世界文学にそれなりに深い造詣が必要みたいでした。
ちなみに、この部分は、『世界文学をどう読むか』(新潮文庫)が先訳であるそうで、この部分だけを読みたい人は、これでよいのかと思います。(まぁ目玉のリストの部分をどう思うか!っていう問題もありますが)
ヘッセは、希代の読書家であるにとどまらず、本のマニアであったようで、ところどころに「本道楽」の話が、挟み込まれている。蔵書をする場合に、その本の最良の版を買うべきだとか、どのように本を扱うべきかとか、そしてなんと蔵書の見栄えなどを考えて専門家に再製本させるだとか・・・・結構すごい。
「本のほこりを払う」というエッセイは、文字通り、引っ越しのためにヘッセが一冊ずつ丁寧に本のほこりをはらい、包装するという作業の中で心に浮かんだ思い出などが書いてあるのだが、その中でヘッセがこの作業に打ち込む理由の一つに、青年期に書店兼古書店員をしていた時に、古い組合の規則にのっとった正式な手続きで本の取り扱い方を習得したから、と言っている。そういう部分まで、本格的な本マニアであったようである。
ヘッセは、新聞が嫌いなようで、ところどころで、「そんなものを読まないで本を読もう!」的なことが見え隠れする。しかし、ホテルに滞在していたときに、暖房設備が故障してしまい、しかたなくベッドに潜り込んだ、「ベッドで読んだもの」というエッセイである。日頃の全然新聞を読まないことを規則としていながら、ホテルに何一つ読むものを持っていずに、しかたなく新聞を二部もってベッドに潜り込む。午後の間中新聞を読んでいたのだが、結局、記事に登場したツェッペリン飛行船のエッケナー博士との思いでが最大のニュースだった。
彼は戦争中に将軍にならなかった。インフレのときに銀行家にならなかった。彼はあいかわらず造船技師で機長である。彼は自分の仕事を忠実に果たしてきたのだ。
二つの新聞から私は心に流れ込んだこれほどたくさんの頭を混乱させるニュースのただ中にあって、このニュースは心安まるものであった。(抜粋)
ここでちょっと気になった。ツェッペリン飛行船というと…確か、大事故を起こした・・・ような気がする。じゃ、エッケナー博士はどうなっちゃったんだろう?
でも、大丈夫!ウィキペディア「フーゴー・エッケナー」の項によると、エッケナー博士は、ナチスに反対の立場を取ったため、ナチスはツェッペリン飛行船会社を国営化し、彼から権限を奪ってしまった、とある。そして、ヒンデンブルク号の事故の時は乗船していなかったそうです。
さらに余分なことを書きますと、『なぜ古典を読むのか』の中で、カルヴァーノは、「時事問題にかかわる印刷物は、月並みで不快なもの」としながら、時事問題は自分がどこに立っているかをわからせてくれる、としている。そのため、「古典を有効に読む人間は、同時に時事問題を適宜に併せ読む必要がある」と言っている。そして、古典の規則⑬において
時事問題の騒音をBGMにしてしまうのが古典である。同時に、このBGMの喧騒はあくまでも必要なのだ。(抜粋)
と、結論づけているのでした。
関連図書:
ヘルマン・ヘッセ (著)『ヘッセの読書術』、草思社(草思社文庫)、2013年
ヘルマン・ヘッセ (著)『世界文学をどう読むか』、新潮社(新潮文庫)、1951年
イタロ・カルヴァーノ (著)『なぜ古典を読むのか』、みすず書房、1997年
目次
書物(詩)
書物とのつきあい
本を読むことと所有すること
保養地での読みもの
言葉
読書について
世界文学文庫/世界文学文献リスト
ベッドで読んだもの
本の魔力
本のほこりを払う
愛読書
日本のある若い同僚に
「パン(ブルート)」という言葉について
書くことと書かれたもの
出典
訳者あとがき
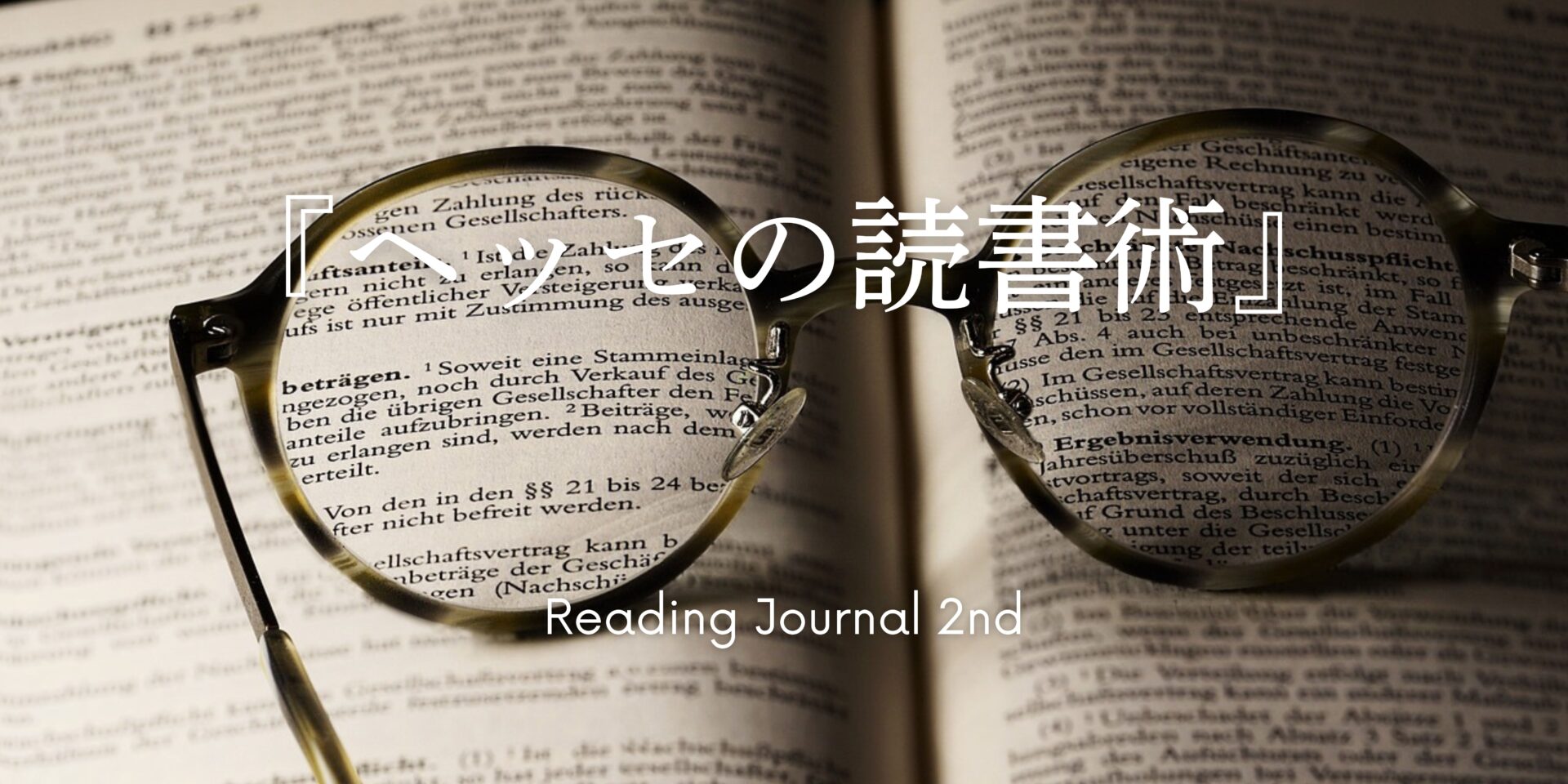
-120x68.jpg)

コメント