『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4章 外国語学習のメカニズム -- 言語はルールで割り切れない (その1)
ここから“第4章 「外国語学習のメカニズム」である。ここでのテーマは、「外国語ができるようになるとはどういうことか、そのプロセスを考える」である。そのために本章では、
- (習得の対象となる)言語の本質
- 外国語学習のメカニズム
について述べられる。
第3章は、3つに分け“その1”で「言語の特質-何を習得すべきか」について、”その2”で「言語の習得のメカニズム、主にインプット仮説」について、そして”その3”で「インプット仮説を踏まえた外国語学習のメカニズム」についてまとめる事にする。それでは、読み始めよう。
「言語能力」、「談話能力」、「社会言語能力」及び「コミュニケーション能力」
外国語を習得するためには、「音声」、「単語の知識」「文法の知識」が必要である。しかし、これだけの知識で出来るのはせいぜい正しい文を作るということだけである。
この一文レベルならば正しい文を作れるという能力を「言語能力(linguistic competence)」もしくは「文法能力(grammatical competence)」という。そして、その一文をうまくつなげて会話する能力を「談話能力(discourse competence)」という。
そして、この談話能力があったとしても、社会的に「適切な」言語を使う能力はまた別物で、それを「社会言語能力(sociolinguistic competence)」という。
このような3つの能力があって初めて普通に会話することが出来る。そのため、これらを総称して「コミュニケーション能力(communicative competence)」とよぶ。
またコミュニケーション上に問題が起こった時に対処するために必要な「方略的能力(strategic competence)」もコミュニケーション能力の一部と考えられている。
言語はルールだけでは割り切れない
「音声」「単語」「文法」の知識だけでは、外国語を使えるようにはならないが、さらに「単語」と「文法」を組み合わせただけで、正しい文が作れるという考えも、間違いである。
ここで著者は、AとBの具体的な例文をもってこのことを解説している。
- A:文法的に問題ないが非常に奇妙な文
- B:より自然な文
単語と文法を勉強だけでは、Aのような文は書けるが、Bのような自然な文が書けるわけではない。その理由は様々でありが、一例として「文法規則の適用範囲」や「様々な慣用句、熟語、イデオムなどの存在とその使用制限」などがあげられる。
このような母語話者にとって誰に教わるわけでもなく身に着けている知識があり、その意味で、単語と文法だけでは自然な第二言語を習得することはできないことは明らかである。
このように「言語はルールだけでは割り切れない」ということを知っておくことはじつは大事なことである。そして「曖昧性を容認できる」できる性質が外国語学習の成功に結びつく。
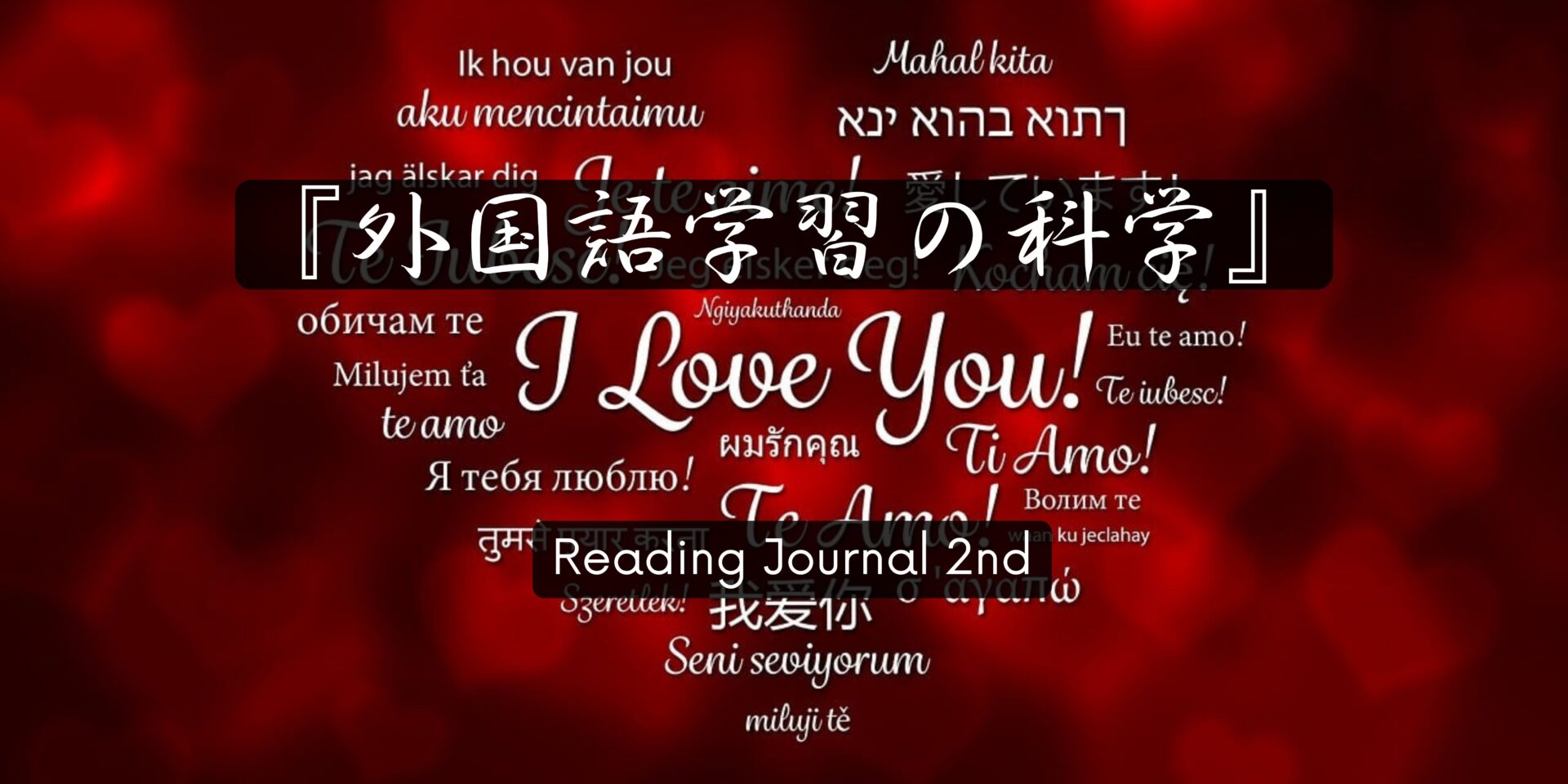


コメント