『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3章 どんな学習者が外国語学習に成功するか -- 個人差と動機づけの問題 (後半)
今日のところは第3章の”後半“である。これまで外国語学習者が学習する際に重要な要因について、第2章(前半、後半)で「学習開始年齢(臨界期問題)」を、そして前回、第3章の”前半“で「外国語学習適性」が取り扱われた。そして今日のところ第3章”後半“での話題は、「動機づけ」である。では読み始めよう。
英語が苦手な日本人と動機づけ
日本人は、英語が苦手である。たとえばTOEFLの得点はアジアの中で最低ランクである。この原因の一つは、言語間距離にあるが、それだけでは、アジアの他の国も同じように言語間距離があるので説明がつかない。そして、日本人が英語苦手であるもう一つの大きな理由は、「動機づけ」の弱さがある。フィリピンやインド、シンガポールなど英語ができなければ社会的、経済的に不利になる国では、学習の動機が非常に強くなる。
ロバート・ガードナーの「統合的動機づけ」「道具的動機づけ」
動機づけには、
- 実利的動機(道具的動機づけ)・・・・英語はほとんどの場合入試科目となっている。
- 文化的動機(統合的動機づけ)・・・・外国人とコミュニケーションをとりたい、外国語で映画を観たい。
がある。
この動機づけは、ロバート・ガードナーが中心になって研究された。ガードナーは、文化的動機づけについて、「学習対象言語を話す人や文化に好意を持っている学習者が外国語学習に成功する」(「統合的動機づけ」)という仮説を立て、これを支持する研究結果を発表した。
一方、実利的な学習動機を「道具的動機づけ」と名づける。ガードナーが初期に行ったカナダでの研究では、道具的動機づけはあまり重要でないという結果だった。しかし、その後にフィリピンで行った研究では、道具的動機づけも重要であることがわかった。道具的動機づけは、その環境によって重要度が異なることが考えられる。
以上を総合して、ガードナーは、道具的動機づけも外国語学習の成功に結びつくが、その成功は短期的なもので、長期的には統合的動機づけの方が重要になり、また統合的動機づけはほとんどの研究で外国語学習の成功と結びついている、ということを強調しています。(抜粋)
ただし、道具的動機づけも、それがずっと続く状況ならば学習を続けることは可能である。
結論としては、道具的だろうが、統合的だろうが、どちらでもよいので、いかに自分を学習動機が高まるような状況に持続的におけるかが外国語学習成功のカギだということでしょう。
相関をとる研究の問題点
ここで紹介されたガードナーの研究方法は、ほとんど相関関係を見るものであった。ここで、
Aという指標とBという指標の相関があるといっても、AがBの原因になっている(あるいはBがAの原因になっている)とはかぎりません。(抜粋)
つまり相関関係と因果関係は違うので、注意が必要である。因果関係まで見る場合は、相関を見る項目以外の外的要因を統計的にそろえて、その他と影響が入らないようにコントロールしたり、見たい要因のみを変えた実験をしたりする必要がある。
また、相関関係を見る研究には、もう一つ「AとBのあいだの相関は、どちらがどちらを引き起こしているかわからない」という問題がある。これは動機づけの研究の大きな問題のひとつである。
たとえばフランス語話者に対する感情的好意がフランス語学習の成功を引き起こすのか、フランス語学習に成功したからフランス語話者に好意を持つようになったかは、わからないということである。また、相乗効果を起こしている可能性もある。
先のガードナーらは、複雑な統計的手法を駆使して、動機づけと外国語学習の達成度には単なる相関があるだけでなく、動機づけが学習の成功を「引き起こしている」と主張していますが、この点についても、様々な議論があります。(抜粋)
ゾルタン・ドルニュイの動機づけと学習プロセスの研究
そのため、一九九〇年ころから動機づけと学習のプロセスの関連を見る研究がゾルタン・ドルニュイが中心となって盛んにおこなわれている。
この研究で明らかになってきたのは、それまでの研究ではあまり重視されなかった、学習者がどういう学習活動に従事するかとか、教師がどういう教え方をするかが動機づけを大きく左右するということです。(抜粋)
これにより、比較的安定な「文化的興味(統合的動機づけ)」や「実利的興味(道具的動機づけ)」とは別に、「個別の学習活動に関する学習者の評価」が動機づけに大きく影響し、そしてこのような動機付けはそれほど安定していないことがわかった。
この「個別の学習活動に関する学習者の評価」が動機づけに大きく影響するという部分は、付け足しのようで付け足しでないと思った。用語が難しいので、なんだかな?と思ったが、要するに先生の教え方が上手いと生徒のモチベーションが上がっちゃうってことですよね。「文化的興味」とか「実利的興味」が動機づけなるって言っても、先生はどうすることもできない。せいぜい「これ試験にでるよ~」って脅すくらいしかできん。でも、「教え方で生徒のモチベーションを上げられる」とわかれば、頑張れるんじゃないかな?先生がんばれ~(つくジー)
グローバル化という動機づけ
日本人の動機づけの弱さが、英語下手の理由のひとつであることは否定できないが、最近は事情が変わってきている。経済のグローバル化により、企業の経済活動が国際化しているため、コミュニケーションツールとしての英語のニーズが高まっている。
英語はすでに世界語になっている、という現実をふまえて、コミュニケーションの手段として習得することをめざすべきです。またその際、不要なネイティブスピーカー信仰を捨てることも大切なのは言うまでもありません。「ネイティブに近い英語」を目指すのは単にコミュニケーションの効率化という便宜上のことであって、それ自体に価値があるわけでなないのですから。(抜粋)
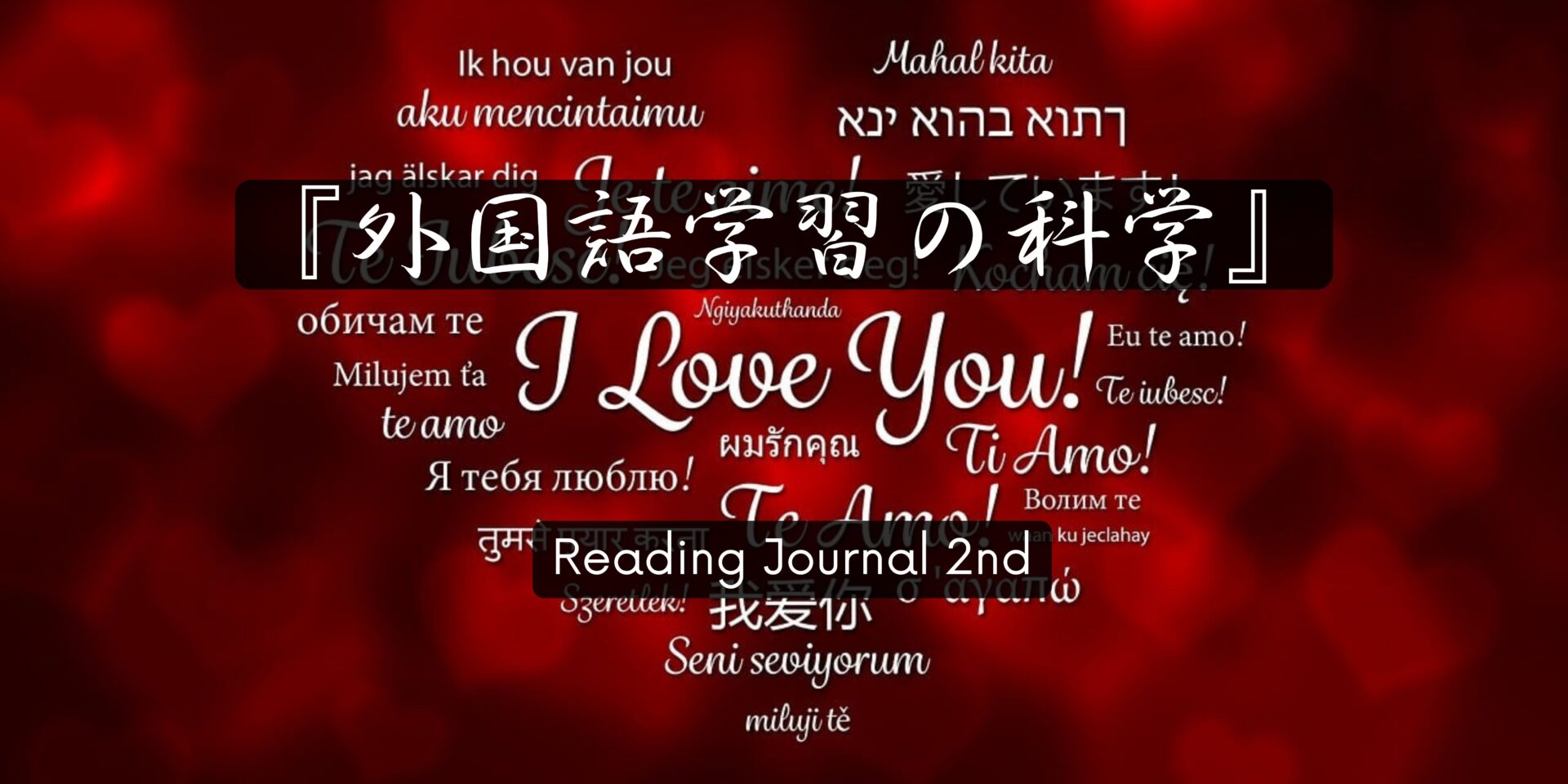


コメント