『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3章 どんな学習者が外国語学習に成功するか -- 個人差と動機づけの問題 (前半)
今日から“第3章 どんな学習者が外国語学習に成功するか”である。
第二言語習得(SLA)の研究から学習者が外国語学習に成功するかを予測する最も重要な要因として、
- 学習開始年齢
- 外国語学習適性
- 動機づけ
の3つがあることがわかってきた(ココ参照)。このうち前章・第二章では、①の「学習開始年齢」の研究について「臨界期仮説」を中心に取り扱われた。本章・第三章では、②の「外国語学習適正」と③の「動機づけ」の問題が扱われる。第三章は2つに分け“前半”で「外国語学習適正」を“後半”で「動機づけ」の問題をまとめることにする。それでは、読み始めよう。
外国語学習適正と動機づけ
外国語学習がうまくいくかは年齢(ココ参照)の他に、個人差に基づく要因がある。とくに「外国語学習適正」は、重要なものである。この適正は、比較的安定したもので一生の間あまり変わることがない。そしてもう一つ「動機づけ」も要因と考えられる。これは時間とともに変化する可能性が強い(動機づけは”後半”でまとめる)。
外国語学習適性とMLAT
一般に「語学の才能がある」という人がいるが、外国語学習に向いている人は実際にいる。この適正の影響の研究は、外国語学習に適した人を選別するという実利的な理由から始まった。
外国語学習に適性を測るテストとしてもっとも有名なのは、MLAT(Modern Language Aptitude Test = 現代語適正テスト)である。適正に関する研究は、このMLATの得点と、学習結果に基づいている。このMLATは、次の四つの異なったタイプの能力を測るように作成されている。
- 音に対する敏感さ
- 文法に関する敏感さ
- 意味と言語形式との関連パターンを見つけ出す能力
- 暗記する能力
「知能・知性」と「外国語適正」の関係についても多くの研究がある。IQテストとMLATの結果を比較すると、「この二つの能力にはかなり重なっている部分はあるが、全く同じというわけでもない」。つまり、「外国語学習特有の適正」というものがあるという結果になっている。
バイリンガル研究で使われる概念に
- 「日常言語能力(Basic Interpersonal Communication Skills = BICS)」・・・日常会話的能力
- 「認知学習言語的能力(Cognitive Academic Language Proficiency = CALP)」・・・教科学習などに必要な複雑な内容について読んだり書いたり、ディスカッションしたりするための認知面の言語能力
があるが、「認知学習言語的能力」と知能テストは相関があるが、日常言語能力との相関は低いことが分かっている。実際に、IQの高い学習者には、文法中心方式が、IQがあまり高くない学習者には口頭練習中心のコミュニカティブ・アプローチのほうが効果的ということを示した研究もある。
大人になってからネイティブのようになれるか(臨界期仮説の反証)
一九九〇年にマイケル・ロングは、「もし大人になってから外国語学習を始めた人でネイティブのようになったケースが一つでもあれば、それは臨界期仮説の反証になる」と主張した。そのため本当に意味でネイティブのようになった人がいるかという研究がかなりされた。
ここでは、一九九四年のアイユーブのエジプトに渡ったイギリス人女性の研究やボンガーツのオランダ人の英語発音習得関する研究が紹介されている。しかし、方法論的な問題に加え何をもってネイティブと同じと判断するか問題点などもあり、臨界期仮説の例外を探すことは難しい。
なお、ここでネイティブのようになることが可能かどうか、という調査しているのはネイティブのようになることが重要だからではなく、それを明らかにすることが臨界期仮説の検証になるという研究上の理由です。(抜粋)
例外的成功者に共通の特徴(高い記憶力)
一九九八年にピーター・スキーアンは、著書の中で「例外的成功者」の特質を検討した。彼はMLATで提案された四つの要因を三つにまとめて、
- 音声認識能力
- 言語分析能力
- 記憶
を言語学習適性の要素として提案している。そして、「例外的に思春期をすぎてから成功した学習者に共通する特性は、高い記憶力」だという一般化を提案している。
つまり、ネイティブのようになるには、ルールを覚えてそれを適用するよりも、膨大な数のフレーズを覚えて使いこなすことが重要である。これは次章で議論するように言葉の本質と関わり、我々の話すことはかなりの部分が決まり文句からなっているからである。
しかし、このような研究を応用することの危うさを認識する必要がある。彼らは高い記憶力があるため、記憶ストラテジーが使えたが、ふつうの人に同じことが出来るとは限らない。「達人」の学習法も、参考にはなるが、そのまま使えるかどうかは別である。
適性にあった学習法(「適正処遇交互作用」)
学習者の適正には、多様性がある。そのため個人の学習プロフィールにあわせた学習法が必要となる。
一九八一年にウエッシュは、「言語分析力適性」と「記憶力適性」が高いグループにそれぞれ、どのような学習法が効果的かを調べた。結果的には、「言語分析力適性」が高いグループは、文法中心の授業、「記憶力適性」が高いグループは暗記中心の授業のほうが効果的であった。
最近は、適正と学習法をマッチさせる(「適正処遇交互作用」)研究が盛んになっている。
年齢と適性
適性と年齢については、面白い結果が出ている。いくつかの研究で「子どもの学習者には、「言語分析能力」に関する適性は関係なく、関係するのは「記憶力」だけである」という結果が示されている。
たとえばロバート・ディカイザーのハンガリーコニュニティーでの研究では、一六歳以降にアメリカに移住した人は、文法分析能力の適性が高い人だけ英語がネイティブに近いレベルとなったが、一六歳になる前に移住した人は適性に関係なく、全員がそのレベルに達した。
またブリジット・ハーリーの研究では、イマージョン(教科内容を外国語で教える教育方法)でフランス語を学んだ英語母語の学習者は、小学校一年生から始めた子供は「主に記憶力」とフランス語の成績が相関を示し、七年生から始めた子供は「主に文法分析能力」と相関があった。
性差と適性
「女性のほうが語学に向いている」ということは、ある程度言えることが研究結果から分かっている。はっきりとした理由は分かっていないが、可能性として男性よりも女性のほうが外国語学習に肯定的態度を持っている場合が多いことがある。また、母語の言語能力に関しても男性よりも女性のほうが概ね優れている。また、生まれつきの男女の性差が原因とも言われている。生まれたばかりの赤ちゃんは、遊んでいるとき女の子はお母さんの顔を、男の子はおもちゃのほうをよく見ることが分かっている。
外向的、内向的性格と適性
外向的性格と内向的性格と外国語学習の習得について、外向性の人は「日常言語能力」が高く、内向性の人は「認知学習言語能力」が高いという仮説についての研究がある。結果的には、外向性の人と「日常言語能力」との相関はあったが、内向性の人と「認知学習的言語能力」との相関はなかった。
しかし、「性格的な外向性」よりも「外向的行動」のほうに強い相関があった。外向的性格の人でも会話練習のない授業では、外向性を活かすことが出来ないということであり、外向的行動を実際にすることが重要である。
自己抑制と適性
外国語で話すことは母語で話すよりも上手くいかない。そこで自我が傷つかないように抑制している人よりも、自由に新しいキャラクタを演じられる人の方が、外国語学習に向いているのではないかという仮説が成り立つ。それを調べた研究がある。
一九七二年にアレクサンダー・ギオラは、お酒の効力と外国語学習の適性について研究をした。それによると「適量>ゼロ>飲みすぎ」の順で成績が良かった。これは直観的に納得のいく結果である。
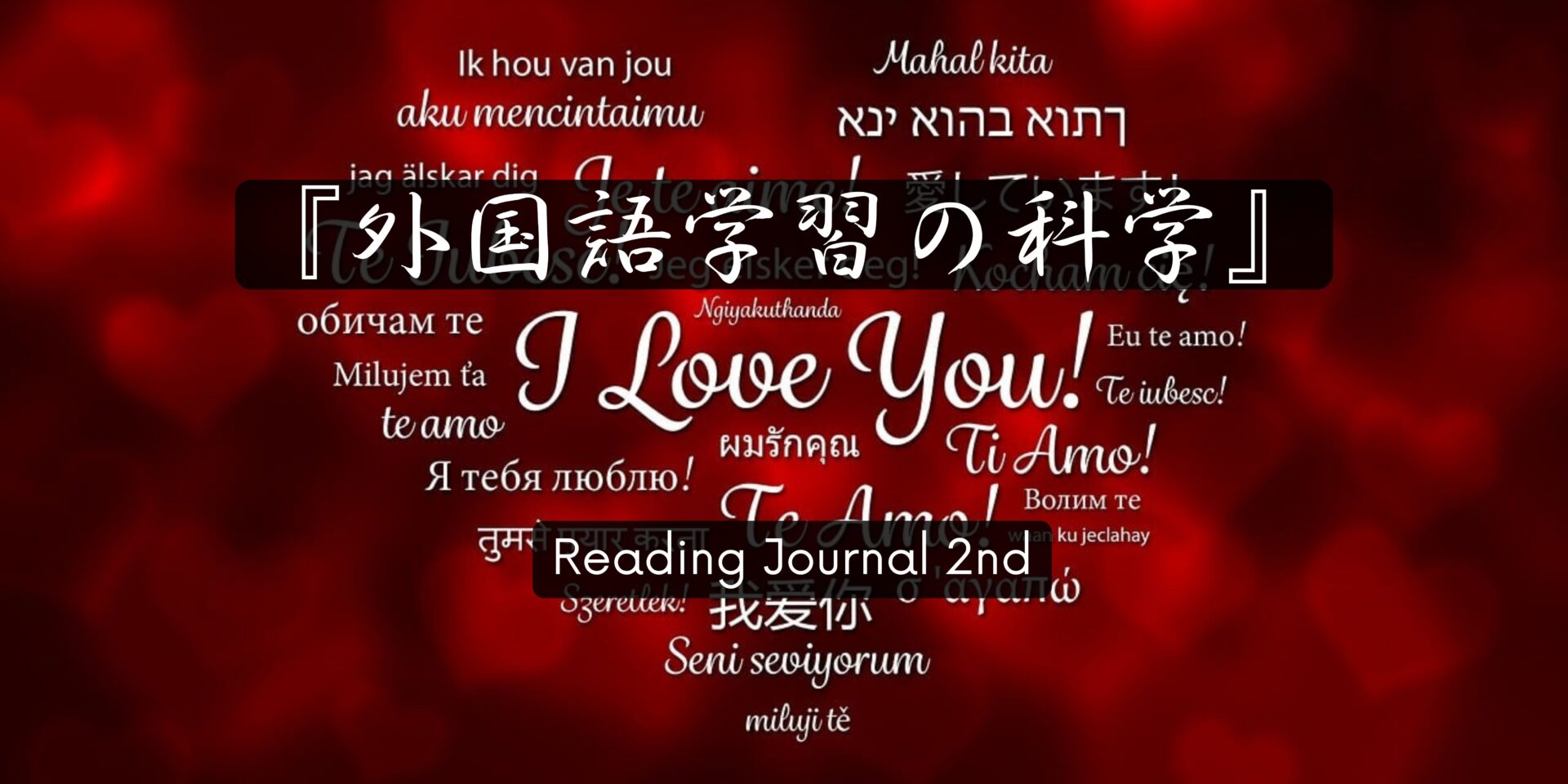


コメント