『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 なぜ子どもはことばが習得できるのか -- 「臨界期仮説」を考える (前半)
今日から”第2章 なぜ子供は言葉が習得できるか”である。前章(“前半“、”後半“)では、母語と学習言語の言語間距離により外国語学習の難易度に違いが出ること。そしてその学習を妨げる要因として、母語の言語転移があることを学んだ。第2章では、なぜ子どもの母語習得はほとんど成功するのに、大人の第二言語習得はほとんど失敗するのかについて、「臨界期仮説」を通して考えている。第2章は、前半と後半に分けてまとめるとする。それでは、読み始めよう。
外国語学習に成功するための要因
幼児の母語習得はほとんどの場合成功するのに、大人の第二言語習得(SLA)はほとんどの場合失敗に終わります。(抜粋)
ただし、失敗に終わるといってもその程度は、さまざまであり、非常に効率よく習得する人もいるがどうしようもないくらい進歩が遅い人もいる。また、どのような学習者が習得に成功するか、も面白い問題である。
今までの研究から学習者が外国語学習に成功するかを予測する最も重要な要因として、
- 学習開始年齢
- 外国語学習適正
- 動機づけ
の3つの要因があると言われている。本章では、まずこの中の①の年齢と外国語習得の関係について考える。②、③については次章・第3章。
臨界期仮説
年齢が外国語の習得に非常に大きな影響を与えるということは、第二言語習得研究では定説になっている。よく知られているのは「臨界期仮説」という考え方である。
「臨界期仮説」とは、「外国語学習には、臨界期、すなわち、この時期を過ぎると学習が不可能になる期間がある」、という仮説である。
ただし、この学習年齢が成否に強い影響をあたえる、ということは研究者の間で意見が一致しているが、臨界期というものが本当にあるのか、あるとすればそれは何歳くらいなのか、についてはまだ合意がない。
「臨界期仮説」への賛否
一般に「外国語学習は若いほど有利」と思われているが、一九七〇年後半にそれまでの研究を詳細に検討したところ、子どもと大人を比べた場合、「大人の方が早いが、子どもの方がすぐれている」という結果となった。
このような研究もあり、第二言語習得に関して年齢の影響が強い、という点は合意があるが、それが「臨界期」というものであるかは、意見が大きく分かれ賛成派と反対派の間には大きな溝がある。
その論争には、
- 思春期に入る一ニ、三歳を超えると学習能力がガクッとさがるのか、年齢が上がるにつれて徐々に下がるのかという点
- なぜ年齢の影響がそれほど強いのかという点
などがある。そしてその説明には、
- 脳神経生物学的説明・・・脳の構造が特定の年齢までに変化するのを終えるため、言語習得に関する脳の柔軟性、可塑性が大人になると失われる
- 「認知的」説明・・・・「大人はすでに抽象的分析能力が身についているため、言語習得が自然に行えない」。子供は、細かい分析をしないので、母語を学ぶのと同じような自然に習得できる。
- 心理的態度の違いによる説明・・・・子どもは自意識が発達していないので、外国の人々と自然に交わることが出来るが、大人は自我が発達しているため、新しい環境(外国語環境)になじめず、それが学習環境に差が出る。
- 母語フィルター・・・・最近有力なのは「母語というフィルターを通してしか外国語を処理できないという説」である。母語話者は自分の母語に都合がよい言語処理システムが確立しているため、外国語を学ぶときは、それがフィルターとなってしまい不十分な習得しか達成できない。
”後半“で③の「心理的態度の違い」と④の「母語フィルター」についての検討をまとめる。
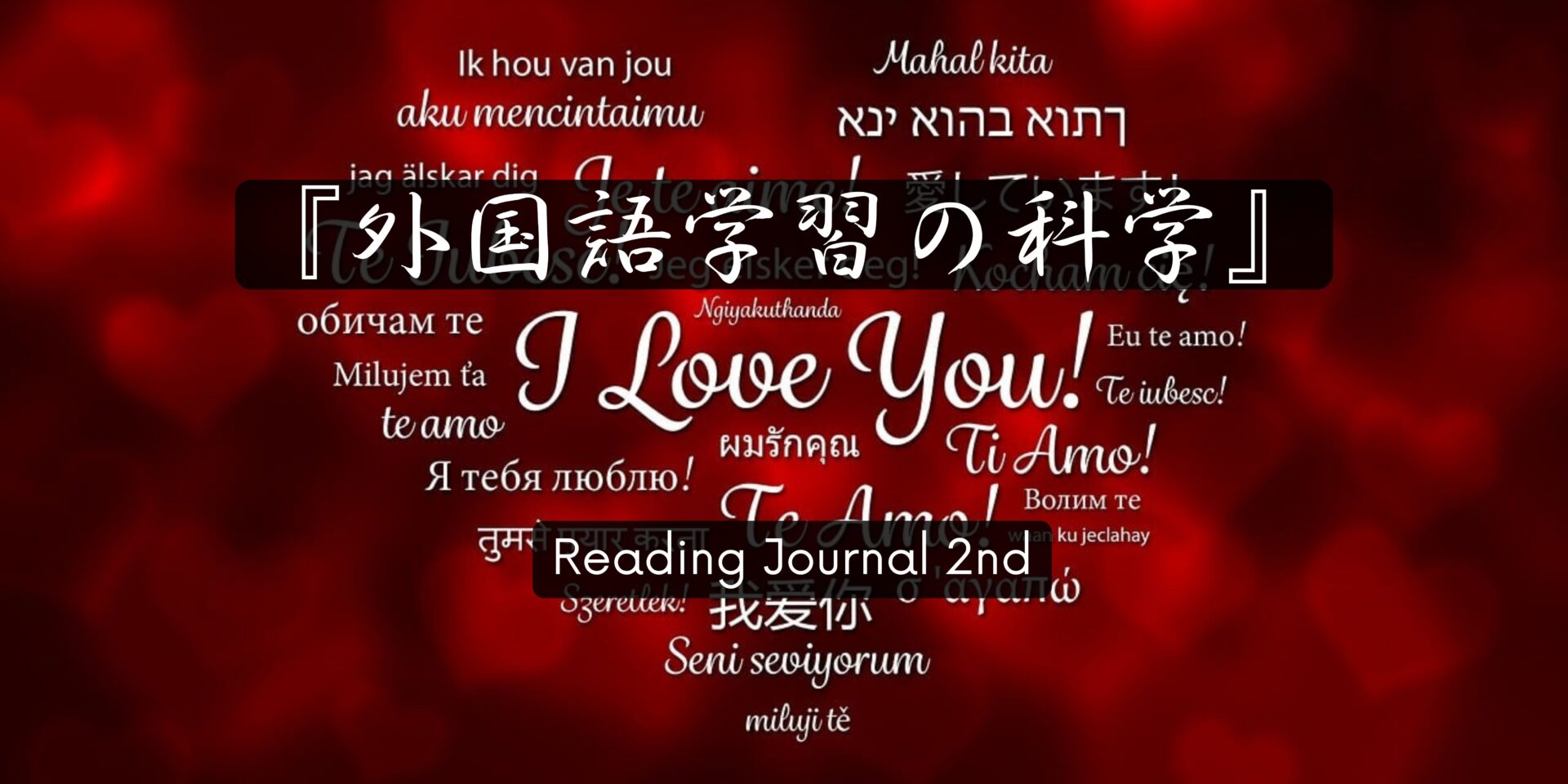


コメント