『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 外国語を身につけるために -- 第二言語習得論の成果をどう生かすか (その4)
今日のところは、第5章 「外国語を身につけるために」の“その4”である。これまでに、第二言語教育・学習の研究の変遷(その1)、外国語学習理論で重要な「習得順序」と「発達順序」(その2)、さらに、外国語学習で重要な“インプット”について(その3)が解説された。今日のところ“その4”では”アウトプット“について解説される。では、読み始めよう
アウトプット仮説
インプット仮説に関連する理論は、クラッシェンの時代より先に進んでいる。クラッシェンは、インプットを理解するには、単語やその場の状況、本人の持つ背景知識などの言語以外の知識を利用することが出来るので、知らない文法や単語があっても理解が可能になるとしている。しかしそれが、インプット理論の弱点にもなっている。
メリル・スウェインは、学習者が第二言語を聞くとき、文法知識がなくても、内語(名詞、動詞、形容詞など)を理解するだけで内容を理解できることを指摘し、そのためイマージョン教育(外国語で直接教科を教える教授法、ココを参照)を受けた学習者が、聞き取りはネイティブと変わらないレベルまでなるのに、文法や社会言語的能力では劣る理由だとしている。そして、アウトプットをすれば、文法処理をせざるを得なくなるので、インプットだけではなく、アプトプットも必要だと主張した。これが、アウトプット仮説である。
文法処理の必要性
また、ビル・バンパタンは、大事なのは理解の過程で、文法事項を実際に処理させることだと主張している。つまり教師がインプットする文をコントロールして、文法処理をしないと理解できない文を与える必要があるとしている。
つまり、第二外国語の習得のためには、単に内容を理解するだけでなく文法項目も処理する必要がある。
大切なのはインプットを理解するのに、単語、意味的情報だけでなく、文法処理を手助けすることである。そのためには、
- 計画的に、文法処理が必要な文を与えること
- フォーカス・オン・フォーム:コミュニケーション活動の中で文法も注意を向けるようにすること
の二つが提案されている。
このように、インプットが単に「意味的に理解される」だけでなく「文法的にも処理される」べきことを、教える側も、学ぶ側も常に意識していくことで、習得がより効率よくすすんでいくわけです。(抜粋)
決まり文句の危険性
イデオムなどの決まり文句は、内部構造を理解することなく暗記して使うことが出来る。そのため、知識の自動化にはつながっても、本当の意味での習得につながるかは、わからない。
これをどう防ぐかについては、まだ研究者間で論争があるとしながら、著者は、決まり文句の内部構造に気づくような、関連事項を(ある段階で)教えることで、決まり文句の生産性につながるとしている。
アウトプットの効力
インプットが言語習得の必要条件であることは、第二言語習得の意見が一致しているが、アウトプットが必要条件であるかどうかは、意見が分かれている。
アウトプット仮説を提唱したメリル・スウェインは、イマ―ジョン教育で不足しているのはアウトプットの機会であるから、アウトプットすることにより、正確さも見につくと主張している。
- アウトプットは自分に対するインプットになる
- アウトプットすることにより、自分の言語のどこにギャップがあるかがわかる。(リハーサルで同じ効果が得られる)
- アウトプットすることにより、ある表現が通じるかどうかという自分の仮説を試すことが出来る。
- アウトプットは、自動化に効用がある。
ということが言われている。この中で一番重要なのは④の自動化への効用である。
アウトプットについて注意すべきは、アウトプットそのものが言語能力の向上につながったという結果があまりないことである。
アウトプットそのものは新しい言語材料、言語知識の習得には役立たない、言いかえると、自分のすでに知っている知識を使って何かをする、ということにすぎない。(抜粋)
しかしながら、インプットだけというのも、効率が良くない。言語の習得には「インプット」と「アウトプットの必要性」が必要であるという仮説(ココ参照)が正しいならば、アウトプットも必要である。ただし、十分なインプットなしにアウトプットばかりに重点を置いても言語習得は進まない。
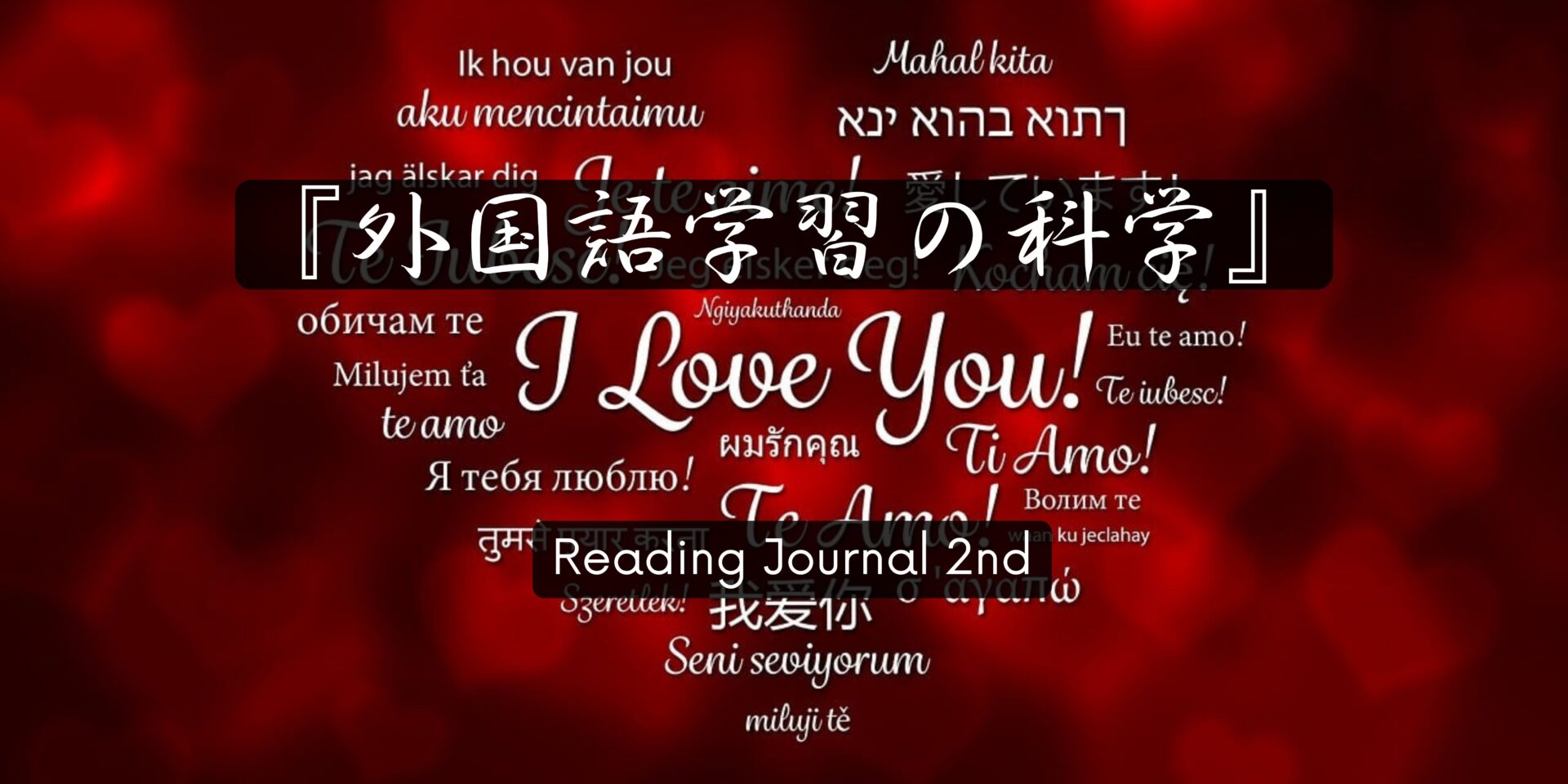


コメント