『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 外国語を身につけるために -- 第二言語習得論の成果をどう生かすか (その2)
今日のところは、第5章 「外国語を身につけるために」の“その2”である。前回“その1”は、第二言語教育・学習の研究の変遷についてであった。そしてここから、外国語教育・学習に直接かかわる応用的な側面が紹介される。今日のところ“その2”は、まず、「習得順序」と「発達順序」についてである。では、読み始めよう。
「習得順序」と「発達順序」
第二言語学習における「習得順序(acquisition order)」とは、学習者が様々な文法項目の習得順序である。これらの研究は一九八〇年代に盛んに行われ、そしてある程度の普遍性があり、母語の影響も見逃せないことがわかっている(ココ参照)。
そして、「発達順序(developmental sequence)」の研究もおこなわれている。この「習得順序」と「発達順序」の違いは、
- 「習得順序」:いくつかの文法形式(冠詞、複数形、過去形、進行形、be動詞など)の習得順序
- 「発達順序」:ある一つの言語領域(否定文、疑問文など)の発達順序。発達順序は、基本的に変えられない(普遍的)
である。ここでは、発達順序の研究として、ジョン・シュリーマンの研究が紹介されている。
さらに、この「発達順序はとびこえて習得することはできない」という主張がある。マンフレッド・ビネマンは、文法学習の発達段階は処理の複雑さのレベルによって決まるとする「処理可能性理論」を主張し、発達順序はとびこえて習得できないので、学習者の発達段階により、その少し上の段階の文法事項を教授することにより習得が進むという「教授可能性仮説」を提案した。
このような研究を通じて、文法事項の習得の道筋はある程度分かってきた。このようなことは、外国語の教師や学習者にとって重要な示唆を与える。
中間言語の可変性
エーレン・タローンの学習者言語(中間言語)の「可変性(Variation)」の研究などにより、「中間言語はつねに安定したものでなく様々な状況により異なった形で現れる」ということがわかってきた。たとえば、単語リストを読むときは正確さに注意が払われので、発音が正確になり、自由会話では発音に注意しないので、正確でなくなる。
そして、中間言語は、「社会的要因」の影響も受けることがわかっている。レスリー・ビーピは、社会心理学の応化理論(accommodation theory)を応用し、学習者が相手に心理的に接近しようとすると相手に近い言葉を話し(収集:convergence)、距離を置きたい場合は、異なった言語を使用する(分岐:divergence)ことを明らかにした。
このように、学習者が使うことばは様々な要因による影響を受けて変わります。ですから、一度話すのを聞いただけで、その学習者の持っている知識がわかる、ということはないわけです。(抜粋)
ここで著者は、第二言語習得論では、学習者の誤りを
- ミステイク:学習者がすでに明示的知識として知っているがうまく使えないために現れる誤り
- エラー:知識としても知らないためにおきる誤り
の二つに分けると言及している。
普遍的学習順序と教えることの効果
普遍的習得順序については、ロッド・エリスなどの多くの研究者は「習得のスピードと、最終的学習到達度については、教えることの効果があるが、習得順序については教えても変わらない」と考えている。
しかし、文法項目には、習得順序が決まっているコアの文法(発達的項目:developmental feature)と教えればすぐに使える文法項目(変異的項目:variational feature)があるという考え方もあるとして、ユーゲン・マイゼルのドイツ語に関する研究を紹介している。
したがって、どういう項目が教えてもすぐに習得できないもので、どういう項目は教えたら効果があるか、ということを研究して解明しないと、学習者にとってよりよいカリキュラムや教科書はできません。(抜粋)
ここで、著者は、教えることの効果として、
- 学習者が言語表現に意識的に注意を向ける(「気づき」と呼ぶ)ことにより、インプットによる自然な習得を促進する。
- 学習者が習得する言語の正しさを求めるような志向に変えていく
があると言っている。
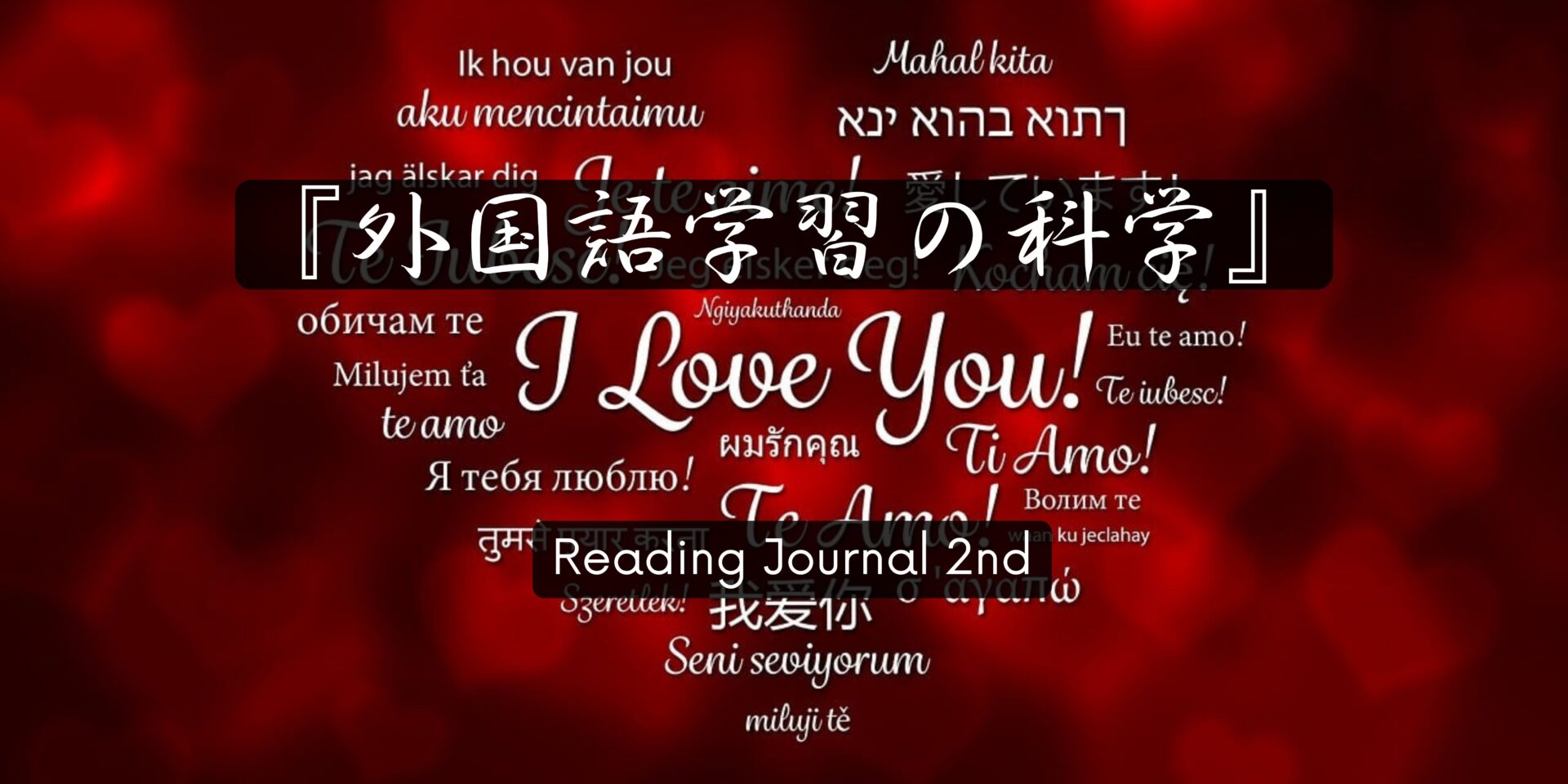


コメント