『外国語学習の科学』 白井恭弘 著、岩波書店(岩波新書)、2008年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
プロローグ
白井恭弘の『外国語学習の科学』を再読しようと思った。この本は、『外国語学習に成功する人、しない人』(岩波科学ライブラリー100、二〇〇四年)の続編である。もちろん両方とも読んだ。本当は、どうせ再読するなら、順番どおりに読もうかなとおもったんだけども、・・・・・『外国語学習に成功する人、しない人』が本棚を探しても見つからず。まぁいいや、ということに。それでは、読み始めよう。
第二言語習得(Second Language Acquisition = SLA)
今日のところは、プロローグである。
外国語を学ぶ速度や達成度には、個人差がある。この違いはどのように生まれるか。また、どのような学習法が効果的であるか。このような疑問に答えるために一九六〇年ごろ生れた学問分野が、「第二言語習得(Second Language Acquisition = SLA)」である。
子どもの母語習得(第一言語習得)と大人の外国語習得(第二言語習得)には、大きな違いがある。一番の違いは、「第一言語は、みな同様に成功する」(均質性)のに「第二言語の結果は様々」(多様性)という点である。なぜ、第二言語習得では、このような差が生まれるのか?第二言語習得研究はこのような、第二言語学習者に関する問題点を科学的に解明することを目的としている。
本書の目的は、第二言語習得研究の成果を一般向けにわかりやすく伝えることです。扱っている現象が複雑なので、まだわかっていなことも少なくありませんが、これまでの研究の結果、様々なことが明らかになっており、どんな外国語学習法がより効果的か、またどんな人が外国語学習に成功するか、といった問題に対しても、ある程度の答えた出るところまできているのです。それを社会に還元することは重要なことだとおもいます。(抜粋)
本書のねらいと構成
本書は、「学習者の立場」と「教育者の立場」という二つの観点から考察している。そして、対象としている読者層は、背景知識のない一般読者である。
構成は、
- 第1章・・・・第二言語習得に関する母語の役割を検討する
- 第2章・・・・なぜ子どもはふつう第二言語学習に成功するのに大人は多くの場合失敗するのか(臨界期問題)
- 第3章・・・・外国語学習にはどんな学習者が成功するか(適正と動機づけ)
- 第4章・・・・第二言語習得のメカニズムについて
- 第5章・・・・効果的な教授法・学習法
- 第6章・・・・具体的な学習のコツ
である。本書で紹介する外国語学習の原理は、基本的にあらゆる言語にあてはまる。しかし、実際に過去四〇年に積み重ねられてきた研究の大多数は英語の習得についてであること、日本での外国語学習の対象はほとんど英語であること、を踏まえて、この本であげる例は、大体が英語の学習者に関するものになっている。
関連図書:白井恭弘(著)『外国語学習に成功する人、しない人』、岩波書店(岩波科学ライブラリー100、2004年
目次
プロローグ [第1回]
第1章 母語を基礎に外国語は習得される [第2回][第3回]
第2章 なぜ子どもはことばが習得できるのか ──「臨界期仮説」を考える [第4回][第5回]
第3章 どんな学習者が外国語学習に成功するか ──個人差と動機づけの問題 [第6回][第7回]
第4章 外国語学習のメカニズム──言語はルールでは割り切れない [第8回][第9回][第10回]
第5章 外国語を身につけるために──第二言語習得論の成果をどう生かすか[第11回][第12回][第13回][第14回][第15回]
第6章 効果的な外国語学習法 [第16回][第17回]
あとがき
重要語
参考文献
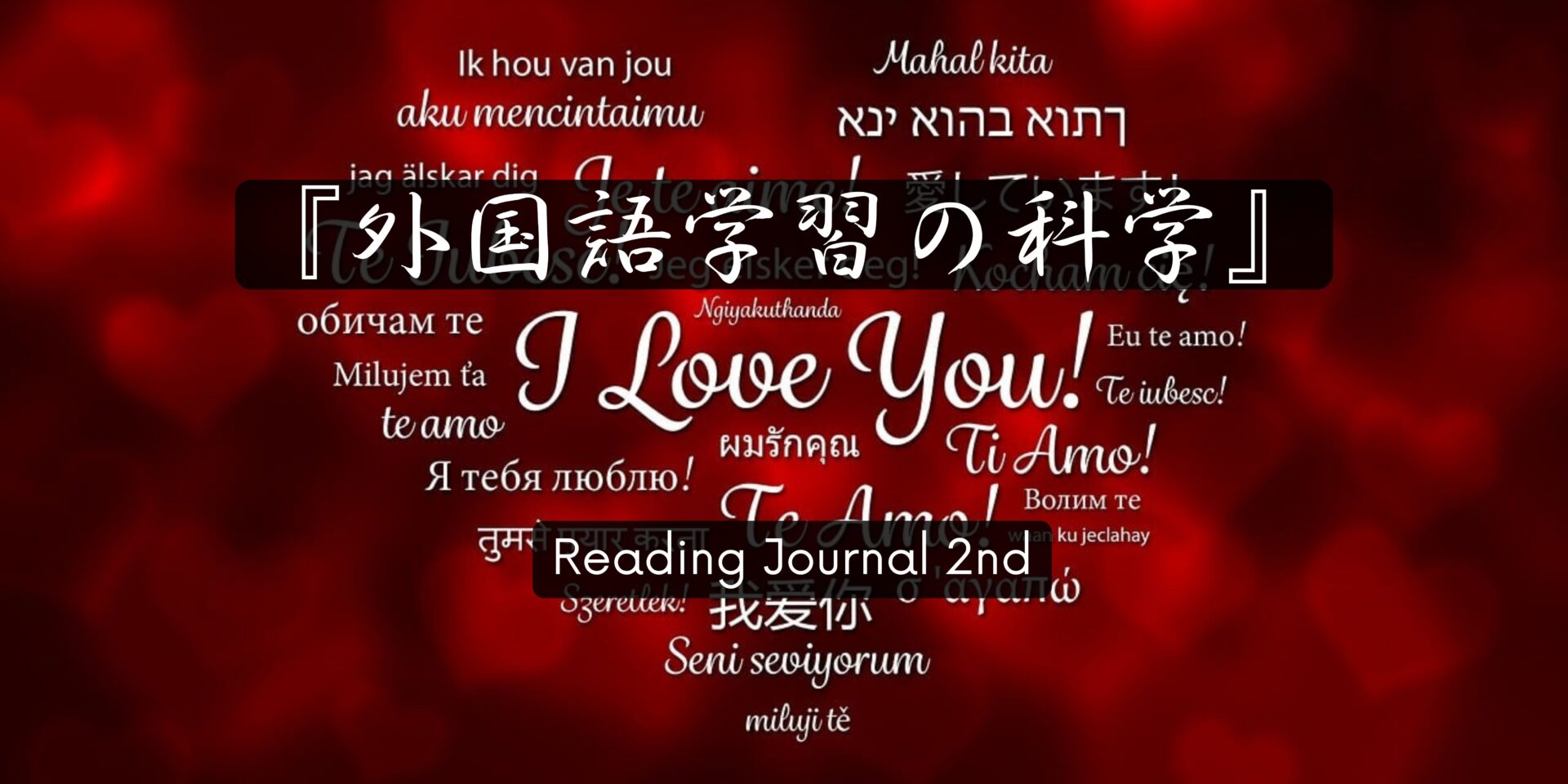


コメント