『アサーション入門』 平木 典子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第五章 心に届く伝え方(前半)
今日から、最終章の「第五章 心に届く伝え方」に入る。これまで、アサーションの定義や歴史から、その考え方と心理学的な裏付けまでを順次学んできた。最終章では、対人関係で苦手と思う状況を、どのようにしたらアサーティブとなれるかについて具体的に考えていく。そしてアサーションが出来ている人はどんなやり取りをしているのか、葛藤するような場面で歩み寄るコツなどについて考える。
第五章は、”前半“と”後半“の二つに分けてまとめるとする。それでは読み始めよう。
自分の思いを確かめる
ここでは、まず「人からの誘いを断る」場面が示される。
このような時、まず大切なことは「自分の思いや気持ちをはっきりさせる」ということである。自分が「どうするか」の前に「どうしたいか」をハッキリさせ、それが明確になるとどうするかのヒントが見えてくる。
いずれの場合でも、自分が決断したことの結果は、他人のせいにせず自分で引き受けようとするならば、困惑や後悔、苛立ちなどは少なくなります。(抜粋)
そして著者は、ここでのまとめとして、
複雑な状況でなんと言えばよいか分からないときの第一のポイントは、状況や場面における自分の思いや気持ちを確かめることです。気持ちはいろいろと出てきますが、そのなかで正直な気持ちを探り、それを言葉にしてみましょう。
ただ、正直な気持ちを捉えることが、自分でも難しい場合があります。そんなときは、いろいろ出てくる気持ちをいくつか捉えて、どれが一番ピッタリくるか、確かめましょう。(抜粋)
と言っている。
事実や状況を共有する
次に場面2として「夫の帰りを待つ妻と自分のことしか考えない身勝手な夫」の例が示される。
ここで、問題なのは、二人とも自分と相手が置かれている状況を共有していないことである。さらに、妻にとって身勝手と感じる夫の行動に対して、妻の困惑の蓄積という問題もある。
この気持ちのズレは、双方がこれまでも必要な事実や状況を伝え合い、共有していないことから生じている。そのため、この行き違いを起こらないように、互いに行動の行き違いを認めて、アサーティブに分かち合うことが必要である。
家族や仕事をする仲間との安定した関係は、大まかなルールや約束事があることで維持される。私たちは、ある程度ルールに頼って互いの動きを期待して、多少のルール違反にも柔軟に対応しながら日常生活を送っている。
その共通基盤が不明確である場合に問題が起こる。ここで、大切なのは事実を分かち合わないで「以心伝心」で伝わることを期待しないことである。
そして、お互いに自分を「主張する」だけでなく、主張する前に客観的な事実を共に確かめ共有してから、希望や要求を述べることが必要である。
提案は具体的に述べる
最後に、「頼まれた仕事をテキパキとこなしていた有能な社員が、親の介護に時間を取られるようになり、時間外の仕事をどのように断ってよいか困っている」状況の話が示される。
まず、このように複雑な事情があって言い方がわからない場合は、言いたいことを整理することが必要である。そして、整理がついたら次にその状況を共有してもらう必要がある。さらに、具体的な提案をすることにより、互いに歩み寄りが出来る。
三つのポイントの復習
最後に著者は、ここで検討した三つのポイントについてまとめている。
- 自分の思いを確かめる (自分は、どうしたいか)
- 事実や状況を共有する(相手と、分かち合う必要がある事実はないか)
- 提案は具体的に述べる(とりあえず、一つ提案をしてみよう)
自分と相手の考えや行動が違っていたり、葛藤が起きそうだったりしたときは、この三つのポイントを覚えておき、アサーションに取り入れていきましょう。(抜粋)
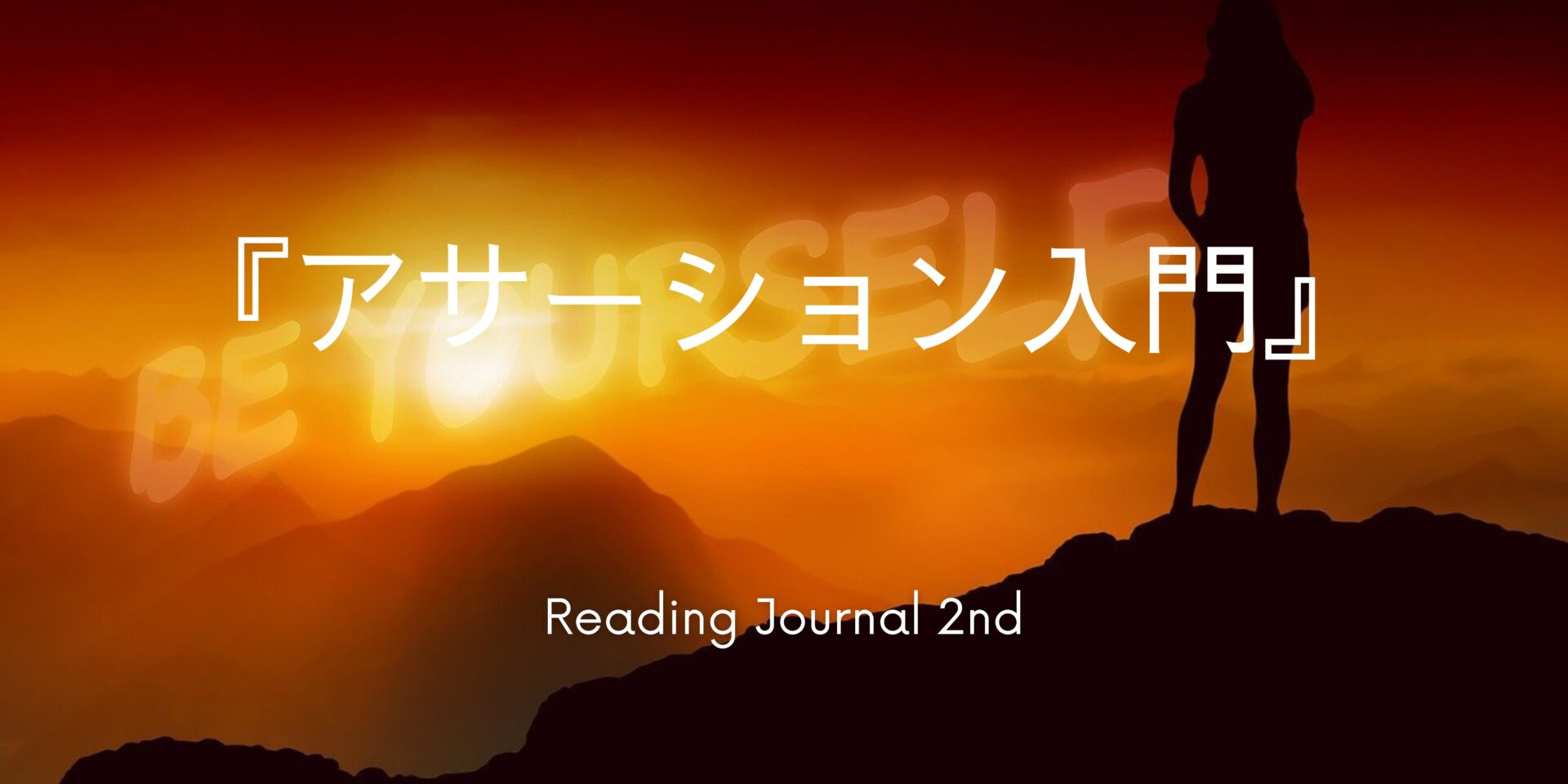
-1-120x68.jpg)

コメント