『アサーション入門』 平木 典子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 考えかたをアサーティブにする(前半)
今日から「第三章 考え方をアサーティブにする」に入る。ここでは、アサーションにブレーキをかける5つの考え方を取り上げる。そして、その5つの考え方一つひとつを取り上げ、それがどのようにアサーションに影響するか、ブレーキになってしまうときはどのように考えを変えていけばよいかが解説される。
第三章は、“前半”と”後半“に分け、まず”前半”において、アサーションにブレーキをかける5つの考え方とそれがどのように作られるかと5つの考え方のうち最初の二つ、つまり「危険や恐怖に出会うと、心配になり何もできなくなってしまう」と「過ちや失敗をしたら、責められるのは当然だ」をまとめる。そして”後半“でつづく三つの考え方、「物事が思い通りにならないとき、苛立つのは当然だ」「誰からも好かれ、愛されなければならない」「人を傷つけてはいけない」をまとめる。
アサーションにブレーキをかける5つの考え方
ここでは、A~Eの5つについて、日ごろの自分の捉え方を考えるテストがある。
その5つの考え方とは、
- A : 「危険や恐怖に出会うと、心配になり何もできなくなる」
- B : 「過ちや失敗をしたら、責められるのは当然だ」
- C : 「物事が思い通りにならないとき、苛立つのは当然だ」
- D : 「誰からも好かれ、愛されなければならない」
- E : 「人を傷つけてはならない」
である。
このA~Eで示したいずれかの考え方を持っていると、アサーションが苦手になる可能性がある。そして、それを自分のこととして受け止めた場合は、「非主張的になりやすく」、世間一般のこととして受け止めた場合は「攻撃的になりやすい」。
つまり、これらの考え方は「アサーションのブレーキになる」と考えられる。
日頃の考え方はどのようにつくられるか
このようなアサーションにブレーキをかける考え方は、子どもの時代に教わったこと、過去の経験やそれに基づく価値観や信念がもとになっている。それは、社会的・文化的な文脈の中で作られ、強化され、信念や価値観の基準となる。しかし、人はそれぞれ背景が違うため、その価値観や考え方も思った以上に違っている。
人の価値観や考え方は、人それぞれのため、それが自分と違っていても、決して間違いと決めつけることはできない。互いのものの見方、考え方の「違い」でしかないことが多い。
また、人は学習する生きものであるため、「子供に時代、過去の経験」を通じて獲得した考え方もそれが通用しなくなってしまった考えられる場合は、その考え方ものの見方を学習し、変えることが出来る。
考えかたを変えることで、気持ちが緩やかになり、アサーティブな自己表現がしやすくなり、自身や余裕も出てきます。(抜粋)
五つの考え方の影響を変えるためのヒント(C~Eは次回へ)
ここよりA~Eまでの考え方を変えるためのヒントが示される。
A 「危険や恐怖に出会うと、心配になり何もできなくなる」
誰でも危険や恐怖に出会うと、心配になり行動にブレーキがかかる。この行動にブレーキをかける心配に具体的な回避や予防などを立てるのではなく、心配にとらわれ自己表現や行動の範囲が狭くなることは大変もったいないことである。
危険や心配に出会ったとき、自己表現の範囲を狭めたり反対に苛立ったりせず、アサーティブにするには、
- 自分の心配は、具体的にどんなことから来ているか
- 心配なことが起きたら、どうすれば対応できるか
を考えることである。そして、それに対する解決策を探して対応することが必要である。また、一人で対応できそうもないときは、誰かに相談することが大切である。ここで誤解されやすいことは、人に相談する必要性を認め、決心することは、「逃げ」や「非主張的自己表現」ではなく、アサーションである。さらに、検討の結果、危険を避けることもアサーションである。
ここで大切なことは、心配を目の前にして一人で「どうしようもない」と考え込まずに、心配をきっかけに「その危険を避けるために、何か方法はあるのではないか」と実現・実行の可能性を探ることである。そうするとたいていのことは、方策が見つかり、また周りの人からの意見やアドバイスも受けられる。
さらに、どうしても恐怖や心配の種に対応できない場合は、諦めるしかない。前向きに検討した結果、諦めるのともアサーションとなる。
B 「過ちや失敗をしたら、責められるのは当然」
重大な危険は避ける必要があるが、「絶対失敗してはいけない」とか「失敗したら攻められて当然」といった厳守・厳罰主義となると、「失敗への恐怖心」を植え付け、自他の言動を縛ってしまう。そのため引っ込み思案となり依存的・非主張的となる可能性がある。逆に他者に当てはめると、他者の過ちや失敗を許さずに、責めたり、罰を与えたり、償いを求めたりしてしまう。
過ちや失敗は、しないに越したことはないが、人が過ちや失敗をしたときには、それを責めても成長にはつながらない。また、責められることで委縮し非主張的になったり、逆に脅威を感じて自己防衛的になったりしてしまう。いずれの場合も、過ちや失敗を認め、是正し、新たな学びをするチャンスを失うことになってしまう。
過ちや失敗はありえるもものであり、そのときは責めるのではなくきちんと理解できるように指摘し、繰り返さないようにするにはどうしたらよいかを確認することが大切です。それは感情的にならずきちんと「叱る」ことであり、感情的になったり攻撃的になったりして「怒る」ことではないのです。
「過ちや失敗をしたら、叱られることはありえる」というのがアサーティブな考えかたでしょう。(抜粋)
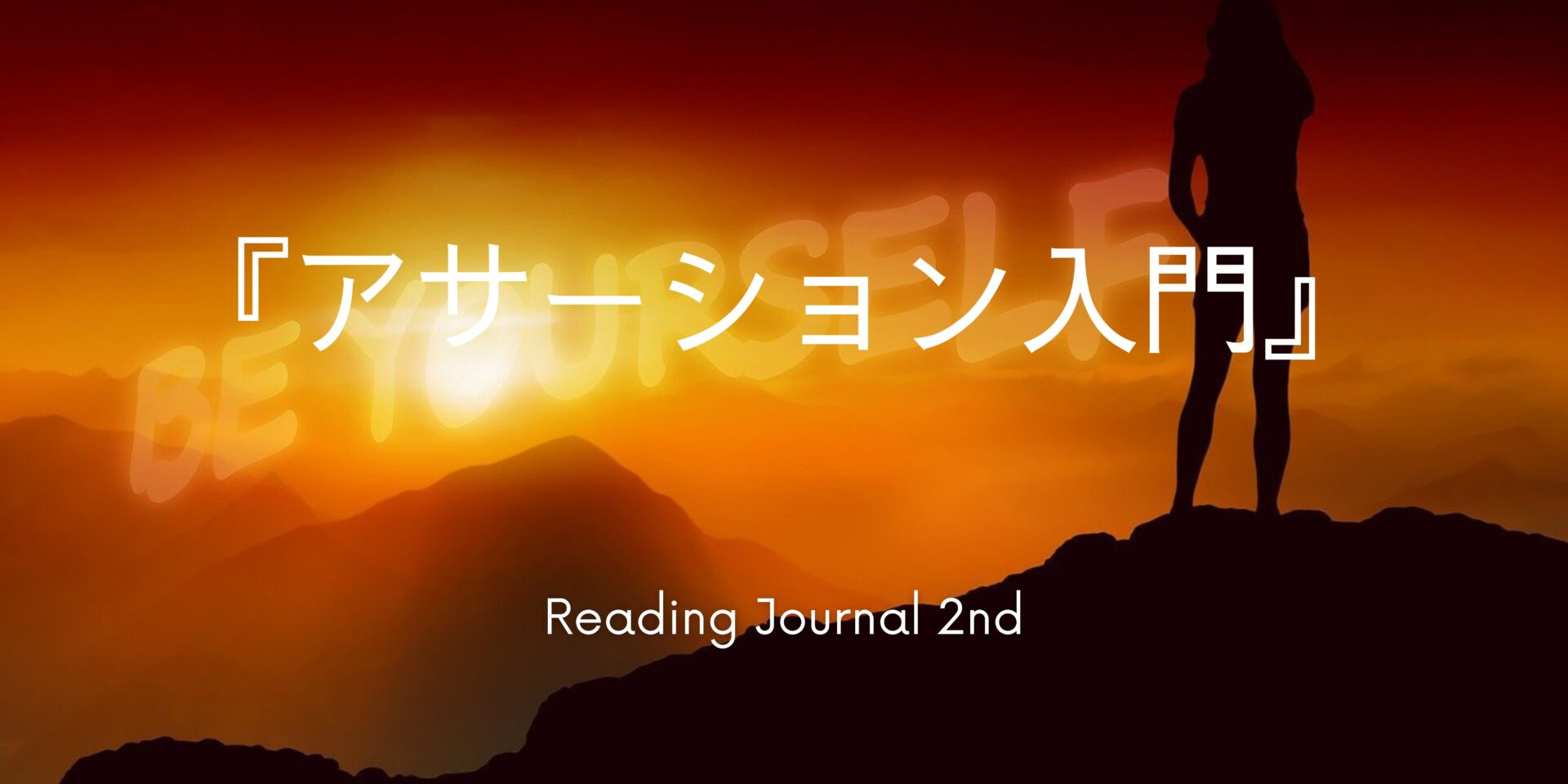


コメント