『アサーション入門』 平木 典子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一章 アサーションとは自分も相手も大切にする自己表現(その2)
今日のところは、「第一章 アサーションとは自分も相手も大切にする自己表現」の“その2”である。前回の“その1”では、アサーションについて、その定義や意味、歴史の概説があった。そして今日のところ“その2”では、三つの自己表現のうち最初の二つ、「非自己主張的自己表現」と「攻撃的自己表現」を取り扱う。そして次回“その3”は「アサーティブな自己表現」と「三つの自己表現のまとめ」となる。それでは、読み始めよう。
「非主張的自己表現」
「非主張的自己表現」とは
最初の自己表現は、「非自己主張的自己表現」である。これは、自分の意見や気持ちを言わない、あるいは、言いそこなう、言っても相手に伝わりにくい自己表現である。あいまいな表現や、人に無視されやすい自信なさげな話し方、消極的態度も含まれる
このような自己表現は、相手から理解されにくく、相手を優先するため、相手の言いなりになってしまうこともある。相手を心から配慮し、尊重して同意したり、譲ったりしたのとは違うため、どこかに「わかってもらえなかった」「自分が譲ったのに・・・」「惨めだな」という、気持ちが残る。
このタイプの表現をする人は、反論もしないため、葛藤やもめごとを回避してくれる「いい人」と思われていますが、一方で「都合の良い人」ともみなされがちです。(抜粋)
「非主張的自己表現」を続けると
このような「非主張的自己表現」を続けていると、だんだんと自分の言いたいことがわからなくなり、自分で決められない、あるいは言い方がわからないという状態に陥る。そしてその結果として、自信がなく、引っ込み思案になってしまう人もいる。
この非主張的自己表現の人は、自分の人権を自ら侵すようなことを招くことがある。また、大事な決定を相手にまかせ、自分の考えを明確にせず、自分にも相手にも無責任になってしまうこともある。
自分の欲求を押さえているため、相手に対し「思いやりのない人だ」「鈍感だ」と恨みを募らせ、突然その怒りや欲求不満を爆発させることもある。反対に切れることもなく、ただ忍耐強く我慢すると、自分のエネルギーを使い果たし心身共に疲れ切り、うつ状態や心身症になることもある。
いずれの場合も、自分を大切にしなかった(自分の人権を無視した)結果、相手も大切にしない(他者の人権も侵してしまう)ことになりかねません。(抜粋)
ここで著者は、本書での「人権」の意味を、法律的な意味でなく「誰もが一人の人間として大切にされること」を意味すると注意している。
「非主張的自己表現」は、どのような心理とつながっているか
この「非主張的自己表現」は、次の二つの心理とつながっている。
- 自分の心理:一つ目は自分の心理で、自分の思いや考えを表現することで、相手を不愉快にし嫌われことや、相手と違った意見を言うことで、葛藤やもめごとが起こることを避ける心理である。これには、穏やかな人間関係を望む心理と、相手に合わせることで安全を確保しようとする心理が働いている。そこには、相手に合わせているつもりでも、実は相手に甘え、依存している心理も働いている。一つ目は自分の心理で、自分の思いや考えを表現することで、相手を不愉快にし嫌われことや、相手と違った意見を言うことで、葛藤やもめごとが起こることを避ける心理である。これには、穏やかな人間関係を望む心理と、相手に合わせることで安全を確保しようとする心理が働いている。そこには、相手に合わせているつもりでも、実は相手に甘え、依存している心理も働いている。
- 社会・文化的背景による心理:二つ目は、世の中の習慣や常識に従うことによって自らの尊厳や権利を無意識に否定する心理である。社会的に権威や経験のある人に逆らわないという常識や習慣は、未熟な人の自己表現を制約しがちである。ここには、相手や社会に順応し、認められようとする心理がある。
「非主張的自己表現」による損失と相手への影響
このような「非主張的自己表現」をしていると、自分の気持ちや能力を確かめるチャンスも、自発性や個性を発揮するチャンスも失ってしまう。
また、相手に対して一見控えめで遠慮しているように見えても、実は「わかってもらえていない」などの不満があり、ときに恨みを守ったりする。これは相手からするとたまったものではない。そして常に遠慮されたり、自分の意見を引っ込められたりしても相手にとっては居心地の悪い感じがする。
「攻撃的自己表現」
「攻撃的自己表現」とは
「攻撃的自己表現」は、「非主張的自己表現」と対照的に、自分の言い分や気持ちを通そうとするものである。「言い放しにする」「押しつける」「言い負かす」「命令する」「操作する」「大声で怒鳴る」などは、攻撃的自己表現である。
さらに、表情豊かに自分の意見を述べたり、丁寧で優しい言葉でおだててきたり、していても、自分の思い通りに操作するとしたらそれは攻撃的自己表現と言える。
「攻撃的自己表現」を続けると
攻撃的自己表現は、自分が正しいかのように言い張り、相手を黙らせようとし、同意させようとする。自分の考えと異なる意見は無視し、排除しようとする。
そのような表現をする人は、一見堂々としていても、どこか防御的で、必要以上に威張ったり強がったりする。そして、結果として一時的に自分の言い分が通って満足するものの、利害関係のない人には敬遠され孤立することになる。
この「攻撃的自己表現」は、権力や権威がある人、知識や経験が豊かな人、役割や年齢が上の人がとりやすい。また、常に自分が優先されるべきだと考える人、自分の思い通りに人を動かしたい気持ちが強い人がとりやすい。
「攻撃的自己表現」は、どのような心理とつながっているか
この「攻撃的自己表現」も「非主張的自己表現」と同じく二つの心理につながっている。
- 自分の心理:まずは自分の心理である。これは自分の考えは正しい、優れているという思い込みや、自分の言い分を絶対通したいという欲求、自分の考えや気持ちが通らない事への不満という心理である。ここで注意したいことは、この「攻撃的自己表現」も「非主張的自己表現」と同じく、相手に依存し、甘える心理につながっているということである。
- 社会・文化的背景による心理:二つ目は、社会・文化的背景による心理である。社会の常識や習慣から無意識に「攻撃的」となり、社会や組織でそのことは許容されると思い込み無自覚のまま、さらに自分の権威、権力、地位、役割、年齢差、性差などを利用して、自分の意見を押し通すために相手を操作してしまう。
「攻撃的自己表現」の影響
そしてこの攻撃的自己表現が習慣になると、他者の従属的態度や支えなしには自己を維持できなくなっていく。
また、このような攻撃的対応をされると、相手は傷つき、恐れて、相手を敬遠したり、怒りを感じて復讐心を覚えたりする。そして、対等で親密な人間関係を築けなくなる。
「非主張的自己表現」と「攻撃的自己表現」の関係
「非主張的自己表現」と「攻撃的自己表現」は、凸凹のような関係と言える。
非主張的自己表現では、弱い立場の人が強い立場の人の攻撃的態度や表現に屈することになり、ストレスを蓄積させ、心理的不適を抱えることになる。
一方、攻撃的自己表現では強い立場の人が、弱い立場の人の弱みや善意を利用することになる。利害関係のあるところでは、弱者をいじめをしながら自分を支えることができても、そのうち周囲から敬遠されてしまう。
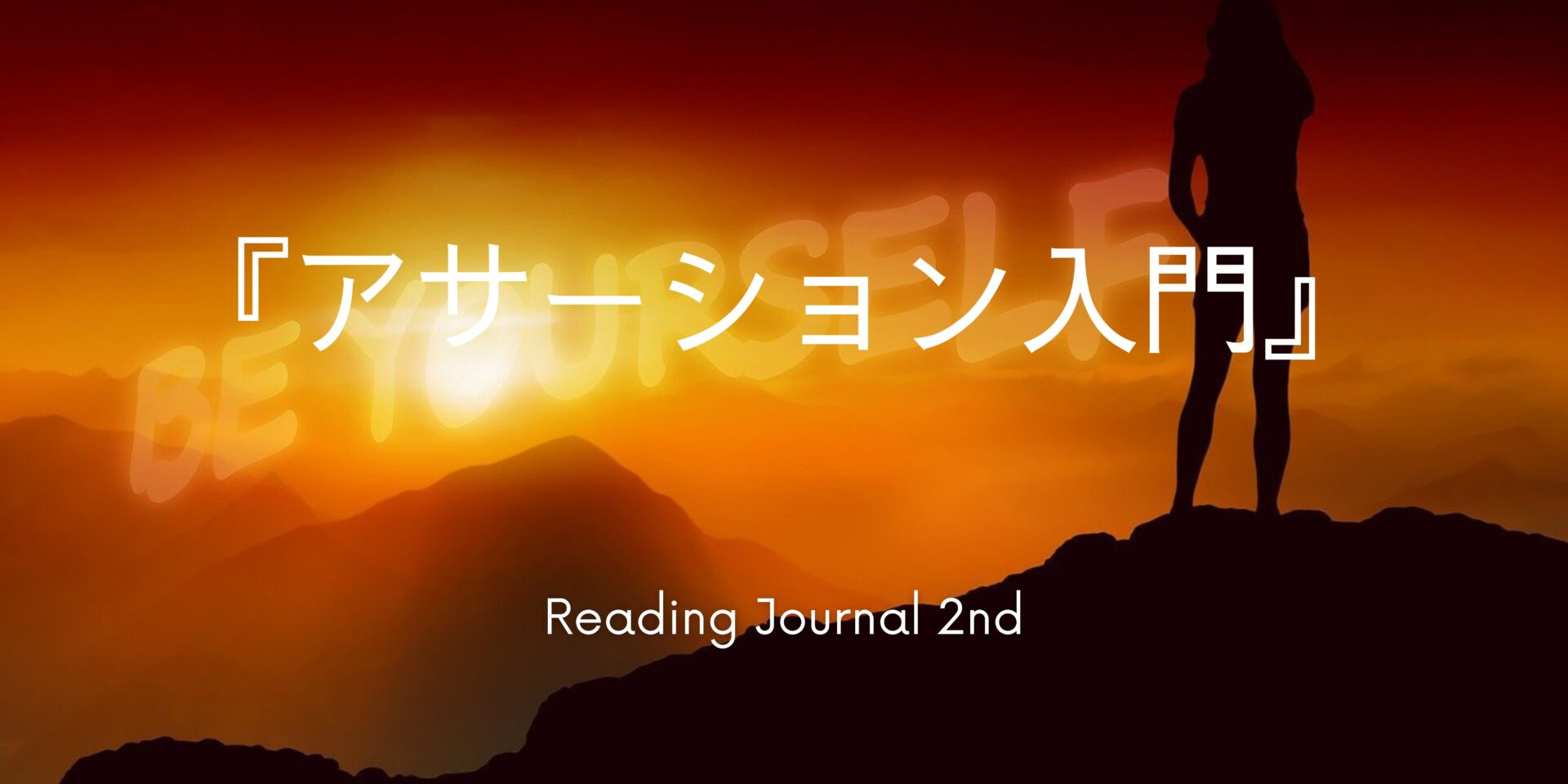


コメント