『アサーション入門』 平木 典子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一章 アサーションとは自分も相手も大切にする自己表現(その1)
前回の「はじめに」につづき、今日から本章に入る。まずは、「第一章 アサーションとは自分も相手も大切にする自己表現」である。ここでは、アサーションの導入として、その意味や著者のアサーションとの出会い、さらにその歴史を概説する。そして、アサーションを理解知るために必要な三つの自己表現、「非主張的自己表現」「攻撃的自己表現」「アサーティブな自己表現」について説明される。
第一章は、3つに分けてまとめることにする。まず”その1”では、アサーションの概説についてまとめ、“その2”で「非自己主張的自己表現」と「攻撃的自己表現」、そして“その3”で「アサーティブな自己表現」と「三つの自己表現についてのまとめ」をまとめることにする。
アサーションの意味
「アサーション」は、「自他尊重の自己表現」、つまり「自分も相手(他者)も大切にする自己表現」という意味である。
アサーションというと、実用的な表現法というイメージがあるが、それは少し違うと著者は注意をしている。アサーションによる自己表現とは、単なる自分の「自己主張」や「言い方」ではなく、相手とどのようにコミュニケーションするかについて掘り下げる考えが含まれる。
つまり、アサーションは、自分も相手も尊重するような人間関係を目指している。
本書では、このような日常のコミュニケーションをふり返り、アサーションの考え方と方法を通して、よりよい相互交流ができるようになることを目指します。(抜粋)
著者とアサーションの出会い
次に、自己表現に関するテストの後に、著者とアサーションとの出会いについてふれられている。
著者がアサーションと出会ったのは、一九七五年の夏、アメリカで行われたロジャースの研修会であった。
ここに出てきた「カウンセリングの父」と呼ばれる、カール・ロジャースについては、『プロカウンセラーの聞く技術』に詳しく載っている。なんといっても著者の東山は、カール・ロジャースの弟子なんだそうです。(つくジー)
この研修会がきっかけで著者は、「自分も他者も大切にする思想」やその実践が、日本人にこそ必要なものではないかと考えた。そして、一九八〇年に著者により「アサーション」の概念が初めて日本に紹介された。
また、英語のassertionは、日本語では「主張」「断言」「断定」「言い張ること」と訳され、それでは、カウンセリングの専門家の扱う「アサーション」とは、意味がかけ離れてしまうため、カタカナ表記の「アサーション」と表記してきたと、説明している。
アサーションの発展プロセス
アサーションは、もともと、人間関係が苦手な人、引っ込み思案でコミュニケーションが下手な人を対象としたカウンセリング方法・訓練法として一九五〇年代に北米で生まれた。しかし、そのような人だけを対象としても効果が上がらないことがわかってきた。
それは、このような人々の「権利を踏みにじったり、押しつぶしたりする人々」の存在があるからである。そのため、「力や権威を行使する側にもアサーションという考え方を意識してもらう必要がある」と考えられるようになった。
その後アサーションの考え方は、人種差別や男女差別を受けた人々、特別な配慮やケアが必要な人々の人権を守るために、その人権を軽視・無視する人たちへの警鐘として、教育、福祉、産業などの分野に広がった。
三つの自己表現タイプ
アサーションの考え方を紹介したウォルビィは、「人間関係における自己表現」には、
- 「非主張的自己表現」:自分より他者を優先し、自分を後回しにする自己表現
- 「攻撃的自己表現」:自分のことだけをまず考え行動し、時には他者をふみにじることにもなる自己表現
- 「アサーション」:自分のことをまず考えるが、他者のことにも配慮する自己表現
の3つがあるとした。
そして人は状況や相手に応じてこの三つの自己表現を無意識に使い分けている。しかし、どの自己表現の割合が多いかは、人による。
関連図書:東山紘久(著)『プロカウンセラーの聞く技術』、創元社、2000年
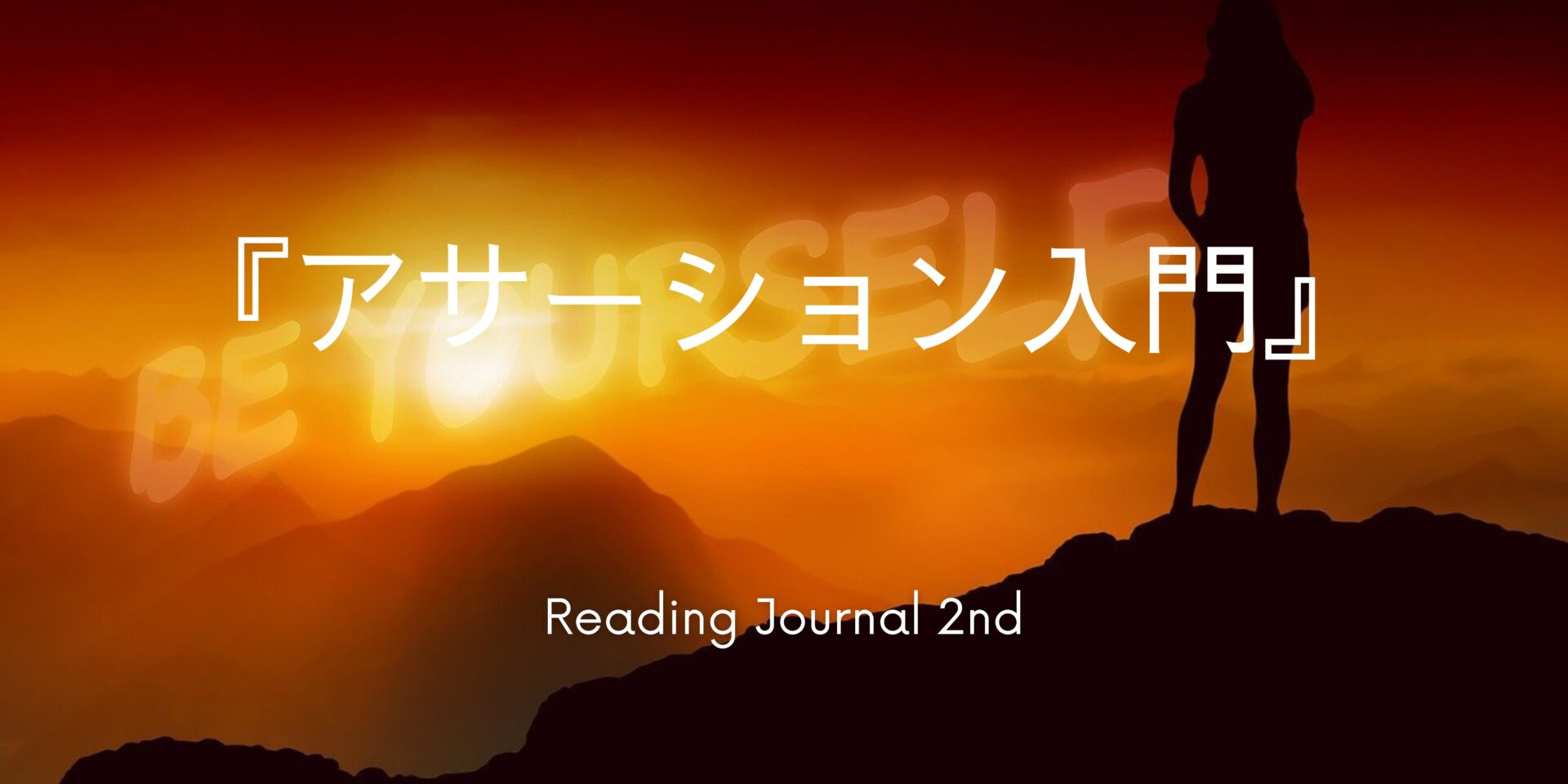

-1-120x68.jpg)
コメント