『アサーション入門』 平木 典子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第五章 心に届く伝え方(後半)
今日のところは、最終章の「第五章 心に届く伝え方」の”後半“である。”前半“では、アサーションのまとめとして、三つのポイント、つまり①自分の思いを確かめる、② 事実や状況を共有する、③ 提案は具体的に述べる、を説明した。今日のところ”後半では、具体的な例をあげて補強し、さらにアサーションになれるヒントが述べられる。そして、最後によくある質問とアドバイスとして、「アサーションは相手に同意してもらうテクニックではない(他者を変える)」こと、そして「私メッセージ」を使うことがアサーションであることが説明されている。それでは、ラストスパート。
アサーションを実践している人
著者は、ここでアサーションを実践している人の例として、著者が出会った静かに話すセールスマンの話とドラえもんの静香ちゃんを取り上げている。
特に静香ちゃんの話は、分かりやすく。小学校でアサーションを教える時に「ドラえもん」を例にして活用している先生の話である。
先生が、まず、具体的な問題(ここでは、貸した消しゴムを返してもらえないとき)を例にして、子どもたちに「ジャイアンだったら?」「のび太だったら?」「静香ちゃんだったら」どう言うかと質問する。すると自然に子供たちは、ジャイアンの場合は「攻撃的自己表現」、のび太の場合は「非主張的自己表現」、そして静香ちゃんの場合は「アサーティブな自己表現」の回答が出てくるという。そして、だれの言い方が気持ち様ですかと先生が言うと、「静香ちゃんの言い方がいい」と子供たちが答える、のだそうである。
ここで著者は、どちらの自己表現も、アサーションの3つのポイントに示したプロセスを取っていると説明している。
さらに、具体的な表現を見つけるために4つのヒントが示される。
- あなたの今の気持ちは? 怒りや不満の感情が先立っていませんか? ほかに、あなたが感じていることはありませんか?
- あなたが対応しようとしている相手と共通に分かち合える状況はないでしょうか?客観的に分かりやすく状況を取りだしてみましょう。
- 提案は具体的ですか?
- その提案に対して合意されたとき合意されなかったときの、あなたの対応の選択肢も考えておきましょう。 相手がイエスのときも、ノーのときも、葛藤を恐れないで対応してみましょう
アサーションへの誤解とアドバイス
アサーションの誤解としてよくあるのが、
- 「相手がアサーションを知らない場合はどうしたらよいでしょうか」
- 「どのようにすれば、相手が同意してくれますか」
というものがある。
これに共通しているのが、アサーションを「他者を変える方法」として使おうとしているところである。
大切なところは、人はそれぞれ自分の意見や気持ちを持っているので、アサーションを知っていても同意するとは限らないことである。
アサーションは相手を変えるためのコミュニケーション法ではなく、その試みの反応は相手に任されている。相手がアサーティブでなく非主張的だったり攻撃的だったりすることもある。
そのためアサーションでは自分が表現した後のフォローが必要となる。相手の反応に対してもアサーティブに対応することである。相手との食い違いや葛藤は、互いに思い違いを確かめ合うサインと受け取り、より深く相手を理解し、解決をはかる出発点となる。
また、誰もがアサーションを知っているわけではないので、まず知っている自分が変わることに意味がある。
相手が非主張的であろうと攻撃的であろうと、自分ができることは、まず自分がアサーティブになってみることです。(抜粋)
そして、そのような態度を取った時に何が起こるかをフォローし続けることが大切である。アサーションでは、自分のコミュニケーションに自ら責任を取ることに尽きる。
「私メッセージ」とは
著者は、アサーションを「私メッセージ」という言葉で表現している。
「私メッセージ」とは、自分の気持ちを明確に伝えることであり、何かを主張するときに「私」を主語にして言語化することである。
自分が感じたり、思ったり、お願いしたりしたいことを、あたかも相手がそうしているかのように「あなたが~だ」と決めつけると、それは「あなたメッセージ」となり、気まずくなったり、後味が悪い思いをする。そのような時は、「私メッセージ」を使うと決めつけに聞こえないメッセージとなる。
また、相手の言動の意図や理由を聞きたいとき、あるいは物事のいきさつを聴きたいときに、「なぜ~?」「どうして~?」と聞いてしまうことが多い。しかし、この「なぜ・どうして」には無用に責める意図が含まれやすい。そのため、「なぜ・どうして」を使わずに「(意図・理由・いきさつ)について知りたい」とか「聞かせてほしい」などと伝えるようにする方がよい。
自分の言い分を通したい、相手を思いどおりに動かしたい、自分の考えは正しい、という思いがあると、「そんなことは当たり前でしょう」とか「当然です」「~すれば~なるはずだ」のような言い方をしてしまう。これは正体不明の他者の力を借りて説得しようとするやり方である。このような時こそ「~してほしい」という「私メッセージ」の出番である。
[完了]全10回
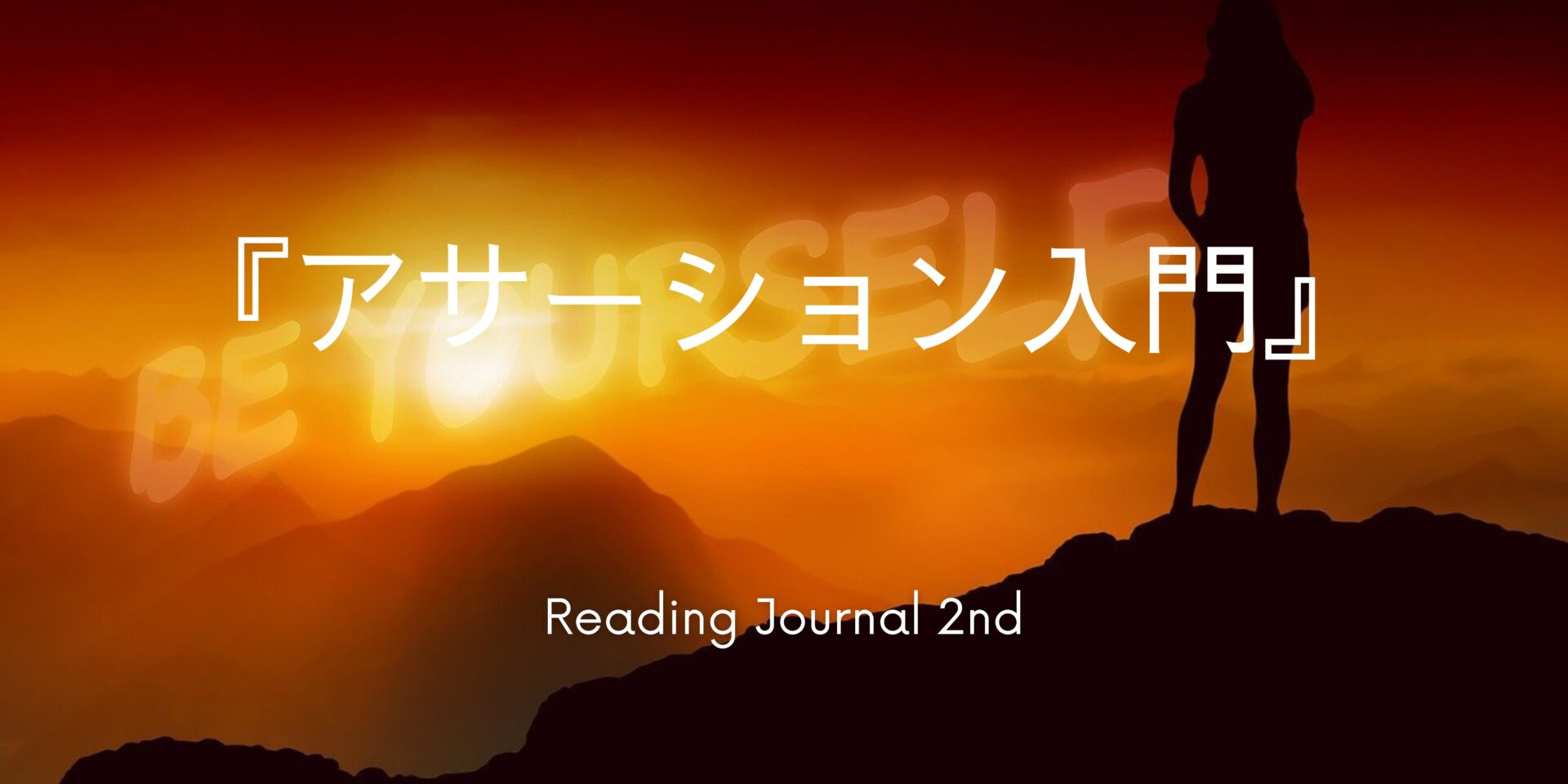


コメント