『あなたを変える行動経済学』 大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第6章 ナッジとはなにか?(前半)
今日のところは「第6章 ナッジとは何か?」である。本章は、ノーベル賞経済学賞を受賞した経済学者リチャード・セイラーが提唱した行動経済学を応用して行動変容を起こさせる方法・ナッジについてである。第6章は、”前半“と”後半”に分けてまとめることにする。”前半“では、ナッジの概念とその制作プロセスについて、”後半”では、ボトルネックの見つけ方と、具体例についてである。それでは読み始めよう。
ナッジとリバイタリアン・パターリズム
「ナッジ」 (nudge:肘で軽くたたく)は、ノーベル経済学賞をとったリチャード・セイラーが定義した概念である。(彼は、『Nudge』 (日本語版『実践行動経済学』という本を書いている)
ナッジは、行動経済学を利用して行動変容を起こす方法で、セイラ―は社会にナッジを組み込むことで、人々はもう少し暮らしやすくなると言っている。
このナッジはリバタリアン・パターナリズムの思想にもとづいている。ここで
- リバタリアン:個人的な自由と経済的な自由の双方を重視する
- パターナリズム:介入主義、温情主義、父権主義という意味で、相手のためになることを、押しつけてやる方法
である。
リバタリアンとパターナリズム矛盾する考えかたなのですが、セイラ―とサンスティーンはこの二つの言葉を組み合わせて、個人の行動や選択の自由を阻害せず、かつ「より良い結果」に誘導するという思想を作り上げたのです。(抜粋)
つまり、ナッジは選択を禁止することも、経済的なインセンティブを大きく変えることもせずに、人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャーのあらゆる要素である。また、ナッジでは大きな金額をかけないということも重要である。
ナッジとスラッジ
しかしナッジでは、「あなたのためだから」といって、本人のためにならないような選択肢を設計することも可能である。このようなものは、ナッジではなく「スラッジ」 (sludge : ヘドロ)という。
ナッジでは、本人にとって利益になるようなもの、社会に望ましい行動を促進することが大事な要素である。
ナッジ設計のプロセスフロー 「BASIC」
このようなナッジを設計のためのプロセスフローとして、国際機関OECD(経済協力開発機構)提案した「BASIC」がある。
著者はこれを「宿題ができない」という例に当てはめて解説している。
- 「B (Behavior)」、人々の行動を見ること:宿題ができない人の行動を観察する
- 「A (Analysis)」、行動経済学的に分析する:宿題ができないのは、現在バイアスで先延ばしであると分析する
- 「S (Strategy)」、ナッジの戦略を練る:宿題を先延ばしする人のナッジとして、「〆切を短くする」「本人に約束させる」などの戦略を考える
- 「I (Intervention)」、実際に介入して検証する:どのナッジが一番効果があるかを、グループ分けして検証する
- 「C (Change)」、最も効果があるナッジを実施する:一番効果があったナッジを全体に適用する。
ナッジチェックリスト「EAST」
次に著者は、ナッジ戦略を考える時のチェックリスト「EAST」について解説している。これは、イギリスのナッジユニット(行動洞察チーム)が提案したものである。
- 「E (Easy)」、簡単かどうか、情報量が多すぎないか、手間がかからないか
- 「A (Attractive)」、魅力的なものか
- 「S (Social)」、社会規範や互恵性を利用しているか
- 「T (Timely)」、ナッジ介入が最も良いタイミングで行われているか
また、リチャード・セイラーと共に『NUDGE 実践 行動経済学』を書いたサスティーン教授は、『入門・行動経済学と公共政策』の中で、このEASTに「F:FAN(面白い)」を付け加えて、FEASTとすることを提案している。
関連図書:
リチャード・セイラー、キャス・サンスティーン(著)『NUDGE 実践 行動経済学完全版』、日経BP、2022年
キャス・サスティーン(著)『入門・行動経済学と公共政策』、勁草書房、2021年
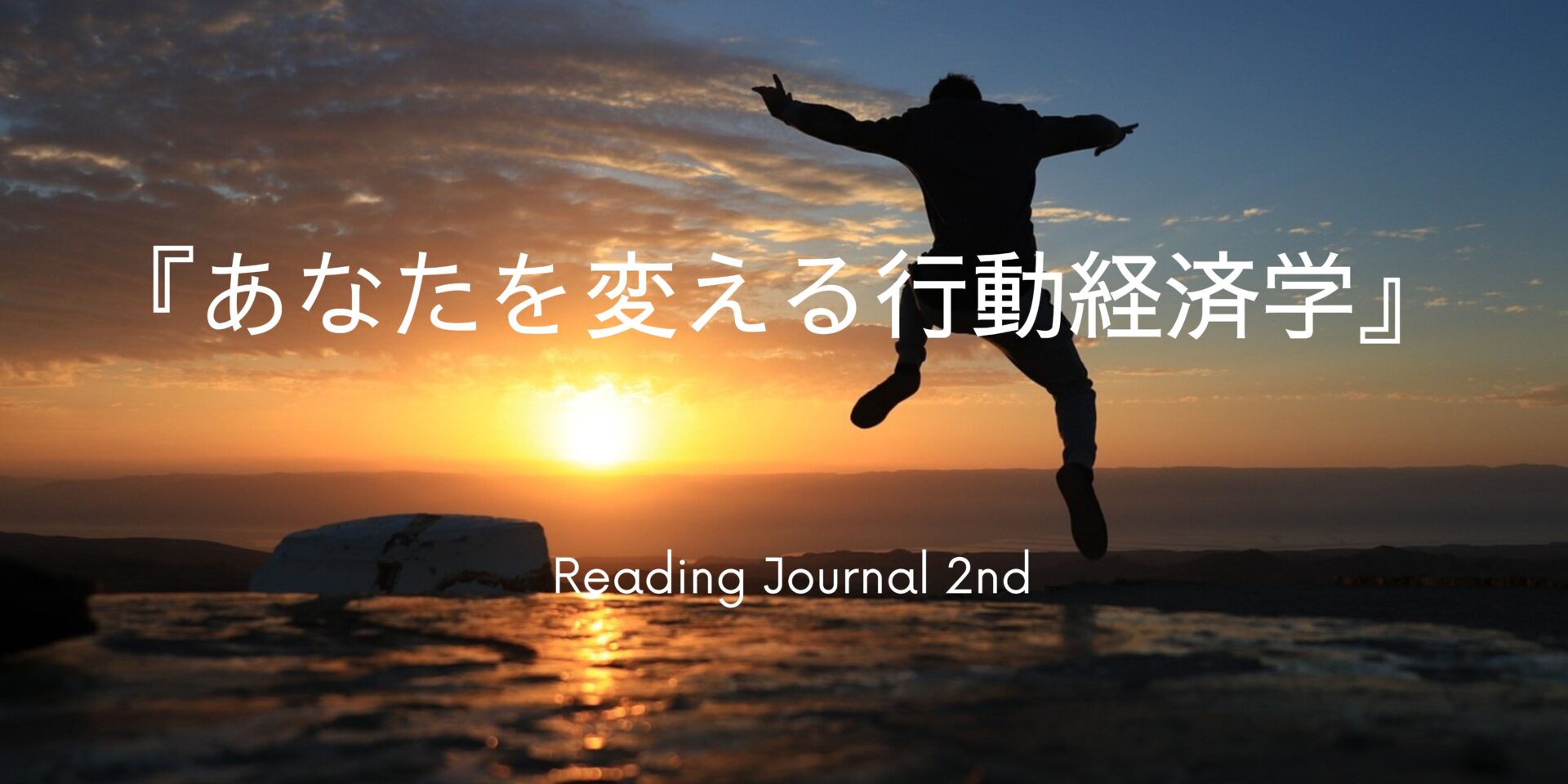


コメント