『アメリカ革命』 上村 剛 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4章 合衆国の始まり ― 一七八七~一七八九年 (後半)
今日のところは、「第4章 合衆国の始まり」の”後半“である。”前半“では、各邦の代表が署名した合衆国憲法が、各々の邦で批准するまでの議論を追っていた。今日のところ”後半“では、初代大統領のワシントンが開いた第一会議の様子、権利章典の採択の様子などが解説されている。それでは、読み始めよう。
アメリカ合衆国の出発と憲法体制の確立
憲法が無事に批准され、アメリカ合衆国が始まった。しかし、アメリカ建国者たちは、ここからその運用や実践の問題に直面する。
著者は、どのように憲法体制を確立したか、の説明には2つのアプローチがあるとしている。一つは、ワシントンのパーソナリティから説明する方法、二つ目は、憲法の条文そのものから説明する方法である。
初代大統領となったワシントンは、自分自身が大統領として行うことが、その後の先例になることを意識して政治的に振る舞っている。建国当初のワシントンの存在感は圧倒的であった。そのため、新たな憲法体制はワシントンの力によって確立したという、説明も成り立つ。しかし、著者はそのような説明では、あまりにヒロイックな見解になってしまう、としている。
連邦憲法の主眼はマディソンが述べているように、いかに野心を持った邪悪な政治家が登場しても、それを抑えられるような統治機構を確立する点にあった。(抜粋)
その点から考えると、重要なのは憲法条文のそのものの規定ということになり、憲法の構造の限界のなかで、いかに政治家が行動したかというアプローチの方に力点を置きたいと、著者は言っている。
初代大統領ワシントン
一七八九年三月に第一議会が始まった。ここより八年間のワシントン政権は、大統領の模範としてのちに継承される。
大統領については、その称号が問題になった。副大統領(上院議長)のジョン・アダムズは、大統領に物々しい称号をつけようとして提案したが、反対にあった。もし大統領に対して過剰な敬意が表されば、議会の従属、大統領の君主化を意味するからである。最終的には、ワシントン自身がそのような君主化を拒んだ。
ワシントンがすぐに直面した問題は、「先住民との外交問題」と「アメリカ人の西方進出の問題」であった。
「先住民との外交問題」に関して、条約締結権は「上院の助言と承認」のもと行うという憲法の条文に則りワシントンは上院に協議すべく書簡を送った。しかし、これに上院が対応できず棚上げされてしまう。そのためワシントンは、上院に赴き演説を行うが、これもうまくいかなかった。結局、この先住民との外交交渉は、独立戦争時からのワシントンの右腕であったヘンリー・ノックスやディヴィッド・ハンフリーズがその役割を担う。
ワシントンは、自ら政治的権力を施行することや、政治的見解を表明することに慎重だった。それは、党派性を持つべきでないと考えていたことと大統領と議会との軋轢を生じないように振る舞っていたためである。そのため重要なのは補佐役である。この補佐役は最初こそマディソンが担っていたが、そのマディソンとも徐々に距離が生じ、バランスが変化する(第五章)。
第一議会の開催と関税の問題
連邦議会の制定理由の一つは、課税権の強化である。そのため第一議会では、課税権が重要なテーマとなる。
ここで、海外製品の流入を危惧していた北部ニューイングランドは、高関税を主張し、外国からの輸入品に頼っていた南部は輸入品への関税の撤廃を主張した。この問題は、さらに奴隷制の問題とも関り議論は紛糾した。結局歳入法の成立には数ヵ月かかり、最終的には、北部が南部に譲歩して低関税をかけることで決着した。
執行府の創設
第一議会では、ワシントン政権の運営方法についても議論がなされた。ここで、執行府(大統領とそのもとにある公務員)をどのように作るかも議論がされた。外務省や財務省などの設置が議論されたが、ここで問題になったのが、公務員の罷免権である。
憲法には、公務員の任命権については、大統領が公務員を指名し、上院の助言と承認を受けて任命すると書かれていたが、罷免権については、何も書かれていなかった。そのため、大統領のみに罷免権があるという意見と、大統領と上院が共同で罷免するという主張とが、対立した。
ここで問題は、両者の主張が憲法解釈によって支えられるかである。
大統領と上院の共同説の根拠は、任命権と罷免権とをセットして理解し、任命権の規定がそのまま罷免権に妥当するというものである。
これに対して、マディソンは大統領単独説を唱えた。大統領単独説の理由は、「権力分立の原則」と「責任の問題」であった。合衆国憲法には、「執行権はアメリカ合衆国大統領に属する」と書かれていて、罷免権は執行権の行使なので、大統領のみが罷免権を持つべきである、というのが「権力分立の原則」に照らし合わせた主張である。そして、上院と共同で罷免権を持つ場合は、罷免に対しての責任の所在が不明瞭になるというのが、「責任の問題」である。
この罷免権の問題は、テクニカルな問題を超えて、二つの重要な論点を含んでいると著者は指摘している。一つは、大統領のみが罷免権を持つ場合、大統領の専制に繋がらないかという疑問である。二つ目は、出来上がった憲法を、誰がどのように解釈するかという問題である。合衆国憲法は、多くの妥協の産物であったため、誰もが異論のない解釈は難しかった。
いずれにせよ、このようなかたちで連邦議会は手探りで政治権力の行使、ならびに議会とそれ以外の政治勢力(特に大統領)との関係を定め始めた。(抜粋)
この罷免権の問題は、最終的には大統領単独で落ち着くことになる。
権利章典の作成
第一議会では、マディソンの提案である権利章典に関する憲法修正も行われた。これは、修正第一条~一〇条では、信教の自由、表現の自由、武器の保有権などを内容とし、今でも存続している。
マディソンの演説では、「マジョリティによるマイノリティへの危険を防ぐ」ということが強調されたが、当時は、人々の権利よりも前に解決すべき問題が多いとして、あまり注目されなかった。また、連邦最高裁判所の役割が人々の権利を守るものと強調されたが、それも連邦憲法制定会議での裁判所軽視の風潮からすれば、意外なことであった。
課税から逃亡する人々
この第一会議の結果、新しい連邦国家の形成は人々に歓迎された。しかし、憲法に基づく課税権は、納税を拒否するために東部から西部に逃れる人の出現という問題を起こした。
当時、アメリカの内陸部には新たな国家(非承認国家)が誕生していた。そして、連邦政府、既存の州、新しい国家/州が複雑に絡み合っていた。
そして、重要なこととして、これらの地域では、一七八三年のパリ条約によってアメリカ大陸が決して平和になったわけではないと、著者は注意している。
アメリカが独立し、ヨーロッパとの関係では、平和を取り戻した。しかし、それが人々の移動を促し、アメリカ西部では、あらたな暴力と殺戮の引き金になった。
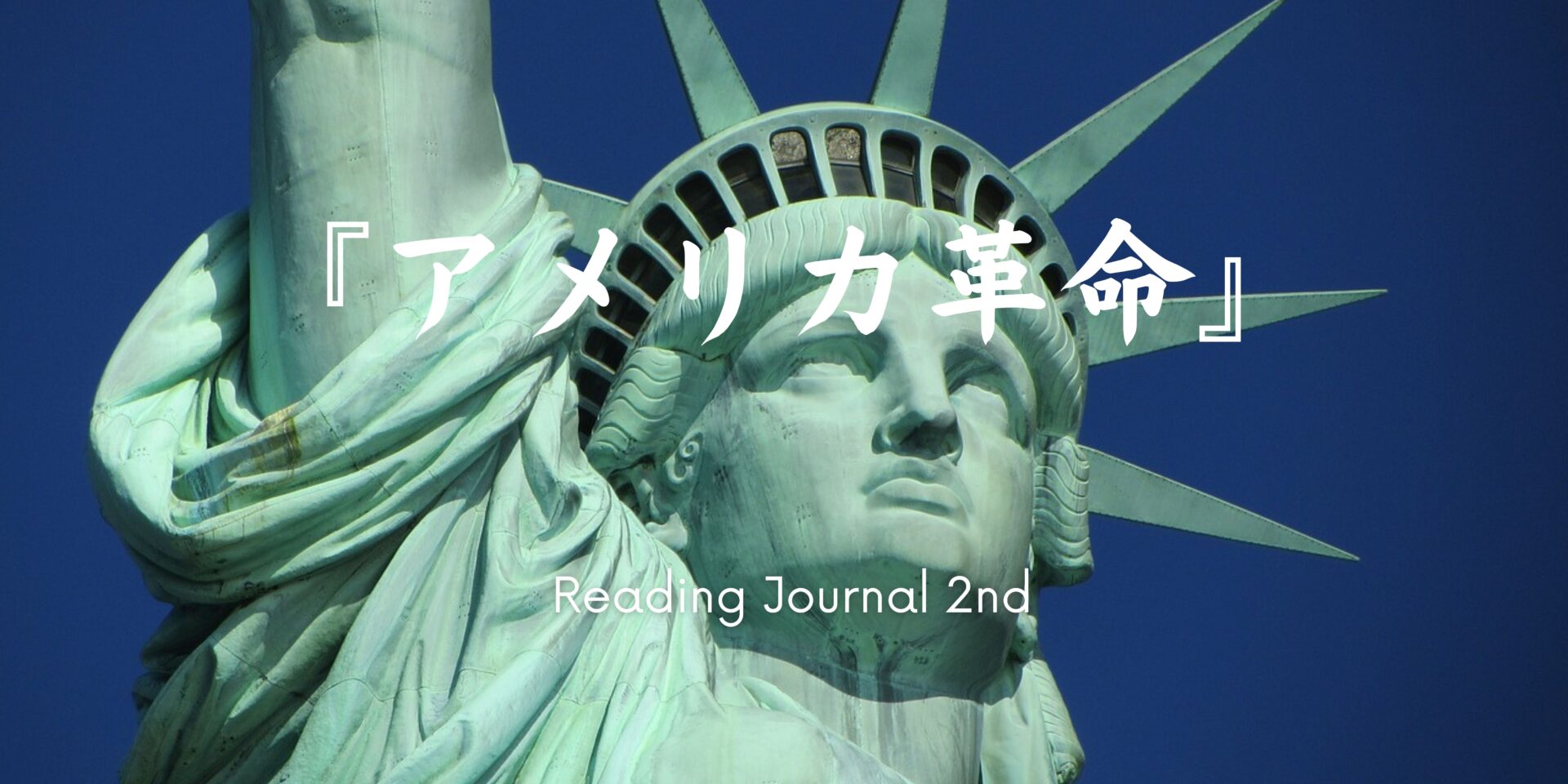


コメント