『100分de名著 安克昌 『心の傷を癒すということ』』 宮地 尚子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4回 心の傷を耕す
今日のところは、最終回「第4回 心のケアが目指すもの」である。これまで3回にわたって、阪神・淡路大震災後に行われた安克昌の活動を追いながら、心のケアについて学んできた。そして今日のところ最終回は、心のケアの社会的意味とその広がりについてである。それでは読み始めよう。
心のケア活動の普及
一九九五年は、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、それに加えて戦後五十周年の節目の年にあたり、戦争被害や加害の証言や記録が多く出版された年であった。そのため、多くの人が心の問題やケアについて考えるきっかけとなった。
それから三十年たって、心のケアに対する意識は向上した。とりわけ災害時の心のケアについては安をはじめとした多くのパイオニアの努力を踏まえて、今後も改善・拡充の努力がなされている。
阪神・淡路大震災当時の心のケアは、それぞれの場所で自発的に行われてきたため、散発的な取り組みになってしまった。そして、それを教訓として、現在は迅速かつ丁寧に、縦横斜めの連携を重視したケアを行う体制が少しずつ整えられている。
その一つが、『心の傷を癒すということ』にも登場する「こころのケアセンター」である。これは、当初は五年間の限定事業だったが、現在では恒久化し、さらに各地に同様な機関が誕生している。
また、二〇〇二年には「日本トラウマティック・ストレス学会」が誕生し、二〇一三年には「DPAT(災害派遣精神医療チーム)」が設立された。
「心理的な居場所」の重要性、避難所・仮設住宅の問題
『心の傷を癒すということ』 には、避難所と仮設住宅の問題も心のケアという側面から詳述されている。ここで重要なのは、「物理的」に安全が担保されている居場所というだけでなく、「心理的」にも安全な居場所ということである。
この心理的に安全な居場所とは、他者から受け入れられ、しかも他者から侵害されずに、そこにいることが安全に感じられる場所である。
まず避難所においては、その生活は過酷だが、まだコミュニティの痕跡は残っている。しかし仮設住宅や県外へ転居しなければならない人は、転居先に十分に心理的な居場所がなくなってしまう。
また、このような心理的な居場所の問題は、被災者だけでなく、学校に行けなくなった子供たち、同居家族との間に強い葛藤のある人、リストラなどで職を失った人、社会的マイノリティの人などの問題でもある。
この心理的な居場所を取り戻す問題は、まだまだ社会的課題を残している。
安は次にように語っている。
人間とはいかに傷つきやすいものであるかということを私たちは思い知らされた。今後、日本の社会は、この人間の傷つきやすさをどう受け入れていくのだろうか。傷ついた人が心を癒すことできる社会を選ぶのか、それとも傷ついた人を切り捨てていく厳しい社会を選ぶのか・・・・(抜粋)
心の傷を癒すということは、精神医学的なテクニックではなく、社会全体の問題としてとらえられなければならない。
安克昌の死と「喪の作業」
安克昌は、震災から五年目の二〇〇〇年にガンで亡くなってしまう。
このとき、安の家族やよく知っている人々の喪失は大きなものであった。
亡くなる直前まで、安は『多重人格者の心の内側の世界 — 154人の手記』の翻訳を中心になって進めていた。この本は、それ以前に安と中井久夫の共訳で出版した、フランク・W・パトナムの『多重人格障害 — その診断と治療』と対になる本であった。
この本の翻訳作業の取りまとめを解説者の宮地は安から託された。そして2年がかりの翻訳作業は宮地にとって、安からもらった「喪の作業」であると言っている。
そして今回取り上げた『心の傷を癒すということ』の新増補版が二〇二〇年に刊行され、その二年後には『安克昌の臨床作法』という本が出版された。このように作品への寄稿や翻訳・編集作業などは、安を慕う人たちにとってその死を十分に悲しむための「喪の作業」となった。
死別という事実は時間さえ経れば受け入れられるものではありません。大切なのは「死別を十分悲しむという作業」。(抜粋)
心に傷を「耕す」ということ
ここで解説者の宮地は、自身も精神医療考証として参加した『心の傷を癒すということ』をもとにしたドラマについて語っている。ドラマを作るという作業を通じて、共同作業が創り出す計り知れない力を感じたと、言っている。
このドラマ作りは、遺族や近しい人々にとって「記憶の想起と追悼」 --- つまり、記憶を掘り起こし、辿り直すことで、安さんを喪失したことと折り合いをつけていく機会でもあったように思います。(抜粋)
そしてこのドラマの制作メンバーや出演者、エキストラで参加した方たちの中には、阪神・淡路大震災で被災していた人もいた。彼らにとっても、みずからの記憶を掘り起こし、たどり直し、心の傷を「耕す」という経験になった。
そして、もう一つこのドラマから感じたことは「創作の力」であると宮地は言っている。ドラマには「心のケアって何か、わかった。誰も、ひとりぼっちにさせへん、てことや」というセリフがあるが、実際に安がこのように言ったわけではない。しかし、宮地は、このセリフに安の思いや考えていたことが、幾重に込められていると感じている。
「誰も、ひとりぼっちにさせへん」は、亡くなってからも安さんがさまざまなかたちで人と人をつないでいることを象徴している言葉だと思います。(抜粋)
社会の「品格」ということ
『心の傷を癒すということ』のなかに次のような言葉がある。
大げさだが、心のケアを最大限に拡張すれば、それは住民が尊重される社会を作るということになるのではないか。それは社会の「品格」に関わる問題だと私は思った。(抜粋)
社会の「品格」とは、そこに生きる人々が、尊重されていること、弱い人を見棄てない公平さである。安は、傷ついた人を医療の世界に閉じ込めるのではなく、社会に開いていくこと、人と人が尊重される社会を作っていくことが大切であると訴えていた。
そのような安の根底には、自身が在日コリアンとしてのマイノリティ性があると宮地は考えている。
安は、阪神・淡路大震災のときも、このマイノリティの人たちを排除する動きがあったと指摘し、コミュニティの助け合いという美しい面だけでないことも、記述している。
心に傷を負った患者は、究極のマイノリティである。その症状を診ることも大切だが、周囲がその人の世界を理解した寛容な社会を作っていくことも大切である。そしてそのようなことが、社会の「品格」となっていく。
バトンをつなぐ
最後に解説者の宮地は、安が残した『心の傷を癒すということ』に書かれているメッセージを読者の一人ひとりがつないでいくことに希望を託している。
さらに、被災した人、心に傷を負った人には、まだ苦しくて読めなくても、そのような作品があり、誰かがその苦しみについて書いていると思うだけでも救いになりえると言っている。
また、この本は、被災地に赴くボランティアや専門家、報道関係者の方々にはぜひ読んでほしいと勧めている。特に『心の傷を癒すということ』第I部の「ボランティア・ブームとトラブル」の項は、救援者と被災者や地元スタッフとのトラブルを避ける上で参考になるとしている。
関連図書:
バリー M.コーエン(著)『多重人格者の心の内側の世界 — 154人の手記』、作品社、2003年
フランク・W. パトナム(著)『多重人格障害 — その診断と治療』、岩崎学術出版、2000年
統合失調症のひろば編集部 (編)『安克昌の臨床作法』、日本評論社(こころの科学 HUMAN MIND SPECIAL ISSUE)、2022年
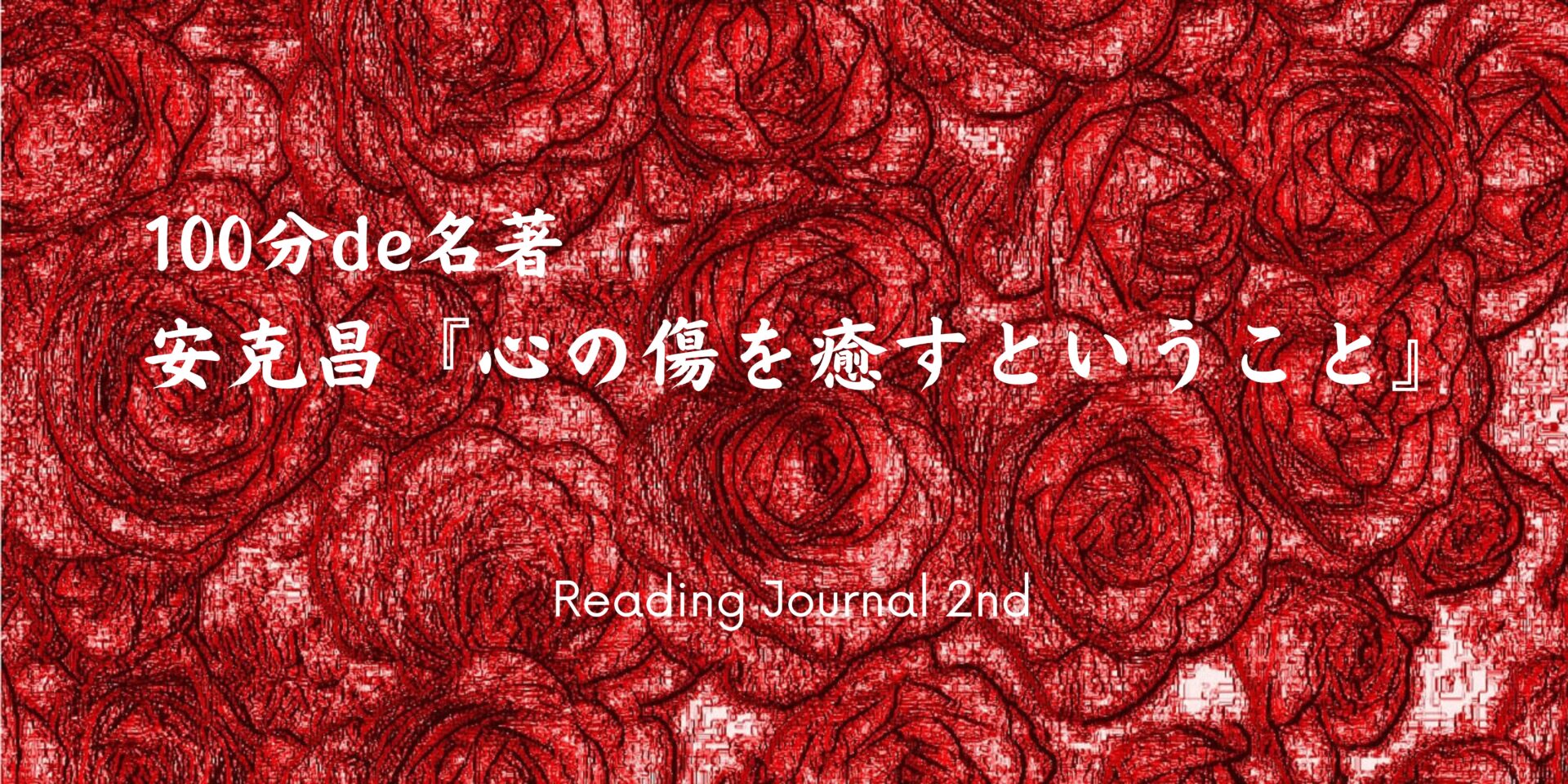


コメント