『100分de名著 安克昌 『心の傷を癒すということ』』 宮地 尚子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3回 心のケアが目指すもの
第3回 心のケアが目指すもの
今日のところは、「第3回 心のケアが目指すもの」である。第2回では、トラウマになりうる体験が、どんな症状になるかがテーマであった。それを受けて今日のところ「第3回 心のケアが目指すもの」では、具体的なケア活動で安が考えた「心のケア」のポイントがテーマとなっている。さらに、『心の傷を癒すということ』の新増補版に詳説されている「外傷性記憶」についての説明もある。それでは、読み始めよう。
安 克昌が行ったケア活動
この回の最初に阪神・淡路大震災後に安が行ったケア活動の様子が概説される。
いち早くケア活動に携わった安は、入院患者や通院患者のケアに加え、地域の保健所に設置された「精神科救護所」でも診療を行った。しかし、避難所の過酷さを目の当たりにすると、依頼を待つのではなく、こちらから出向いてのアウトリーチ活動も始めた。このような活動は今日では、あたりまえのように行われるが、当時としては先駆的な活動だった。さらに全国から集まったボランティアの精神科医の調整役も担い、避難所における夜間の緊急対応も開始した。この夜間の緊急対応は「世界でも前代未聞の試み」だった。
「共有する」ことの力
安は、このような救護活動の他に、大学病院内のナースステーションをまわり、被災した看護師たちへの巡回セミナーを行った。その目的は、看護師たちがお互いの傷つきに気づいてもらい、それを共有することによる、心の負担の軽減である。
この「共有する」ということのちからを、安さんはとても大事にしていました。(抜粋)
安は「孤立しやすい当事者にとってヨコの連帯はかけがえのないもの」「心の傷を癒すためには、”ヨコの関係”が非常に重要」と考えていた。
外傷性記憶(トラウマ体験の記憶)
『心の傷を癒すということ』の新増補版には、「外傷性記憶(トラウマ体験の記憶)」について詳説されている。ここでは、その「外傷性記憶」の要点が書かれている。
この「外傷性記憶」つまりトラウマ体験の記憶について、安は七つの性質をあげている。
- その多くが「断片的」であること。一連の体験のなかの一部が、なぜか突出して現れる。
- 「非言語的」であること。言葉に表現することが難しい感覚的なものとして想起する。
- 「否定的感情」。悲しみ、怒り、怨み、恥といった「否定的感情」がつきまとう。
- 「否定的考え」との結びつき。「自分は無力だ」「ダメな人間だ」「死にたい」などの「否定的考え」と結びついている。
- 「島状」に記憶される。外傷性記憶は、他の記憶と相いれず、溶け込むことのない異物感があり、そこだけ時間が止まっているように感じる。
- 「侵入性」。しかし、異物としてひっそりしているのではなく、自己のなか、あるいは意識のなかに侵入してくる。
- 別の外傷性記憶とのリンク。外傷性記憶は島状にありながら、「別の外傷性記憶とはリンク」してしまう。
傷の言語化と外傷性記憶、PTSDの治療
外傷性記憶の治療はPTSDの治療にもつながっていく。外傷性記憶が消えていくと、少しずつ言語化することが出来るようになる。そしてやがてトラウマ体験が自分の体験の一部として統合されてゆく。安は、
PTSDの患者は、心的外傷を受けていながら、その体験を自分の中に受け入れることができないでいる。つまり、治療の目標は、外傷体験を受け入れられるように援助することである。(抜粋)
と言っている。そして、このPTSDの援助について、トラウマ体験の研究者、ベッセル・A・ヴァン‐デア‐コルクの著書より、次の四つの要素があると紹介している。
- 安全であるという感覚:(安はこれが最重要と指摘している)
- その恐ろしい体験と折り合いをつける
- 生理的なストレス反応を統制する
- 安定した社会的つながりと対人関係における効力を再確立する
そして、「本人の自発性を大切にして本人のペースで、体験について語ってもらう」ことが治療の中心となる。心的外傷体験は、自分にコントロールすることが出来なかった体験であるが、その自分のコントロール感を取り戻すことが大事で、そのように力づけることがエンパワメントである。
心のケアの目標と“生きづらさ”からの回復
目立った症状が落ち着いてきても、まだ”生きづらさ“が持続していることがある。心のケアの目標は、この”生きづらさ“をいかに和らげるかである。
心的外傷体験をどう捉えるか、どう乗り越えるかは、その人がこれからどう生きていくのかという、人生そのものの問題になっていく。
表現することによる心の整理
安は、震災後の早い段階で、自分が「医療」の視点で心のケアを考えすぎたことに気づき、さらに「自分が治してあげなければ」という責任感から患者を抱え込んでしまったと反省している。
そして、心のケアだけでなく、この本を書くこと自体にも迷いを持っていた。しかし「心のケア」の見地からは、自分の体験を整理し、感情を表現することが気持ちの整理には重要であったとしている。
精神科医として、震災の影響を「心の傷」という視点から記録していく作業は、とりもなおさず安さん自身が「自分の体験を整理し、感情を表現する」ことでもあったのだと思います。(抜粋)
新しいものを作る作業と、「ポスト・トラウマティック・グロウス(心的外傷後成長)
心的外傷からの回復は、「やり直すのではなく、新しいものを作っていく」作業である。心に深い傷を負っても、本人の努力や周囲からの働きかけによって、新しい人生を拓くことが出来る。そしてそのような“もがき”の中で、心にポジティブな変化が生れることがある。それを「ポスト・トラウマティック・グロウス(心的外傷後成長)」と呼ぶ。ここで大切なのは”もがき“のプロセスである。
これは「レジデンス」という言葉についてもいえ、現在の「レジデンス」の定義は「リスクや逆境にもかかわらず、よい社会適応をすること」である。
心の傷は、元の自分に戻ることで癒されるのではなく、外傷体験を乗り越えようともがき、新しい自分と折り合いをつけていく力を獲得するプロセスによってこそ癒せるのだと言いたかったのではないでしょうか。(抜粋)
関連図書:安 克昌(著)『新増補版 心の傷を癒すということ: 大災害と心のケア』、作品社、2019年
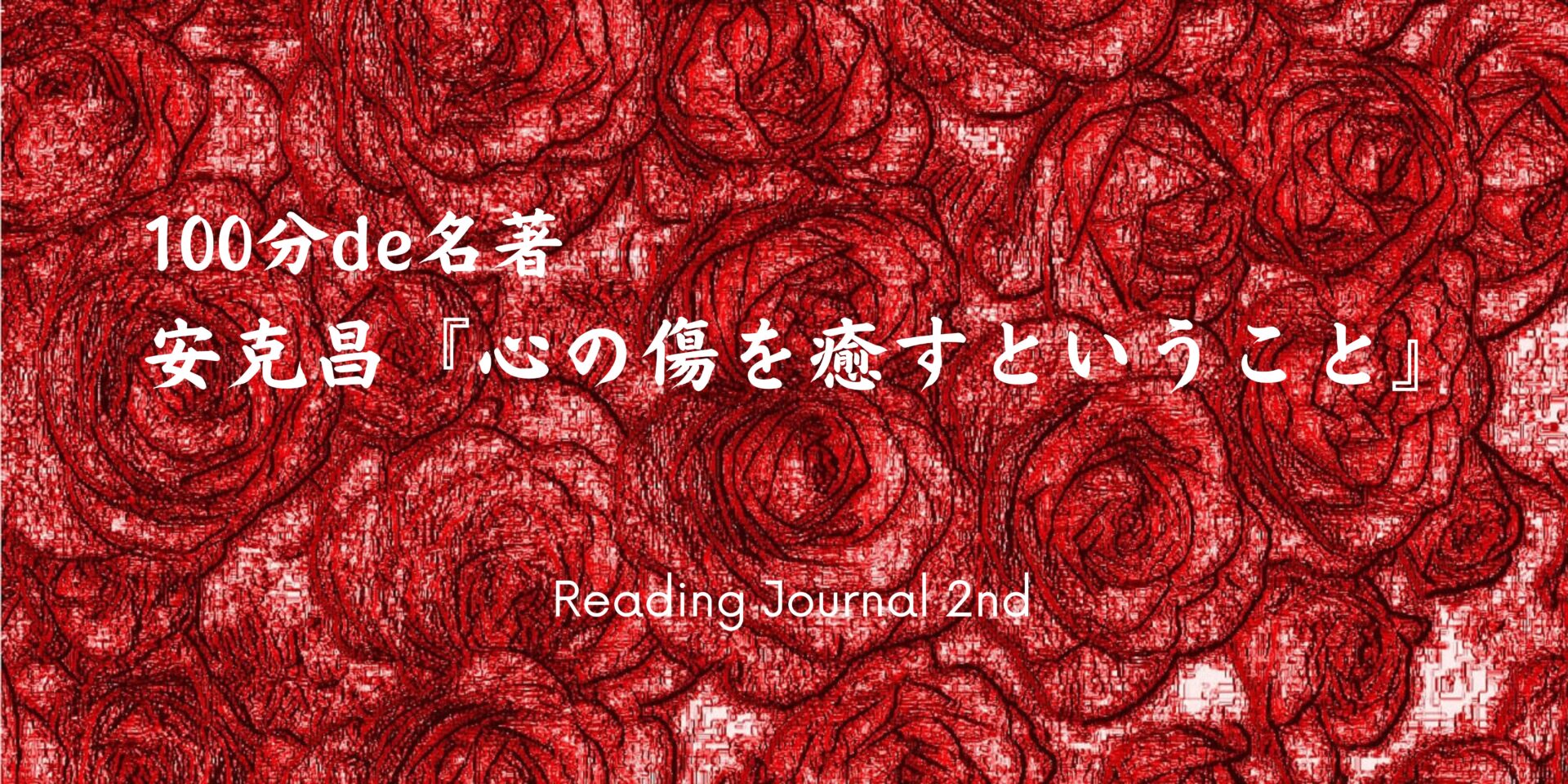


コメント