『100分de名著 安克昌 『心の傷を癒すということ』』 宮地 尚子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2回 さまざまな「心の傷」を見つめる(後半)
今日のところは、「第2回 さまざまな「心の傷」を見つめる」の“後半”である。第2回では、トラウマになりうる体験が、どんな症状になるかがテーマである。”前半“では、PTSDと悲観・喪失感が取り扱われた。今日のところ”後半“では、安克昌が「リアル病」と名付けたもの、心のケアを行う主体について解説されている。それでは、読み始めよう。
「リアル病」というもの
阪神・淡路大震災から四か月ほどたったころに、仙台の学界に出席した安は、「みょうな居心地の悪さ」「まるで映画を見ているような違和感」を感じた。そして安は、地震の体験から自分の価値観や感じ方が知らず知らずのうちに変わっていることに気がつく。安はこれを「リアル病」と名づけた。
この「リアル病」に対して、安は「リアルな事態にとらわれる一方で、口先だけのこと、やたらに理屈っぽいことに対して拒否反応が起きる」と分析している。リアル病には、楽しい時間を過ごしているときにも、どこか冷めた目で見ているような感じがあり、心のなかに相反する二つのものが共存している。
虚無感を癒すには
被災地が復興していくなかで、被災者は新たなリアルに直面する。それは「過去をひきずった今」であると安は書いている。
この「過去を引きずった今」という思いのなかには、「虚無感」つまり、「人間は運命の前には無力であり、社会は不公平であり、すべての営為、すべての価値は無駄だ」という思いがある。
この虚無感と戦いながら生きていくのは大変忍耐力を要することであるが、安は人と人との結びつきがその悲観論を癒してくれると言っている。
「安全な場所」「安全な相手」「時間をかけること」
被災者のこのような心の傷に対して、私たちは「何ができるか」「何をすればよいか」ということではなく、「苦しみがそこにある」ことを気づくことが大切である。そしてただ傍にいて、語られない苦しみを感じること、寄り添いつつ「待つ」ことが大切である。
心に傷を持った人は、「話してもわかってもらえない」と感じている。しかし、だからといって、助けを拒絶しているわけではない。このような心のケアには、「安全な場所」「安全な相手」「時間をかけること」の三つが大切なポイントとなる。
心に傷を持った人が語り始めた時「聞き役に徹する」ことが重要である。そして安は、デビッド・ロモの言葉を引きつつ「話の主導権をとらずに相手のペースに委ねる」「善悪の判断や批評はしない」などのポイントをあげている。
心のケアの主体
トラウマ反応がPTSDとして長期化することを予防するには、「被災体験を他人に話すこと、それについて感情を表現することが大切」であり、「救援者が、被災者の体験や感情を聞くことが<心のケア>になる」と安さんは書いています。(抜粋)
そしてここでいう、他人や救援者はカウンセラーに限らない。こころのケアはみんなのもので、社会全体で担うものである。相手がカウンセリングの知識やスキルがあるかどうかではなく、「この人といると安心する」と感じるようなときに、偶発的に”問わず語り“が起こったりする。詳しい事情を知らない人の方がかえって打ち明けられる場合もあり、意外に「いい加減」「言いっぱなし、聞きっぱなし」の方が良いこともある。
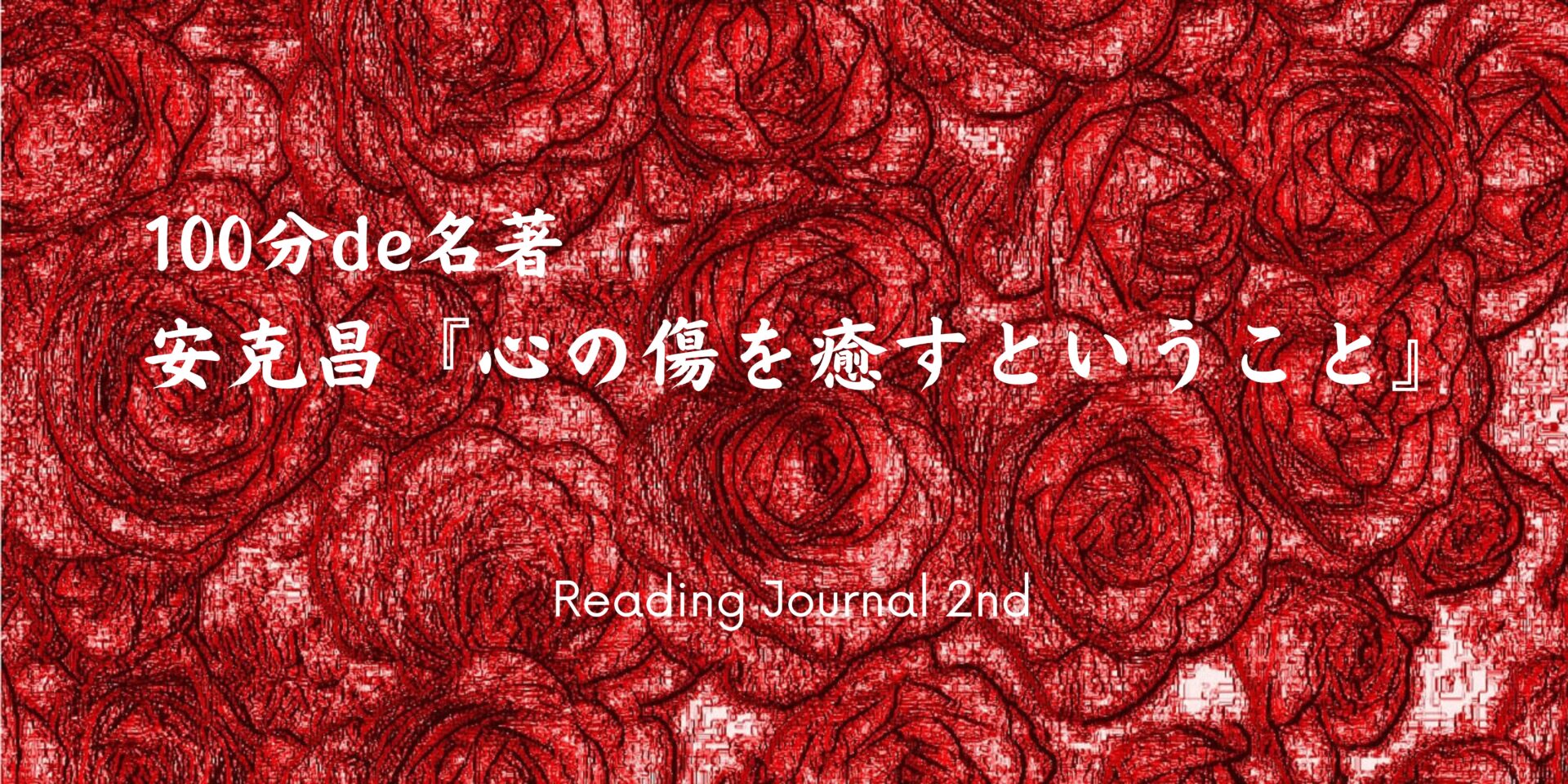

-1-120x68.jpg)
コメント