『100分de名著 安克昌 『心の傷を癒すということ』』 宮地 尚子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2回 さまざまな「心の傷」を見つめる(前半)
今日のところは、「第2回 さまざまな「心の傷」を見つめる」である。前回の「第1回 そのとき何が起こったか」では、震災での体験、特にトラウマになりうる体験がテーマであった。今日のところは、トラウマになりうる体験が、どんな症状になるかがテーマとなり、特にPTSD(心的外傷後ストレス障害)についてである。
この第2回は、二つに分け”前半“では、PTSDと悲観・喪失感を”後半“では、安克昌が「リアル病」と名付けたもの、心のケアを行う主体をまとめることにする。それでは読み始めよう。
PTSDの四つの症状
震災などのトラウマにやるような衝撃体験が引き起こす心的症状にPTSD(Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)がある。このPTSDには「過覚醒」、「再体験」「回避」「否定的認知・気分」の四つの症状がある。
- 「過覚醒」:「極度の緊張や警戒がつづく状態」である。常に神経が張りつめているため、くつろいだり、眠ったり、集中したりすることが難しくなり、ちょっとしたことで、驚愕したり、怒鳴ったりする。
- 「再体験」:衝撃的な体験をしたときの記憶や感覚が、ちょっとしたことで蘇って来ること。今まさに衝撃を受けているような「フラッシュバック」に襲われると、強い心理的苦痛や動悸・冷や汗などの身体反応も伴う。
- 「回避」:衝撃的な体験を想起させるものを避けること。それをなぜ避けるのか意識できないケースもある。またどこにトリガーとなる者があるかわからないため、引きこもってしまう人もいる。
- 「否定的認知・気分」:「否定的認知」は社会や世界に対するネガティブで強固な思いこみであり、「否定的気分」は、恐怖や怒り、不安、罪悪感といったマイナスの感情・気分を持ち続けるということである。トラウマを受けた人にしばしば見られ、周囲と疎遠になる、心が委縮し「麻痺」する、などの症状が起きる。
PTSDと生きづらさ
このような症状そのものは、「異常な状況における正常な反応」である。そして、時間とともに解消していくことも多い。しかし、PTSDはこのような「正常な反応」が解消せず、症状が持続し悪化した状況である。
しかし、「正常な反応」としての症状が落ち着いたように見えても、心の傷が解消されたとは言いきれません。目立った症状を伴わない“生きづらさ”は、治療の対象になりにくく、回復が妨げられてしまうこともあります。(抜粋)
死別の悲嘆と喪失感
震災時に多くの人の心に傷を与えたのが、大切な人との死別であった。とくに「子供を喪った親」と「親を喪った子ども」に大きな傷を残した。
この死別の悲嘆と喪失感は、トラウマとは別に考えた方がよい。トラウマは、なるべく避けたい出来事だが、喪失体験は、そこに引きつけられ、そのことばかり考えてしまうからである。
子供を喪った親の事例(「グリーフワーク」の必要性)
子供を喪った親のなかには、それが受け入れられず自殺を試みたり、大量の飲酒をしたり人もいる。そして、死別から数十年たってもなお悲嘆のなかに暮らす人も多い。
これは、動かしようのない事実をいかに受け入れるかという問題となる。死別を十分悲しむという作業(「グリーフワーク」)がまず必要である。安は、このグリーフワークの必要性を、震災で子どもを無くした親たちの会で改めて認識したと言っている。
また、「早く」立ち直ってほしい、「そろそろ」立ち直ってもいいころだろうという周囲の期待や文化が癒しを妨げていると指摘している。
ここに出てきた「グリーフワーク」という言葉は、柳田邦男の『人生の一冊の絵本』にも出てきた。この本は、絵本を紹介している本であるが、柳田邦男は、日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事故に関りを持っているため、この「グリーフワーク」に関連する絵本の紹介もある(ココとかココ参照)。(つくジー)
親を喪った子供の事例
安は震災で親を喪った震災孤児の声も紹介している。
多くの子どもは悲しみとともに、自分だけが助かったことへの罪悪感を抱いていた。阪神・淡路大震災では、多くの親が我が子をかばって亡くなっていた。
また、低年齢の子どもの場合は、親との死別というショックを和らげるために、罪悪感が空想的な思考や悪夢に結びつくこともあった。生々しい悪夢を見たり、無気力になったり、学校に行かなくなったりなどの行動面の他に、アトピー性皮膚炎やぜんそくなどの身体症状としてあらわれた。
震災孤児たちにとって最も大切なのが、「生き残った家族同士」の関係である。安は、子どもたちをサポートするには、「家族全体の傷つき」を考える必要があると指摘している。
家族に生じる亀裂
震災によって、夫婦関係の不仲や震災後に同居を始めた老親との関係など家族関係の亀裂も顕在化した。
夫婦関の亀裂は、震災直後の言動に対する不信感が強いわだかまりとなって生じるケースが多かった。またこれまで別々に暮らしていた人との同居は、平時でもトラブルやストレスの原因になるものであり、震災後のようなときはなおさらである。
このような家族の問題に子どもたちは敏感で、なかには病気という形で現れるケースもある。
関連図書:柳田邦男(著)『人生の一冊の絵本』、岩波書店 (岩波新書)、2020年
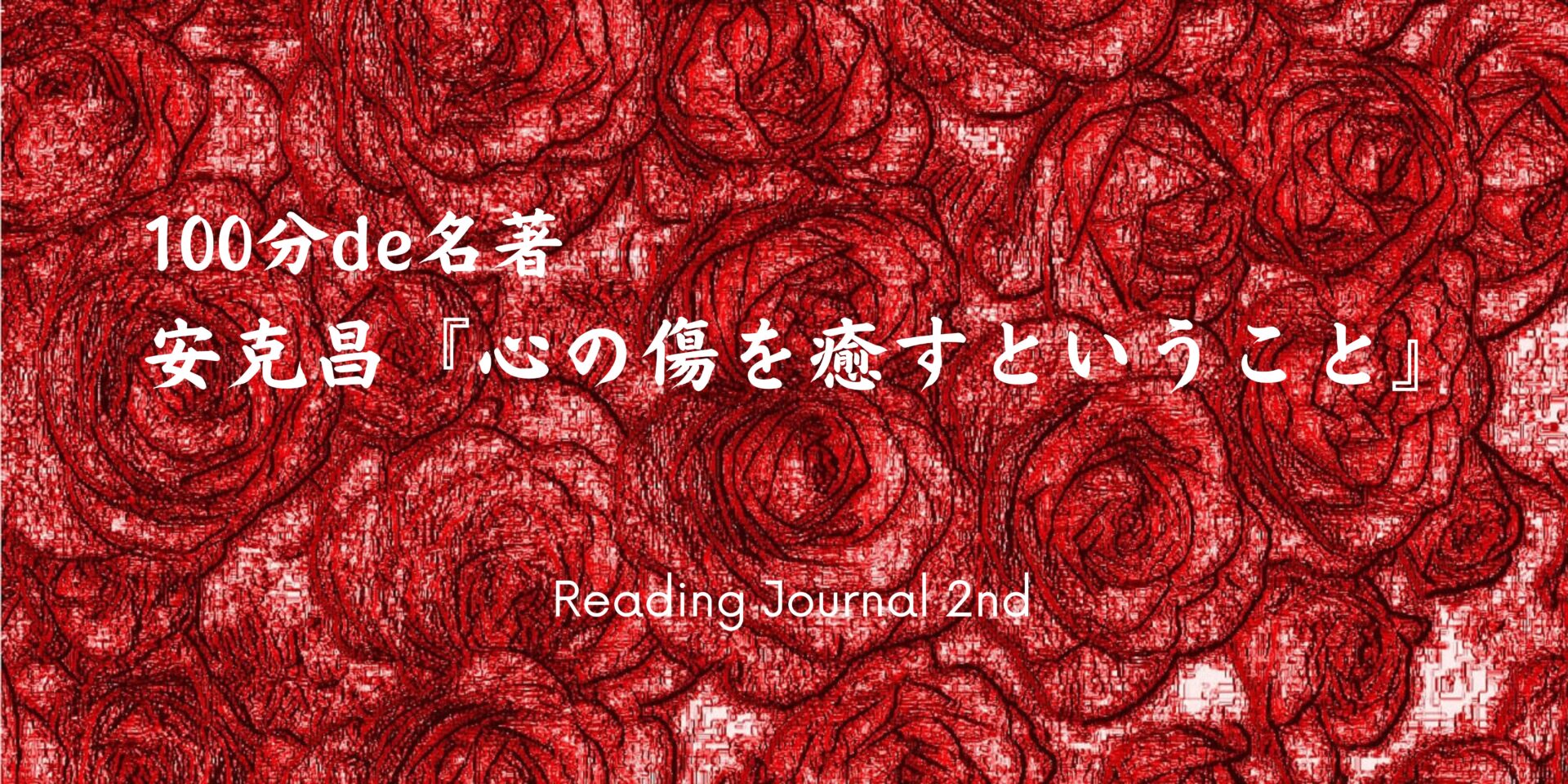


コメント