『100分de名著 安克昌 『心の傷を癒すということ』』 宮地 尚子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1回 そのとき何が起こったか
「はじめに」につづき、ここから本編に入る。今日のところは「第1回 そのとき何が起こったか」である。ここでは、阪神・淡路大震災が起こった後、安克昌が行った行動から書き起こしている。そこに広がっていた非現実的な世界があり、人々はPTSDなどの症状を抱え苦しんでいた。ここでは、それらを『心の傷を癒すということ』からの引用を交えて、取り上げられている。それでは、読み始めよう。
内側から当事者の声を伝える
『心の傷を癒すということ』は、一九九五年に起きた阪神・淡路大震災が人々の心にもたらした衝撃と、その後どのような心のケアが行われたかということを、被災者の姿が見える形で記録したルポルタージュです。一九九六年に出版されました。
まず解説者の宮地はこのように『心傷を癒すということ』を紹介している。
著者の安克昌は、早くからトラウマや解離性障害の患者を診てきた精神科医で、当時神戸大学医学部付属病院に勤めていた。かれは自らも被災しながら病院での診察、避難所を回っての心のケア、病院スタッフなどの心のケアに行った。
この活動で安が大切にしたのは「当事者一人ひとりの声」である。今でこそ当事者研究の重要性が言われるが、一九九五年当時はそういう考えを持つ人はごく少数だった。
安さんは震災以前から「治療者から見た当事者」やその症状だけでなく、「当事者自身」が語る痛みや希望、心に秘めた思いも含めて世の中に伝えたいと考えていました。(抜粋)
この『心の傷を癒すということ』は、つねにそのような視点から書かれている。
尚、このテキストは、二〇二〇年に刊行された新増補版の『心の傷を癒すということ』が定本である。
衝撃の大きさと非現実感
ここから、テキストは『心の傷を癒すということ』をすこしずつ読みながら解説がなされる。
まず、震災直後の様子であるが、安の記述は淡々と記されている。そして安自身も現実感を失っている自分に気づく。
PTSDとサバイバーズ・ギルト
大震災のような破局的体験は人々の心に耐えがたいダメージを与える。その一つがPTSD(Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス)である。
このPTSDで安の患者となった人が、安に語ったのは、避難している途中で「助けて!」と叫ぶ人たちのことだった。その人たちを助けられなかったという思いが、彼女を苦しめた。
このような、人を助けることが出来ず、自分だけ助かったという罪悪感で自分を攻めてしまうことは、「サバイバーズ・ギルト」と呼ばれ、多くの被災者を苦しめた。
このPTSDについては、福間詳『ストレスの話』でも解説されている(ココ参照)。(つくジー)
防御のための「大丈夫です」
安は震災後の看護師や医師、消防士などの様子も記述している。彼らの様子は意外にも冷静で、安が「たいへんでしょう」と言っても「だいじょうぶです」というだけだった。しかし、それはあまりのショックで現実感を喪失していて、仕事に没頭することによりその喪失感から注意を逸らせているだけだった。
このような現象は、衝撃的な体験をした人が自分を守るために現実感を失う「解離」という防衛機能である。また、衝撃を受けたことや傷ついたことぉ「否認」する行為も多くみられた。
安さんも指摘している通り、解離や否認は、「異常な事態に対する正常な反応」です。しかし、否認したまま仕事に没頭し続けると、「自らを酷使し、消耗させてしまう」ことに繋がりかねません。(抜粋)
こころが傷つく三つの出来事
PTSDという言葉は、この阪神・淡路大震災と同年の地下鉄サリン事件によって広く一般に知られるようになった。このPTSDは、トラウマになるような衝撃的体験から一定期間を経たのちも特定の症状が残り、著しい苦痛があったり、社会生活の妨げになったりする場合に持ちられる病名である。
ここで「トラウマ (Trauma)」とは、ひと言でいうと「心の傷」である。
このトラウマやPTSDになるような出来事には、大きく三つあると言われている。
- 命を奪われるかもしれないという凄まじい出来事
- 自分の無力を突きつけられるような出来事
- グロテスクな光景を目の当りにすること
露出した「内蔵」的現実
倒壊した建物が横たわり、崩れた建物からさまざまな物が散乱している様子を見て、安は「内蔵」を連想してしまうと言っている。このような「内蔵」的現実もグロテスクな光景の一部である。
震災の露わした「内蔵」的現実は、数年のときを経てなおトラウマとなって人々の心に沈潜し続けるのです。(抜粋)
つながりの再発見
震災によってライフラインが寸断され、当たり前のことが当たり前でない現実となる。しかし、一方で「人と人とのつながり」を再発見したと安は語っている。
震災後地域の多くの人が助けあうような光景が生れた。このような、震災後に生まれるある種の共同体感情は、災害心理学では「ハネムーン現象」「ハネムーン期」と呼ばれる現象である。
安は、そのことを文献で知っていたが、その思いがけないやさしさや思いやりを感じて、人間とはすばらしい存在と思ったと言っている。
安はこのような「人と人とのつながり」を「共同体感情の下で身をよせあう」と表現した。
人間は、強い不安や恐怖を感じたり、危機的状況に陥ると、そばにいる誰かと手をつないだり、思わず誰かにしがみついたりします。これは自然な反応です。物理的につながることで、安心感を取り戻すわけです。(抜粋)
しかし、「ハネムーン現象」のような、思いやりのあるコミュニティが発生するのに対して、自己中心的ではしたない行動をする人も現れる。そして、一時まとまっていたコミュニティがバラバラになったり、対立や分断が起こったりすることもある。
「人と人とのつながり」は、美しいばかりでなく、脆くもある。この脆さが秘めたコミュニティや社会で、人々の心の傷がどのような症状として現れ、時間と共にどう変化するかは、次回、解説される。
関連図書:
福間 詳安(著)『ストレスの話 そのメカニズムと対処法』、中央公論新社(中公新書)2017年
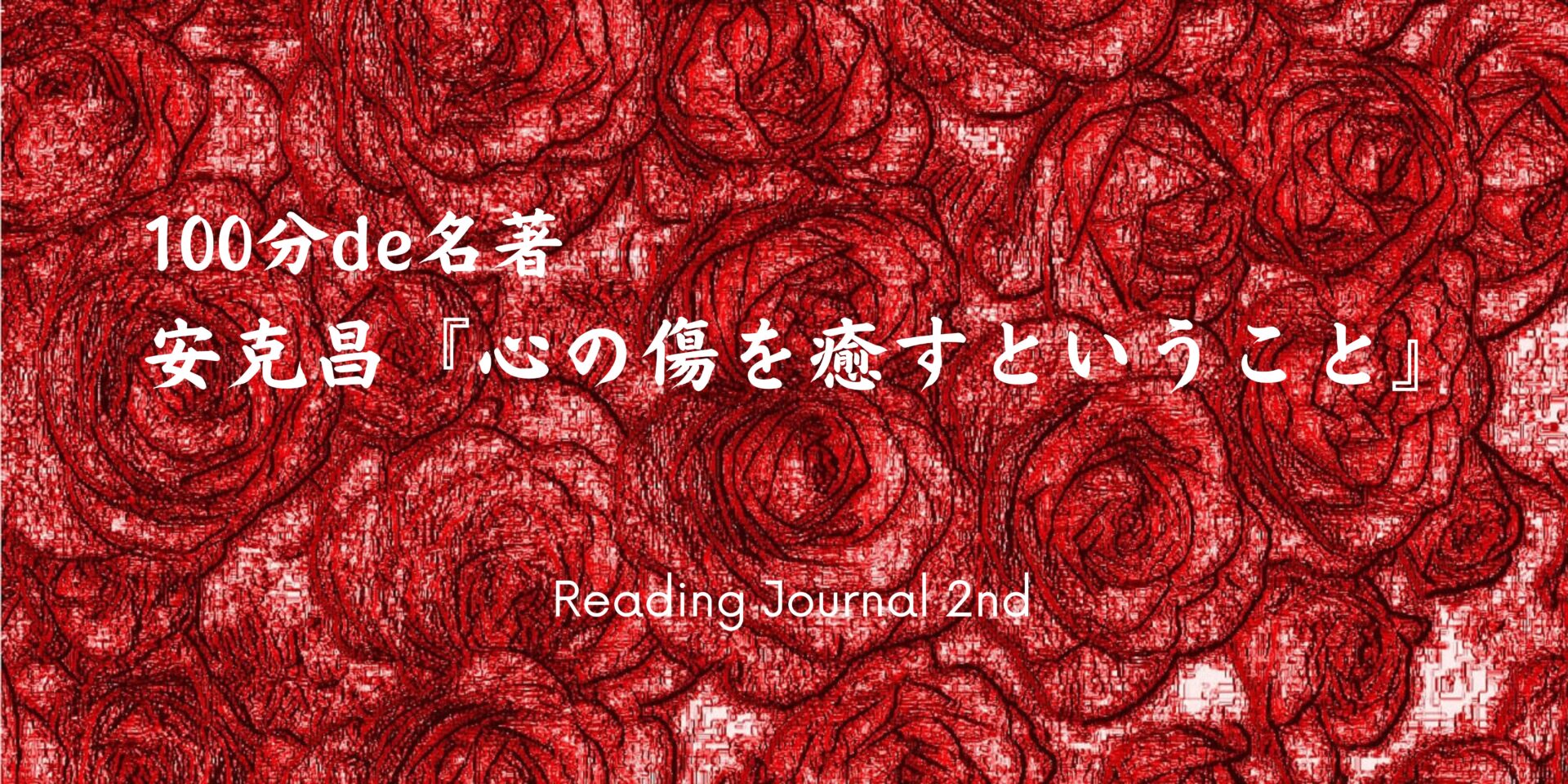


コメント