『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4章 本読みの方法(2) 二度目:詳細読み(前半)
今日から「第4章 本読みの方法(2) 二度目:詳細読み」に入る。前章「第3章 本読みの方法(1):通読」(ココとココ参照)で、ノートを取りながら「おおまかな地図」を作った。いよいよその地図を頼りに詳細に読むことを始める。
第4章は”前半“と”後半“に分けてまとめることにする。それでは読み始めよう。
全体の「大まかな地図」ができたら、二度目の読書、詳細読みに移る。ここで著者は難解な本は、「二度」程度では決して終わらないと、注意している。実際に著者の感触でも、相当に読み込んだ本でも7割理解できていることは稀である、と言っている。
専門的な書籍に関しては、何か月もかけて、何度も読み、また、一度理解したと思っても、何度も読み返すという作業を経て、次第に自分の知識となっていくと考えるべきです。(抜粋)
詳細読みの方法
二度目の読み「詳細読み」の中心は、通読で作成したノート・「大まかな地図」の細かい箇所を埋めていく作業となる。
詳細読みでは、読書ノートを横に置きながら読み進め、「思いついたこと」、「疑問に感じたこと」を該当箇所に記入していく。
そして、この詳細読みで大事なことは、「立ち止まること」である。一度目の読みで「?」の記号を付けた用語や概念を一つ一つ克服しながら読み進める。詳細読みでは、疑問を感じたら立ち止まって、ノートの前後を参照しながら、同じ個所を何度も繰り返して読む。そうすると不思議に「わかる」ことも少なくない。そして「わかった」と感じたらその内容をメモする。
「わからない」を大切にする
このとき「わからない」という感覚を見逃さないことが大切である。そしてその「わからない」理由を考える必要がある。
この「わからない」は多くの場合は、次のような理由による。
- その部分で使われている用語の理解が不十分:それ以前で「説明されていた」はずの用語に関して十分に理解せずに進んでしまった場合は、その漏れを発見する必要がある。
- その部分に使われている論理関係の理解が不十分
- その部分で扱われている問題の理解が不十分:よくわからないと感じたときは「問題」が何かを徹底的に考え直す必要がある。また、問題にも構成があり、上位の問題と下位の問題の関係を見失うとわからなくなる。
- 著者が言おうとしていることを図にする必要がある:一部の難解書には、文字面から論理を追っても理解が困難で、それを図形的な表現を使う必要がある。
「わからない」の対処法
ここから①~④の「わからない」理由についてひとつずつその対処法が解説される。
対処法1 用語の理解が不十分である場合
【対処法1-1】 その用語を説明していた部分にまで戻って、そこからしっかり理解することからやり直す
この時重要となるのが「読書ノート」である。読書ノートをさかのぼって該当箇所を探す。また、本に用語索引がついている場合は、それを利用することもできる。
ある用語が「特殊な意味」「一般と異なる意味」で使われている場合は注意が必要である。ある用語に「特殊な意味」を持たせている場合には、「著者の意図に沿ったかたち」で正確に把握する必要がある。また、そのような時はどこかに、その用語の説明があるので、それを発見する必要がある。発見したら、その定義をメモして「要注意!」などと書いておくとよい。
【対処法1-2】 対の概念に着目する
単語や概念は単独でなく対で用いられている場合がある。その場合は、「対」を成している単語との組み合わせをしっかりと理解する必要がある。この対の関係は翻訳でうまく訳出されていない場合もある。「対」を用いて概念を提示することは、思想家の表現上の技術であるので、もしわかりにくい用語に遭遇したら、その周辺に対となる用語が無いかを確認するとよい。
【対処法1-3】 その用語を、別の参考書や解説書、入門書、ネットなどで検索し、理解する
その用語がその分野であまりにも重要でことさら説明する必要がないと思われるため説明は省かれる場合がある。そのような用語は本の中には説明がないので、参考書、入門書、ネットなどで外部参照をする必要がある。またそのような用語は、翻訳者が、脚注をつけている場合がある。
このような基本的な用語を理解することは重要で、その理解なしにはその本の理解は決してできない。
対処法2 論理関係の理解が不十分である場合
【対処法2-1】 その文の前後をよく読み、その主張が導き出されている論理関係を把握する。必要であれば、読書ノートに論理関係を記載し、矢印で結び付けておく。
論理関係を見つける場合は、その論理関係が妥当か否かではなく、どのような論理関係を用いているのかを知ることが重要である。著者の主張が一般的な理解と異なる場合もあり、その主張がどのような論理関係から導き出されるかを把握しないと違和感だけが残る。
【対処法2-2】 その主張の周辺部分に、論理の筋道に該当するようなものがない場合は、その分野の概説書や入門書をあたり、その主張が一般的なものであるか否かを検証する。もしくは、その分野を専門とする人間に聞いてみる。
いくら読み返しても論理関係の道筋が存在しない場合もある。それは「外部参照」が必要な場合である。
「聞いてみる」のが早道だが、適任者がいない場合もあるので、読書ノートに「独立した主張」「根拠は明示されていない」などと記載する。読み進めていくうちに論理関係がわかったり、他書を参照して「この分野では広く受け入れられている論理」とわかる場合がある。
「そう言われている」と安易に理解するのは、のちのち困難を生じさせる。「根拠が明示されていない」と一旦書き込んでおいて、後に根拠を探すのが効率的である。
ここで著者は、「論理関係」を批判的に検討することはさらにレベルの高い読書となり、それに拘泥するあまりに、本の内容の理解を中断するのは本末転倒と注意している。
このような場合は、のちのちのために「論理展開に難ありと感じる」などと赤文字でメモを残すのがよい。
対処法3 問題の理解が不十分である場合
【対処法3-1】 その部分の近くで中心的な「問題」を探し出す。そして、その「問題」と、その(理解が困難な)箇所との関連を考える。
その部分の主張の「役割」が理解できない場合に「わからない」と感じることになる。ある部分は必ず全体の論理展開を支える「役割」を担っている。その「役割」を理解するためには、前後の部分の「問題」をきちんと把握する必要がある。
登山型の本、閉じている本の場合は、「問題」が読書ノートに書かれているはずである。本文で躓いた部分の前後の読書ノートを確認し「問題」の記述がないかを探す。
「登山型の本」や「閉じている本」の場合には、それぞれの部分の役割を理解しながら読み進んで行くことが、全体の理解の早道となります。(抜粋)
本文で重要な「問題」を見落としてメモし損ねている場合もあるので、それを探し出せるように、読書ノートには、要所要所で参照ページを書いたり矢印で結んだりしておくとよい。読書ノートや本文を読み返してもどうしても「問題」が見当たらない場合は、本のその部分に傍線を引いて「どこに説明があるのか?」と書いた付箋を貼っておく。
【対処法3-2】 問題が明確に提示されている部分が発見できない場合は、「外部参照」している可能性があるので、他の書籍やネット検索などを用いて、「問題の構造」を明らかにする。
問題がどうしても明確に書かれていない時、その問題が「その分野では当たり前」の場合がある。その場合は別の本で外部参照をしてしっかり学ぶ必要がある。
【対処法3-3】 その部分の役割や位置づけが明確にわからない場合、「ハイキング型」の部分であると考えて、とりあえず次に進む。
「登山型の本」の場合でも、部分的に「ハイキング型(読者に周囲の状況を考えさせるタイプ)」の部分が含まれていることがある。その場合は、その部分の役わりや位置づけを見つけることはできない。
対処法4 著者の主張を図にする必要がある場合
【対処法4-1】 該当部分を抽出・吟味して、図を描いてみる。
現代思想の分野で多く見られる「図形的イメージの比喩」の場合は、文章そのものは非論理的に見えることがある。その場合は、「その部分の図を描く」ことが理解するためには必要である。この時、自分なりの図を書くことが大事である。そして読み進めていって著者のイメージとズレがあるなと思ったら、書いた図を更新する。
【対処法4-2】 そもそも、その単語や概念の示す図形的イメージがわかないとき。
「ベクトル」「フラクタル」などの数学的用語が使われている時、「ファサード」や「切妻」などの建築用語が使われている場合は、その図形的意味の最低限の知識は必要である。用語集などで理解することが求められる。
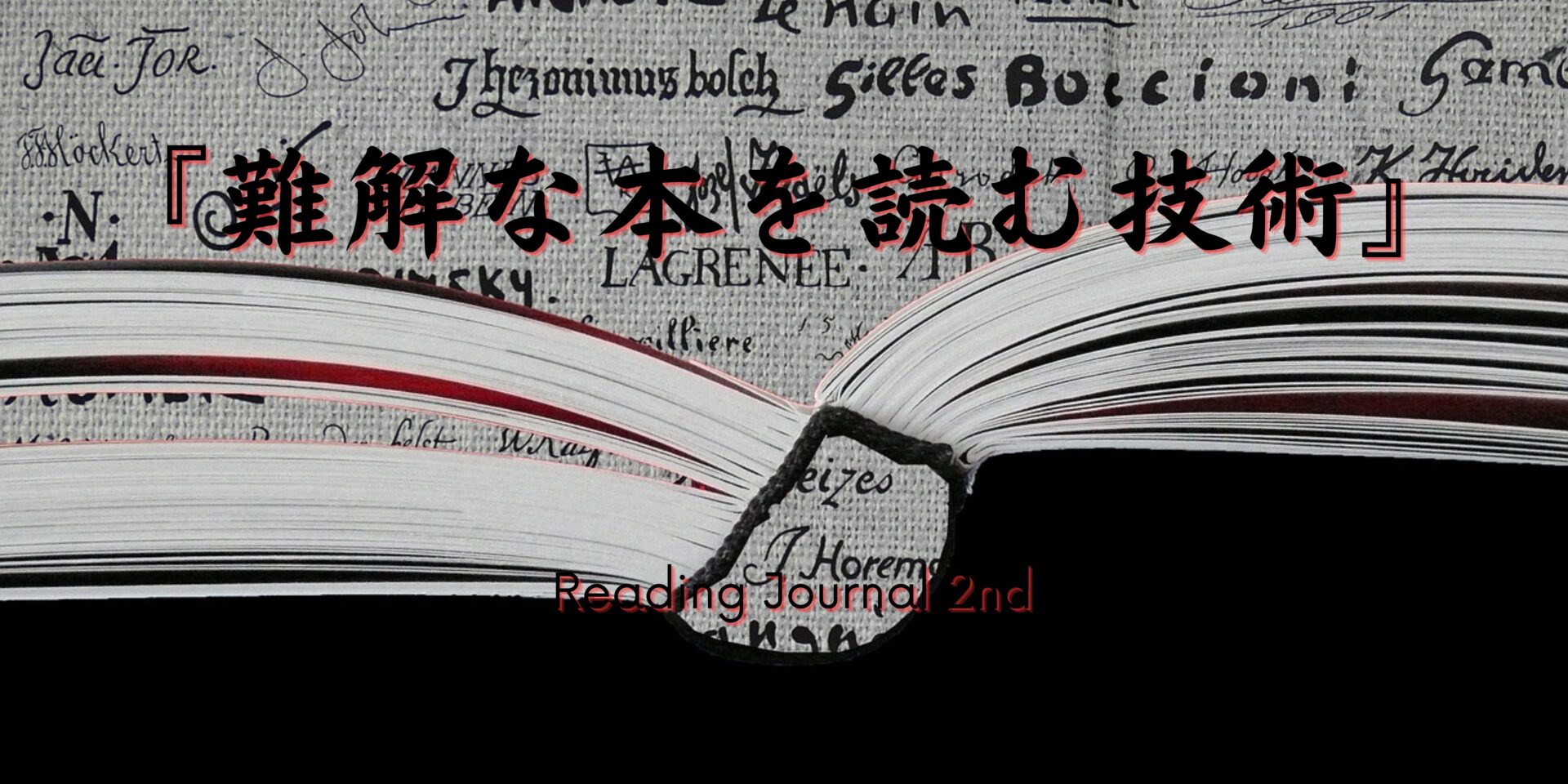


コメント