 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 憲法とそれ以外の法 — 憲法法典の変化と憲法の変化(その3)
長谷部 恭男 『憲法とは何か』より
憲法は、憲法典を素材に法律の専門家が紡ぎ出した慣行の集まりであり、テクストを変えたからと言って、必ずしも憲法が変わるわけではない。また、憲法典を変える場合は、それによって、どの程度「憲法」が変わるかを専門家に聞く必要がある。:『憲法とは何か』より
 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 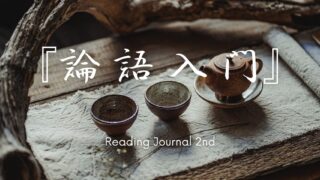 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 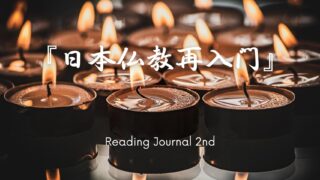 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd -320x180.jpg) Reading Journal 1st
Reading Journal 1st -320x180.jpg) Reading Journal 1st
Reading Journal 1st 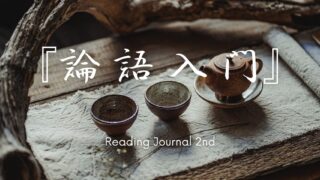 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 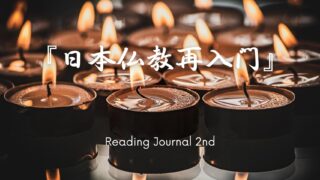 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 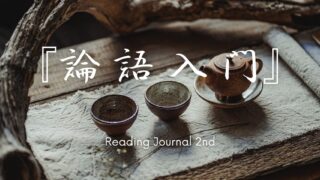 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd