「漱石」 三浦 雅士 著
[Reading Journal 1st:再掲載]
(初出:2009-01-29)
第八章 孤独であることの意味 - 『道草』
初期の三部作(『三四郎』『それから』『門』)、後期三部作(『彼岸過迄』『行人』『心』)には、母に愛されなかった子という主題が直接的に書き込まれていないが、その疑いのために形成された心の癖が一貫した主題になっている。
『彼岸過迄』では、市蔵は母と向き合っているのではなく、千代子と向き合っているが、その心の癖は母とのあいだで形成されたものだ。
漱石が自身の心の癖と向き合っていることを示している。母と向き合っているのです。(抜粋)
『行人』の主題は一郎とお直のぎくしゃくした関係である。小説の結論では、一郎の中に見出せる哲学(一種の唯我論)を理解できないお直が悪いということになっている。しかし、誰もそんな読後感を持たない。一郎が千代子を取るに足らない女だと馬鹿にしきっているように思える。
漱石は、こころで、その疑問を自分に突き付けている。『心』では、それまでの主人公、語り手などをすべて先生に流しこんでいる。
先生は、寄ってたかって自分を好いようにしてしまう親族に身構えると同時に、こっちがいくら思っても、向こうが内心、ほかの人に愛を注いでいるならば、私はそんな女と一緒になるのは厭だと思う人間だが、それは、それまでの漱石の主人公の心の癖、心の機制を示している。エッセンスのようなものです。(抜粋)
他の人に愛の眼をそそいでいるのが厭だというのは、母との関係において形成される。
『心』を書き終えた漱石は『硝子戸の中』において母と真正面から向き合っている。自分の生まれ、里子に出された経緯、母の思いでなどが語られている。
文面からは、漱石が母に愛されていなかったとは思えない。少なくとも、相互に悪い感情を持っていたとは思えないわけだが、だからこそ逆に、なぜ里子に出し養子に出したのかという疑問がいっそう強められただろう。(抜粋)
漱石は、『硝子戸の中』の後『道草』を書く。
『道草』は、漱石自身をモデルにしている。ここでも母は出てこないで、主人公は妻と向き合っている。『道草』は、主人公の健三のみならず、副主人公の妻、お住がよく描かれていてみごとである。
健三は、妻が何か自分に含むところがあり悪意を持っているというようにしか話せない。この回り込むような話し方の背後に母に愛されなかった子としての体験が潜んでいるとすれば、『道草』全編にその主題が浸透していると言える。
小説は、金をせびりにきた養父の島田に金を渡したところで終わる。その時、あの人とはこれで片付いたというお住にむかって健三は、世の中に片付くなんてことはない、いっぺん起こったことはいつまでもつづく、ただ形が変わるから他人にも自分にも分からなくなるだけだと言う。会話の後、お住は赤ん坊を抱き上げ、おお良い子だと言いながら、何度か赤いほっぺに接吻する。
この会話がじつに意味深長に思えてしまうのは、母に愛されなかったという幼児体験は、結局いつまでも続く、それが他人にも自分にも分からなくなるのは現れ方がいろいろな形に変わるからだけだと言っているように響くからです。フロイトの理論そのものです。それに対してお住は、赤ん坊を抱き上げて接吻することで答えるわけですが、その母子関係こそ幼い漱石が心から望んだことにほかならなかったのです。(抜粋)
健三の幼児体験の悲惨は、養父母の島田とお常によってもたらされたが、実父によって仕上げられた。実父にとって健三は小さな厄介者であり、養父母の離婚により実家に帰った健三は、豹変した父によってさらに大きな打撃をうける。実際の漱石においてもそうであったに違いない。
健三は、心の癖をもった人であった。養父の島田にずるずるとお金を払い続け、妻には冷淡で何でも疑いの目を向けた。『道草』の主題は自分はどうしてそういう人になったのか、どうしてこのような心の癖ができたのかを探究することだった。
健三は『道草』の終盤に兄弟に関する不愉快な事件を思い出す。二番目の兄が病死したときの形見の件で、兄にも姉にも義理の兄にも無視されてしまう。
彼は自分の権利も主張しなかった、また説明も求めなかった、ただ無言のうちに愛想をつかした、そうして親身の兄や姉に対して愛想をつかすことが、彼らにとっていちばん酷い刑罰に違いないだろうと判断した、というのである。
母をめぐる争いにおいて、漱石は、兄や姉には存在しないも同然だった。里子に出され、養子に出され、帰って来てからも、父にはガラクタ同然に扱われたのである。兄や姉にとって漱石は無に等しかった。少なくとも漱石の眼にはそう見えた。時計はその事実を、もはや成人したにもかかわらず、再び強烈に漱石の眼前に突きつけたのである。
それに対して漱石は、ただ無言のうちに愛想をつかした、そうすることで、彼らにとっていちばん酷い刑罰になるだろうと判断した。(抜粋)
これはどう言うことか、心を閉ざすということ、孤独になるということである。孤独になって激しく精進して勉強して偉くなる、尊敬できる人物になると言いうことである。
漱石は、この刑罰を最も身近なもの、もっとも自分を愛している可能性のあるものに適用する。もちろん東京にも松山にも学界にも文壇にも適用するが、もっとも効果が目にめるのは、もっとも身近な妻であった。
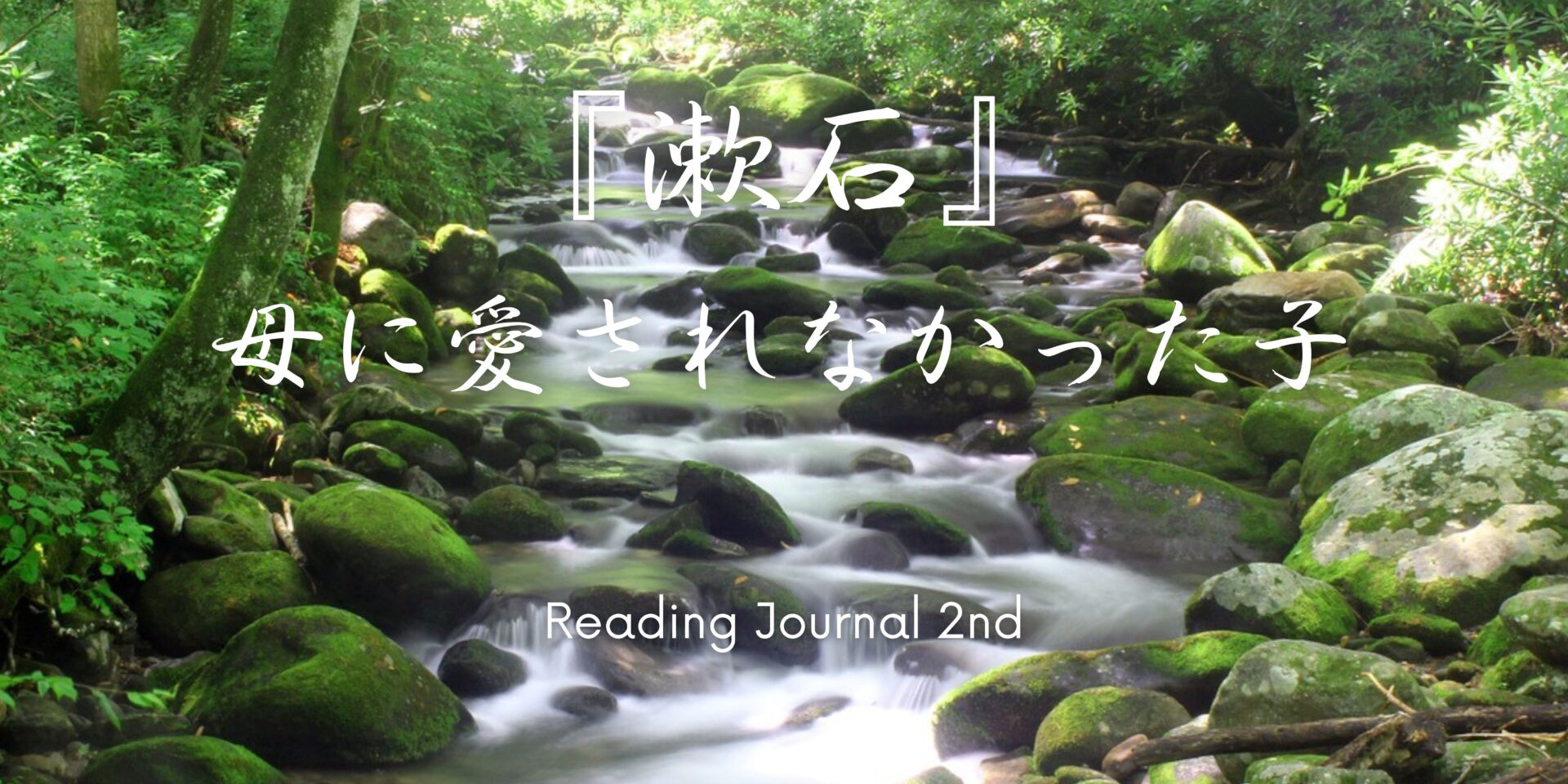


コメント