「漱石」 三浦 雅士 著
[Reading Journal 1st:再掲載]
(初出:2008-10-22)
第五章 母から逃れる - 『三四郎』『それから』『門』
漱石は『虞美人草』を書いた後、母に愛されなかった子という主題から解放されたように見えるが、そうではない。たとえば、母という主題と無縁と思われる『坑夫』ですら、関係がないわけではない。
抗夫は、家出をして抗夫になった青年の体験談から執筆されたが、それは、自身の主題に共振するところがあったので取り上げられたのだ。『抗夫』は、『虞美人草』で、主人公がじゃ消えてやるよと言って本当にそのまま消えてしまったらどうなったかを書いたものである。『抗夫』では主人公は、世間が厭になり生家が厭になり、消えてやるよとばかりに家を飛び出し、そのまま自殺することもできないので、抗夫になる。そして青年は地下深くで危うく死にそうになる。そこで安さんという先輩に出会って諭されるのである
地下は冥界の母胎である。それこそ父母未生以前の場。生への回帰を示唆する安さんは、さしずめ始原の母の代替物である。・・・・中略・・・・・一度は死ぬかと思ったその暗い場所で出会った安さんは生の象徴なのであって、その象徴に向き合うことが重要なのだ。・・・・中略・・・・・
母から逃れた先で母に出会ったようなもの、本人が気づいていないだけなのです。(抜粋)
このことは、漱石の書いた紀行文『満韓ところどころ』によって、さらに明確になる。漱石は、この紀行文を炭坑を見学しようと下り、やっと目が慣れて見学しようとするところで突然終わりにしている。これは、紀行文としては、きわめて中途半端だが、小説としては極めて暗示的であり、読者は『抗夫』を思い出してしまう。
漱石自身もまた思い出したに違いない。書き進めてきた『満韓ところどころ』が、結果的に過去への旅であり、自身の病の意味を自覚する旅であり、自己内面への旅であることを思い知らされたに違いない。(抜粋)
この坑内の奥へ奥へ下りていくその先に待ち構えていたものは、自己自身との対面であるほかならないのである。そして、これこそが『三四郎』をはじめとする初期三部作の主題、愛されていたことに気付かなかった罪、すなわち、『虞美人草』の裏返しなのである。
また『抗夫』のもう一つの意義は、文体の変化である。ここでは漢籍を用いた表現はほとんど姿を消し、また思想もすべて登場人物を通して表明されている。
簡単に言えば、漱石はここで他人になる訓練を自身に課したわけです。(抜粋)
『三四郎』においてこの他人になる技術は、高度に発揮されている。まず三四郎が上京する場面である。三四郎は自身の曖昧な態度から、汽車に乗り合わせた女性と同じ宿屋の同じ部屋の同じ布団で休むことになる。三四郎は布団に敷布で仕切りをつけて寝て、何事もなく一夜を共にする。翌朝三四郎は女に、あなたはよっぽど度胸のない方ですねといわれる。この冒頭の場面の女は『草枕』の那美さんの延長上にあり、後に出てくる『三四郎』のヒロイン美穪子を予告している。
漱石は、三四郎と床をともにしたこの女の身になりもすれば、美穪子の身になりもしているのである。だからこそ、女の欲望も美穪子の欲望も、本人自身、気づいていながら気づいていないような曖昧な領域として描かれているのだ。(抜粋)
女も美穪子も三四郎に好意をもったのである。しかし三四郎の鈍感さはその事に気がつかなかった。異常なのは三四郎のほうである。
鈍感は罪である。三四郎は愛されていなることに気づかない罪、鈍感の罪を犯している。
・・・・・中略・・・・・
『三四郎』だけではない。『それから』『門』と続く三部作で主題とされているのは、自分が愛していること、自分が愛されていることに気がつかない罪にほかならない。
そして、このことは、『虞美人草』で描かれたことの裏返しなのである。
『三四郎』で描かれている愛されていることに気がつかなかった罪という主題は『それから』『門』でも繰り返されている。(抜粋)
『それから』の主題も愛されていることに気づかない罪である。物語は高等遊民である主人公(代助)のもとに、一通のはがきが来る事から始まる。はがきは代助の友人の平岡からで、彼が関西の銀行を首になり東京へ来るというものであった。また、平岡の妻、三千代は代助が仲を取り持ち平岡へ嫁いだ。
もともと三千代に好意以上の感情を持っていた代助の心は日に日に高まっていった。そして、代助は三千代に自分の気持ちを伝える決断をする。
僕にはあなたの存在が必要ですという代助に三千代は「残酷だわ」という。事情があるとはいえ別の男と自分を結婚させておいて、三、四年もしてからじつは好きだった、思い切れない、あの男と別れて自分と一緒になってくれと言うのは、残酷としか言いようがない。
重要なのは、三千代に乗り移られた漱石が、まるで必然であるかのように代助に向かって、なぜ捨ててしまったのか、と詰問してしまっているという事実です。
・・・・・中略・・・・・
表現者の必然として他人になりかわったいま、まさに自分の代理人と言うべき代助に向かって、つまり自分自身に向かって、漱石ははっきりと問うことになったのである。なぜ捨ててしまったのか、と。
・・・・中略・・・・・
自分は母に捨てられたのではない、逆に母を捨てたのではないか、と。(抜粋)
ここで、なぜ捨てたのか、の問いに代助は、だから罰を受けていますと答える。罰と復讐の関係がここでは、『虞美人草』の時と逆になっている。
その後、三千代がゆっくりと、しょうがない、覚悟を決めましょうという言葉を行ったとき代助は怖くなったのである。
この、なぜ捨てたのという問いは、漱石がじゃあ、消えてやるよという台詞を使ってはいけないところで使ってしまったという事を示している。
『それから』の代助が問いつめられているのは、じゃあ、消えてやるよと言ってしまう自分とはいったい何であるんかという問題です。これこそ母に愛されなかった子という主題の核心である。(抜粋)
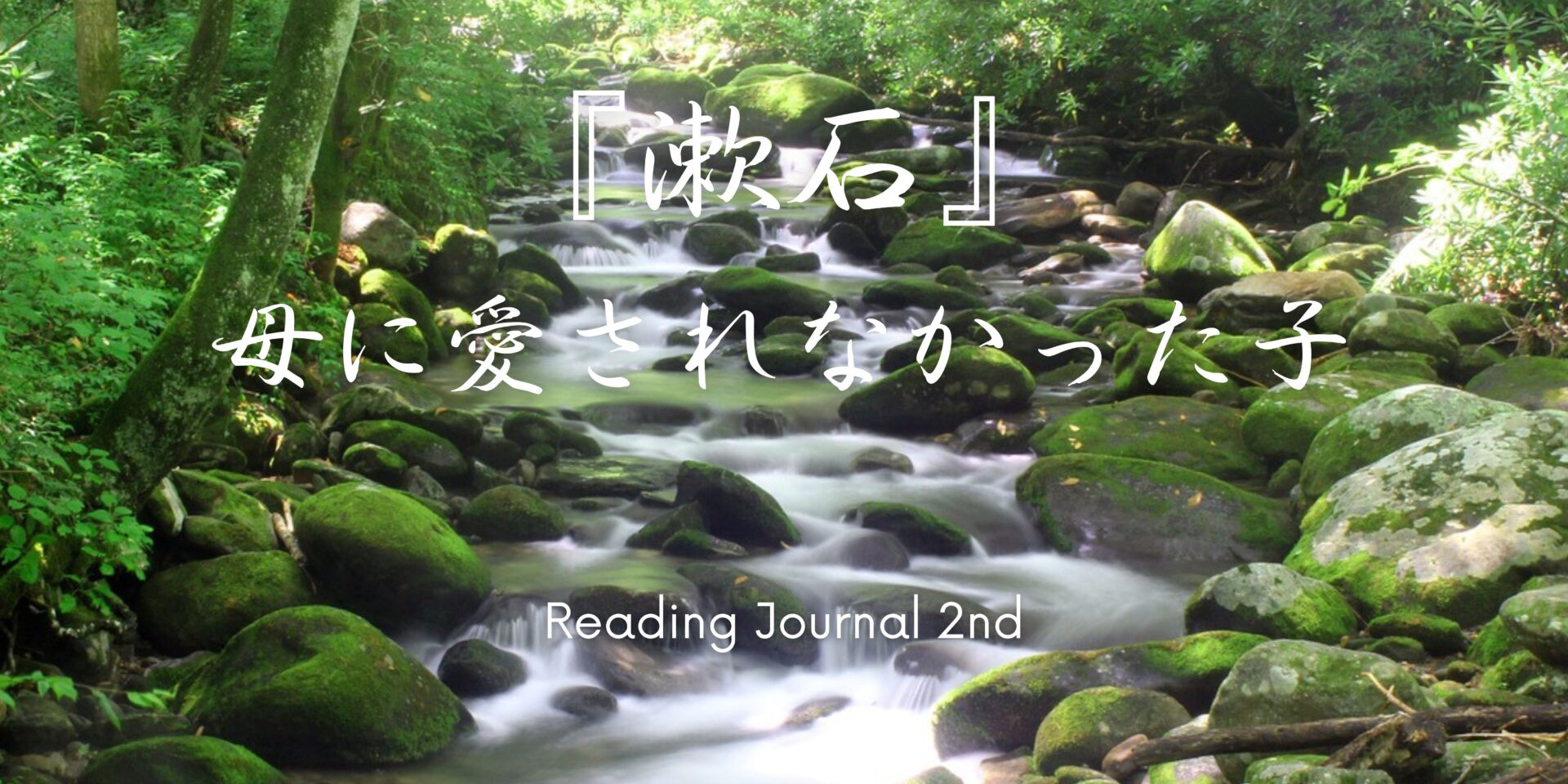


コメント