「漱石」 三浦 雅士 著
[Reading Journal 1st:再掲載]
(初出:2008-10-20)
第三章 登校拒否者の孤独 - 『木屑録』と『文学論』
夏目漱石は、引きこもっていた時期が2度ある。一回目は十五歳春から十六歳秋までの一年半、二回目は、ロンドン留学の時期である。
ここでは、その引きこもっていた時期に焦点を当て、漱石の文学論への歩みを読み説いている。
漱石は母が亡くなった一八八一年の春に在籍していた東京府第一中学校を中退し、漢学塾である二松学舎に入学している。なぜ漱石は二松学舎を選んだのか、それは漱石自身の漢学への関心に加え、急速な西欧化の反動として儒学を中心とした道徳教育が復興してきた当時の状況もあり、漱石がかつての学問に近づきたかったからであると著者は推測している。
しかし、この二松学舎も一八八二年の春には辞めている。そして翌年の秋に成立学舎に入学するまで、漱石は一年半もぶらぶらしているのである。
漱石は登校拒否者だった。(抜粋)
漱石の談話『一貫した不勉強』に、漱石が中学校を辞める前に学校に行かずに道草を食っていたという記述がある。これは十三歳、中学校二年生のことであると考えられる。その後中学を中退して二松学舎に入っているのだが、それも一年余りで辞めている。『硝子戸の中』の記述などから中学校時代の漱石は神経症と言っていい世界にいた事がわかる。
そういう世界の中にあって、漱石は肝心の母を失い、中学校を退学してしまった。すぐに二松学舎に入るが、それも一年ほどで止めてしまう。それから一年半、十五歳から十六歳にかけて、まるで登校拒否を貫徹するかのように、学業優秀であったにもかかわらず、漱石はどの学校にも行かなかった。(抜粋)
この引きこもりの時期に漱石が何をしていたのか。『木屑録』によるとその時期に漱石は文学で身を立てることを思っていたのだという。
漱石は、挫折と引きこもりという、十代での危機の体験をそのままロンドン留学中に反芻することになる。
留学するにあたり漱石は、オックスフォードなどの大学に在籍することをあきらめ、ロンドンに在住して大学での現代文学史の聴講と個人教授を頼んでそのつど質問する事にした。しかし、大学での聴講は三、四ヶ月でやめ、個人教授も一年で辞めっている。
このことは、第一中学を退学して二松学舎に移り、そこも一年で辞めた少年時代の体験に重なる。
漱石は『木屑録』の中で、登校拒否、退学、転校、再び退学、そして引きこもりの十代の危機の中で、文学の定義を得たと言っている。
それと対応して、漱石は、ロンドンで個人教授を辞めてからの残りの一年を「根本的に文学とは何か」を研究したことが『文学論』の記述などからわかる。この三十代での危機は、十代の危機と反復にほかならない。
だが、『文学論』が結果的に実現したのは、文学の心理学でも社会学でもない。夏目漱石という作家の小説方法論である。(抜粋)
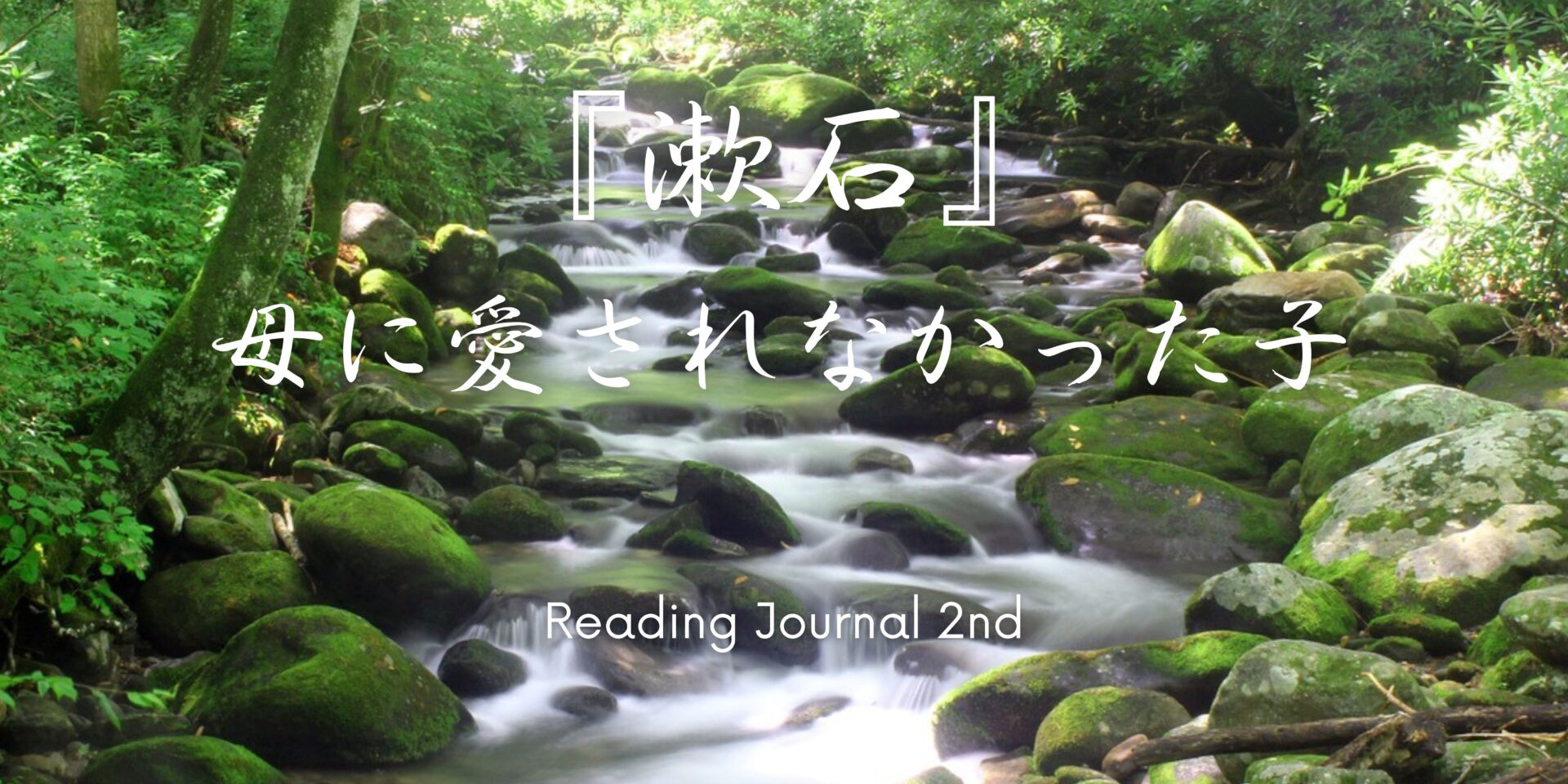


コメント