「星の王子とわたし」
内藤 濯 著 文藝春秋 1968年 950円 (700円で購入)
[Reading Journal 1st:再掲載]
(初出:2007-02-02)
はしがき
岩波版「星の王子さま」の訳者、内藤濯による星の王子さまの解説書。(内藤はフランス文学研究の碩学であり、 劇作家の岸田國士の先生である。詳しくはココ参照)
はしがきに、童心というものを軸に星の王子さまといわゆる児童文学の違いを書いている。
星の王子さまの翻訳時、著者は大変に熱が入った。その理由は、
童心のありかたをしっかりとつかみたくなっていたことが、正直なところ訳業のおもな推進力になった(抜粋)
である。
童心について著者は、いくつかの逸話で解説している、その中の一つは、
数学家の吉田洋一氏の随筆で、子供ごころの面白さを見いだしたのに、こんなのがあった。
あそびに夢中になったA少年が、ふと足もとくるって、かなり深い穴にころげ落ちた。いっしょに遊んでいたB少年が、穴のふちに腹ばいになって、やっと救いあげる。ほっと、胸をなでおろしたB少年は、泥まみれの服をそのまま、家に帰ってくる。それを見た両親は、どうしたのだと訊く。B少年は事の次第を包みかくさず、
「Aちゃんが高い穴に落っこちたもんだから・・・・・・」といったというのである。
高い穴ーーこれはB少年の口から、不用意のうちに飛びだした言葉である。子供たちのあいだには、対応の感情はあっても、対立の感情はない。もしB少年が対立の感情をもっていたのだったら、A少年の落ちた穴を、そっけなく”深い”と言ったにきまってる。それだけ言葉がつめたいのである。ところで、少年にとって至って自然な対応の感情は、子供をしぜんに相手の身にする。だから、B少年はなんの不思議もなく、穴に落ちたA少年の身になって”高い穴”といったのである。思いやりの感情がからんでいるだけ、ぽかぽかと暖かいものを包んでいる言葉である。しかしおとなにありがちな対立の感情は、ややもすれば、”高い穴”を”深い穴”にして、無意識ながら暖かいものをはねのけることになりそうである。ここらあたりにも、おとなの感情と、こどもの感情とのあいだのずれがあるのだと思うと、こどもの躾けというものも、おとながおとなの感情にこだわっているようでは、せっかくの躾けが躾けにならなくなりはしないだろうか。心すべきことだと思う。(抜粋)
そして、物語が童心を持っていれば、サン・テグジュぺリの言葉で「切れ目のない一つの世界」を持っていれば、児童文学はそのまま一般文学としてのねうちをもつ。
しかし、童話作家は「かつて子供だったことを忘れているおとな」が多数であり、子供の視点で物を見ずに大人の視点で物を見るため、その童話は子供の素直な心をむざむざしちまげる教訓臭いものになってしまっている。
子供自身が気づかずにいた子供ごころのあどけなさを、しかるべく仕組んだ文学、そういうのだったら、あっさり文学といえば事すむのに、ことさら児童文学とか童話とかいうふうにこま切れにしたがるこの国の慣わしが、私には気になる。(抜粋)
日本での児童文学の多くはおとなの物語を子どもの想像にあてはめた作であって、おとなのために書かれた子供の物語ではない。
言いかたをかえれば、子供と大人の当然なつながりを、無残にも断ちきった作だからである。(抜粋)
そして、著者は星の王子さまについては、このように言っている。
サン・テグジュぺリのこの作は、かつて子供だったことを忘れがちなおとなのために書かれた作である。一歩すすめて言えば、大人の心の奥に眠っている子供ごころを呼びさまして、子供と共通のあどけなさで世に処するおとなたちの世界を、人間世界の中心にしたい悲願で貫かれた作でもある。したがっておとな向きの童話などといっても、言い足りない多くのものが残る。ナチスドイツの侵略で苦しんでいる親友レオン・ウェルトを慰める意味で、一気に書かれた作であることを思うと、猶更である。
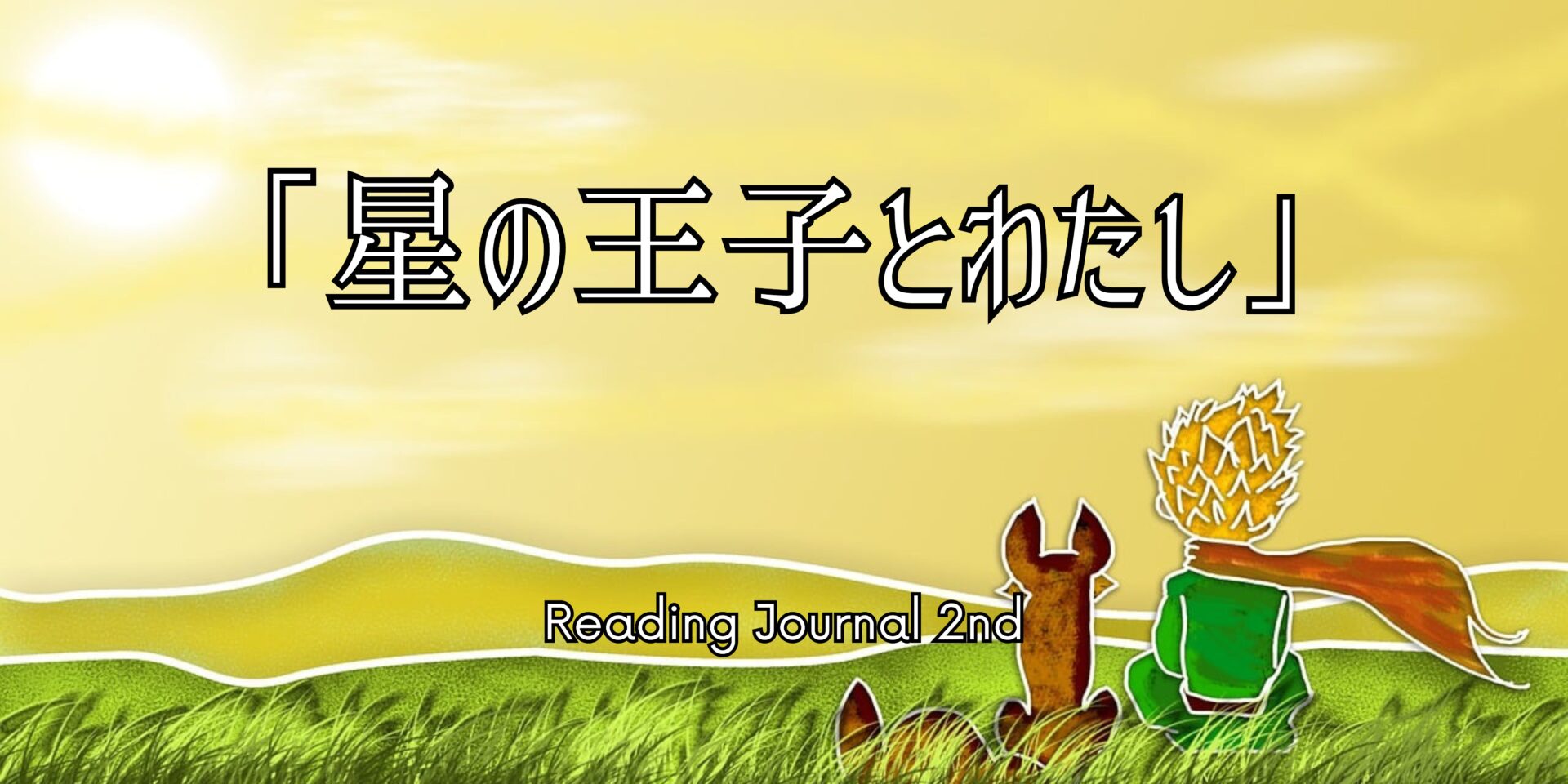


コメント