ブログを再開するにあたって、多少は文章のことも知らんとなぁ~と思って、これまで辰濃 和男の『文章の書き方』と『文章のみがき方』、岩渕悦太郎の『悪文 伝わる文章の作法』、そして瀨戸賢一の『日本語のレトリック』を読んできました。
そう言えば、昔のブログ(reading Journal 1st)にもあったかな?と思って探してみると、ありました。この本、秋月高太郎の『ありえない日本語』です。文章かな?言語かな?と思いますが、とりあえず文章枠で再掲載を決定しました。
(2025年8月24日)
「ありえない日本語」
秋月高太郎 著 筑摩書房 (筑摩新書)720円+税 2005年
[Reading Journal 1st:再掲載]
(初出:2005-04-25)
はじめに 序章「ありえない」はありえない? 第一章「なにげに」よさげ
言語学の本としては「ありえない」んですが、買ってしまいました。
若者の言葉を言語学的に考察している。名前からして軽い本なんだけど「言語学とは・・・」みたいな本は読むのが大変なので、こういう本が最近はいいのね。(そして、有益でもある。)
序章と第一章は、「ありえない」と「なにげに」について。
まずは、[ありえない」の「信じられない」に近い用法についての話。たしかにこの本に書いてあるように、若い人を中心に「ありえね~~~!」みたいな叫びがあって、それを世代が上の人が聞くと、違和感があるわけです。
でも、どうかな?さすがに「ありえね~~!」て叫んだりしないけど、「それって、ありえなくない!」とか使ってるような気もしなくもないなぁ。
「なにげに」は、文法的にどのように発生したか(省略のプロセスによる)どのような用法の変化があったかについて詳しく書いてある。興味深い!
「なにげに」が使われ始めた当初は、若い世代でも認知度は低かったとのこと、しかし、1990年代後半から認知度が高まったそうだ。文法的には、形容詞の連用形の形であるが、もっぱら「なにげに」の形で用いられるため、むしろ副詞的な使い方であるらしい。しかし、最近この連用形での使い方(活用する)がみられ始めたという話である。
また、この「なにげに」の普及から「・・・・げ」という言葉の用法が普及した。
たとえば、「よさげ」、「なさげ」などである。
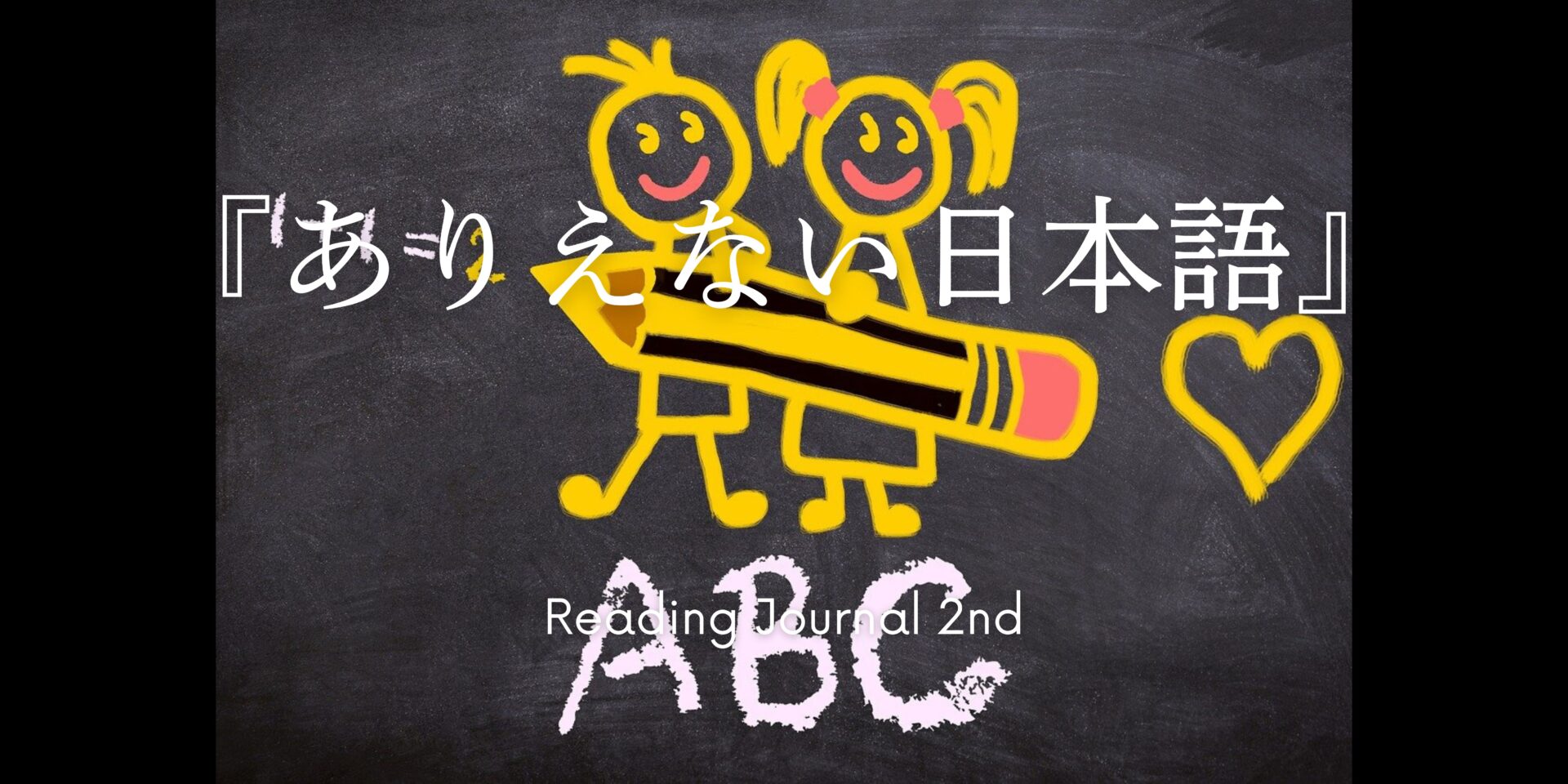


コメント