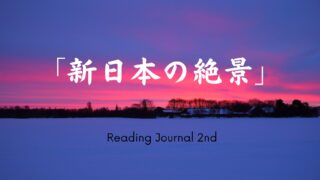 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd [マガジン]「新日本の絶景」
旅行読売2025.2
特集1は「新・日本の絶景」である。土地の観光通に聞いた”穴場“的な絶景を紹介している。いろんな絶景が紹介されているが、その中には、なんと”廃墟“まで!次に特集2は「大河ドラマ「べらぼう」の世界」である。:『旅行読売 2025年2月号』より
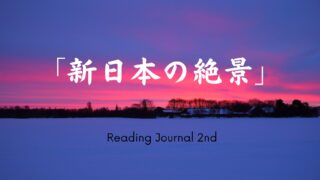 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 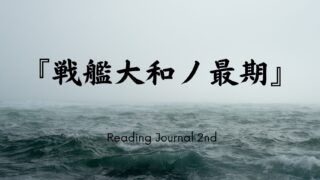 Reading Journal 1st
Reading Journal 1st 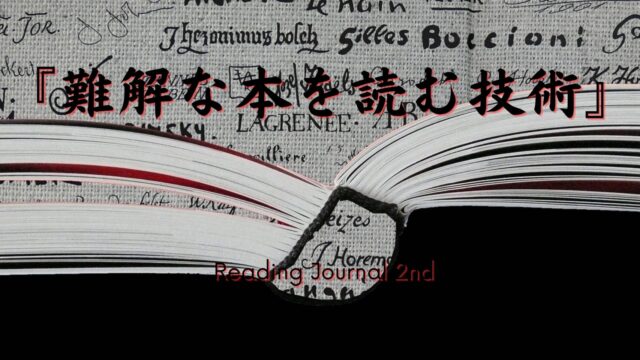 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 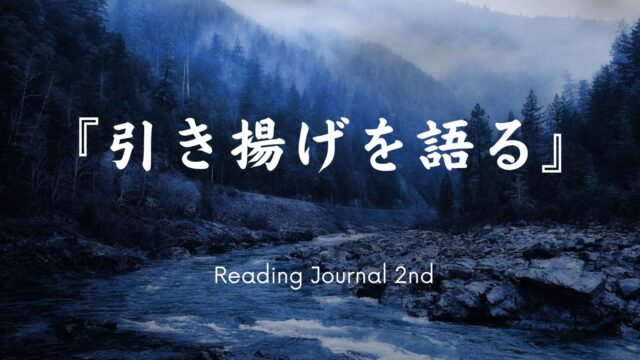 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 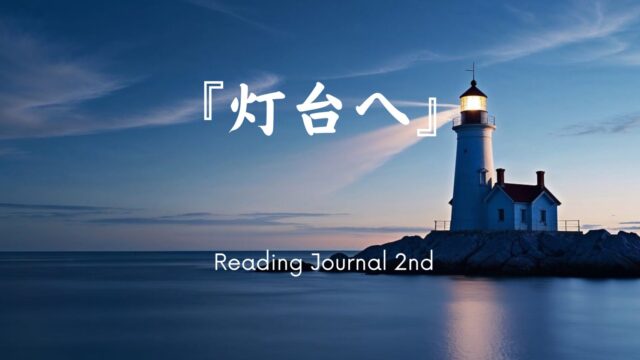 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 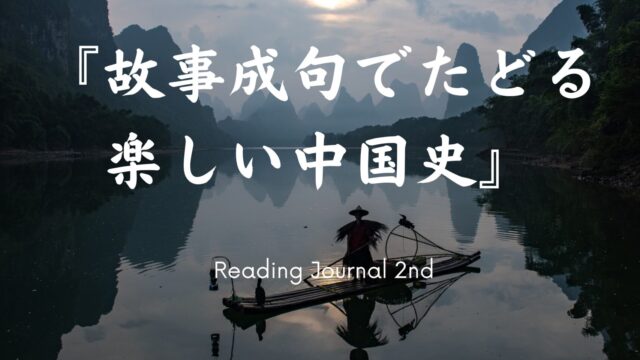 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 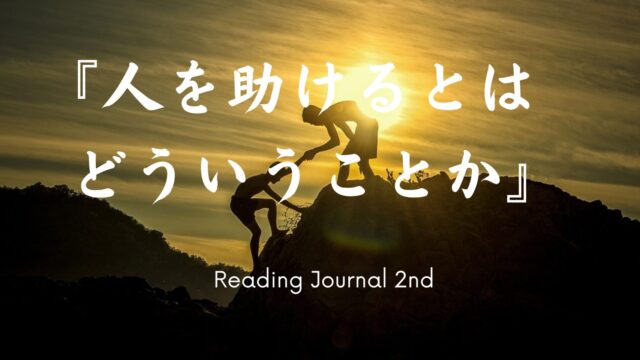 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 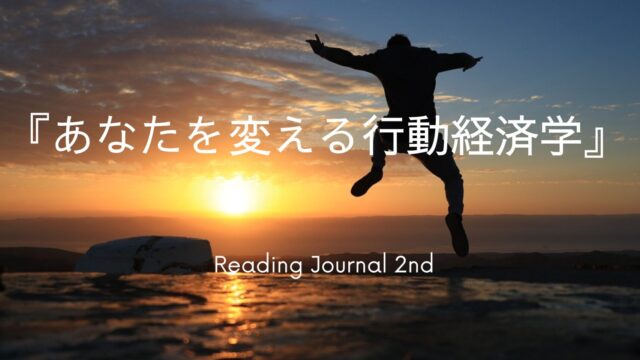 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 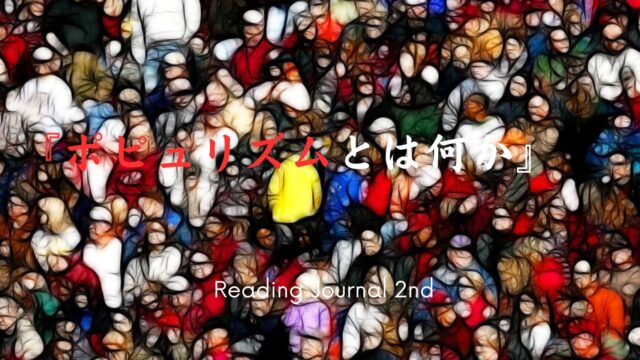 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd