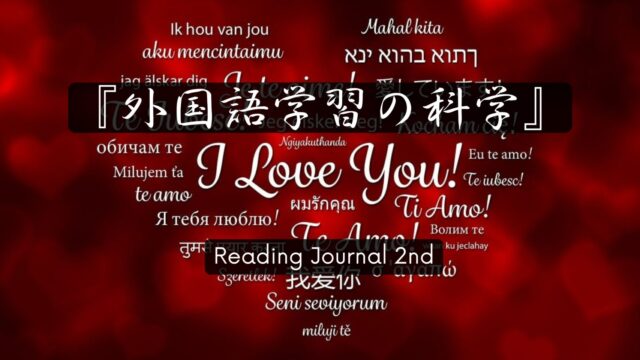 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 母語を基礎に外国語は学習される(前半)
白井恭弘 『外国語学習の科学』より
ある言語の習得の難しさを決めているものの一つに「言語間距離」がある。日本語と英語は言語間距離が離れているため、日本人は英語の習得にハンディキャップを追っている。この言語間距離と習得の難しさの問題は、母語の知識の「転移」が関係している。:『外国語学習の科学』より
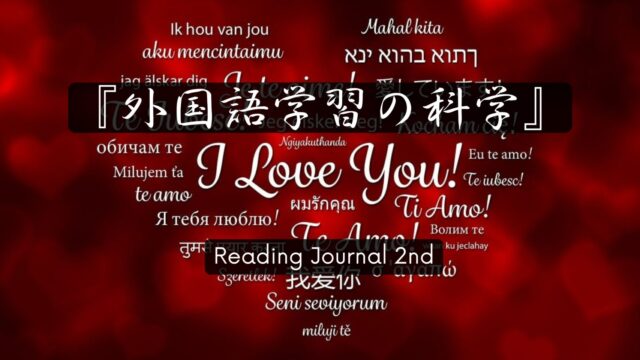 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 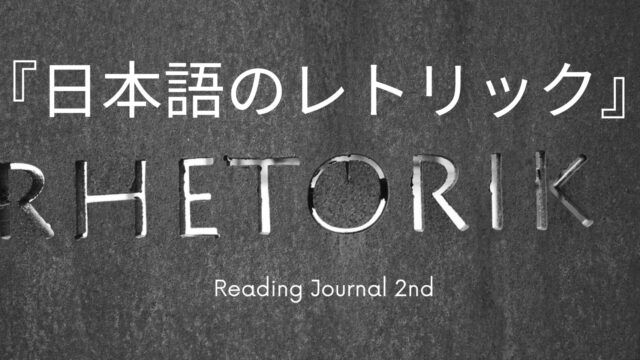 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 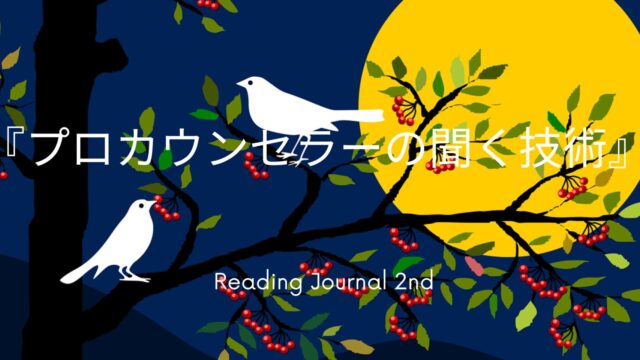 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 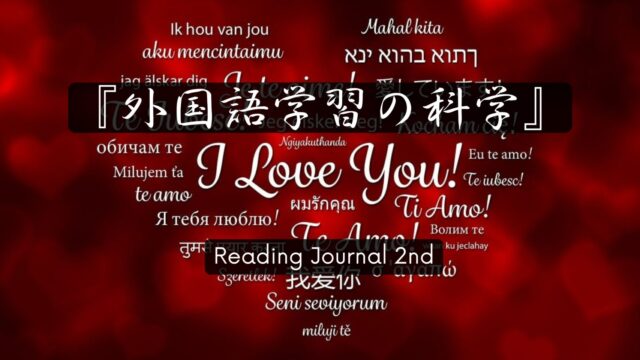 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 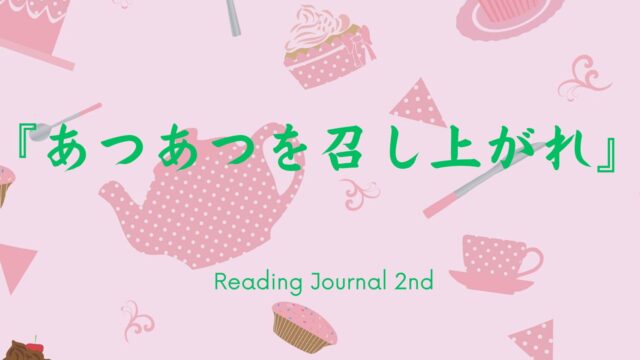 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 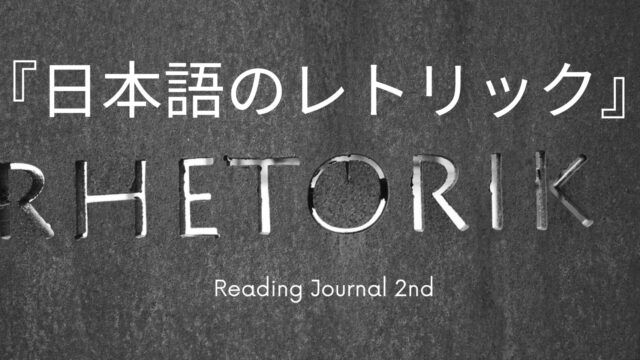 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 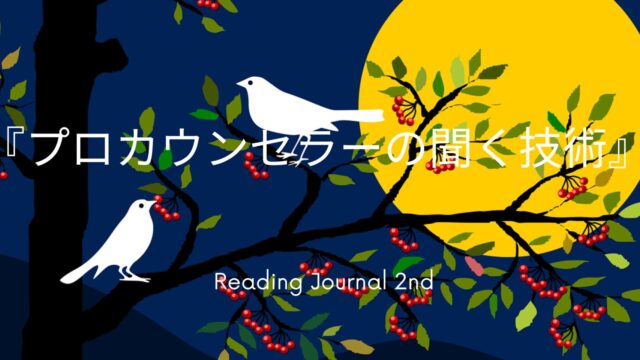 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 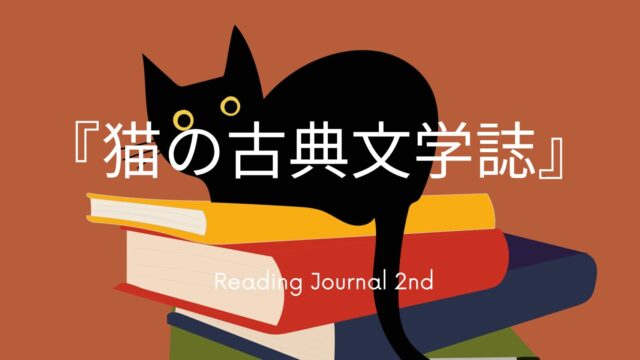 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 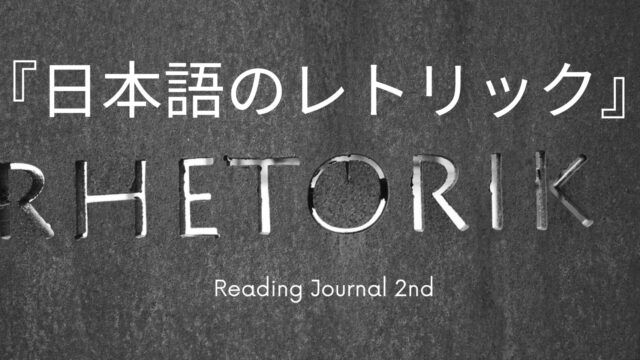 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 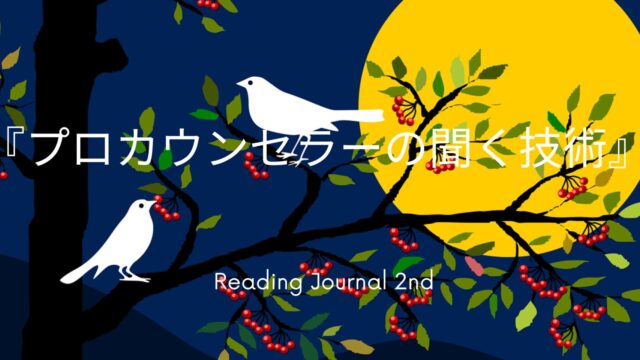 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd