 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 「カリスマ」の登場(その3)
湊 一樹『「モディ化」するインド』より
グジャラート暴動後、モディ州首相には交代論もあったが、その後に行われた二〇〇二年の選挙でモディ率いるBJPは、圧勝した。その選挙においてBJPは、ヒンドゥー至上主義を前面に押し出した選挙戦をし、イスラム教徒との分断を煽って支持を得た。:『「モディ化」するインド』より
 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 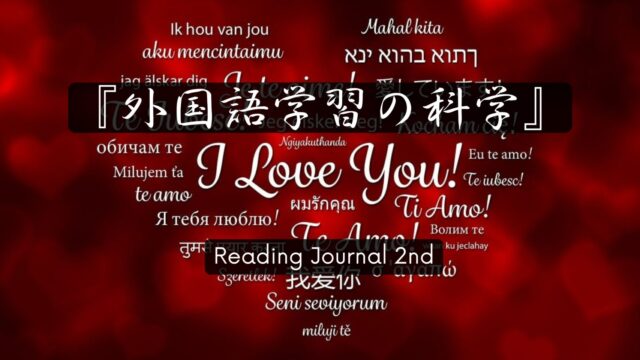 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 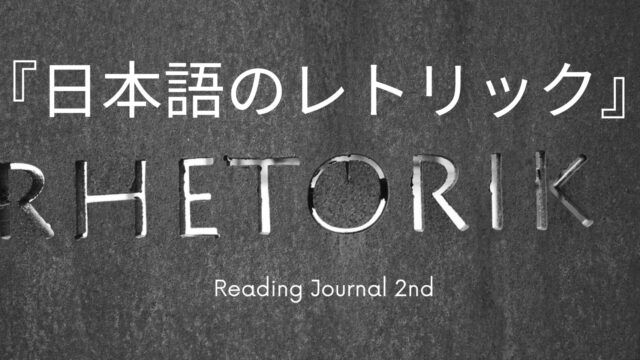 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 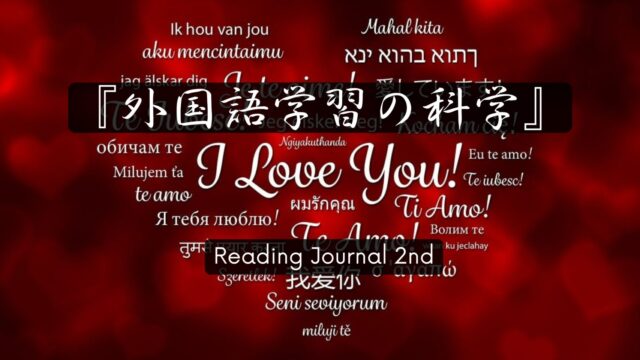 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 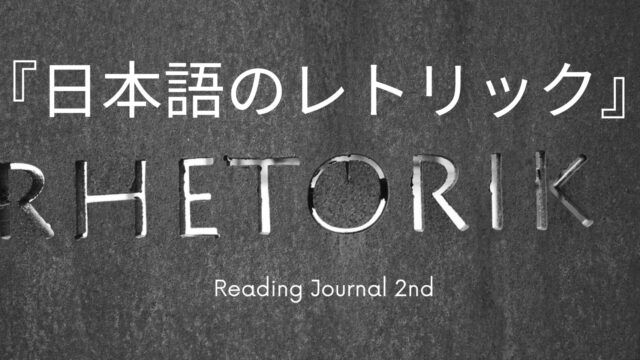 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 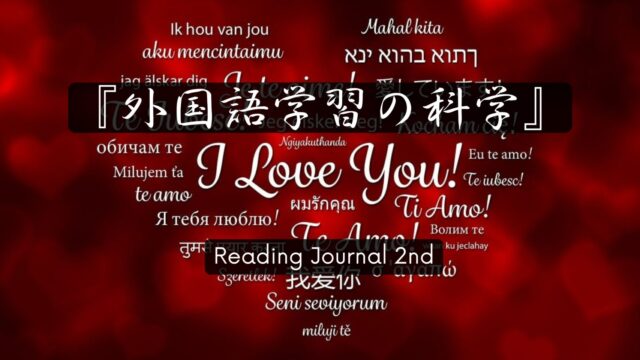 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 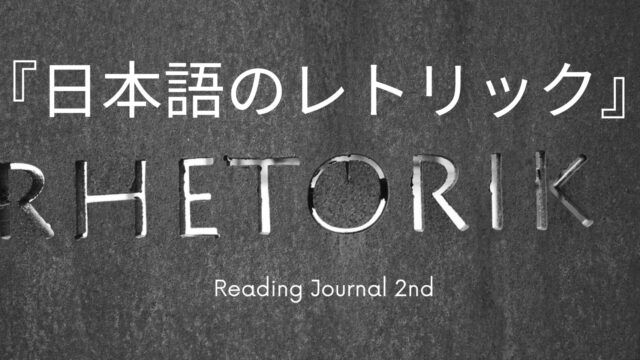 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd