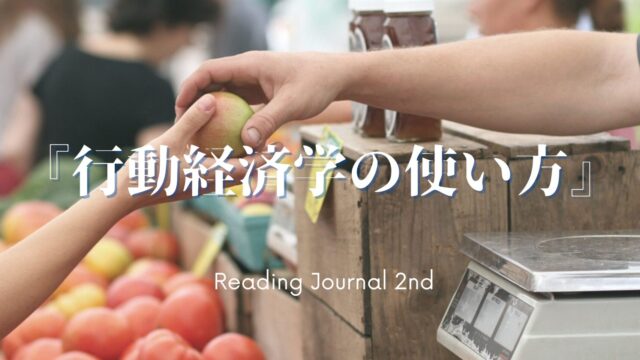 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 行動経済学の基礎知識(その2)
大竹 文雄『行動経済学の使い方』より
行動経済学では、人は現在バイアスのために計画を先延ばしする傾向があるとしている。そして先延ばし行動を理解しコミットメント手段により防ぐ人を賢明な人と呼ぶ。また、利得的な個人を想定せず、社会的選好を持っていると仮定する。:『行動経済学の使い方』より
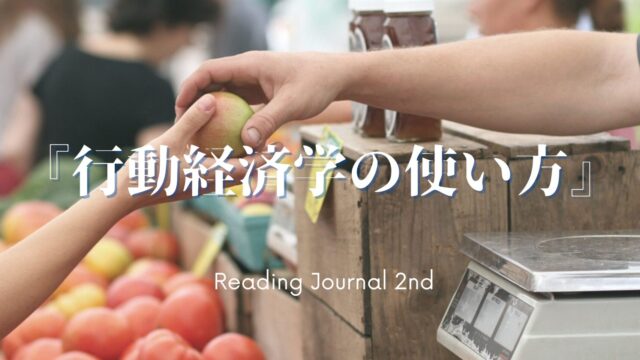 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 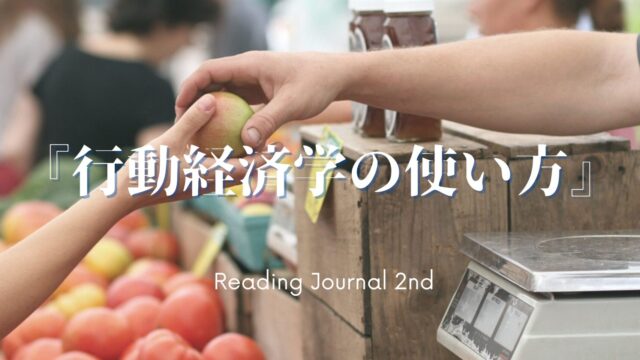 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 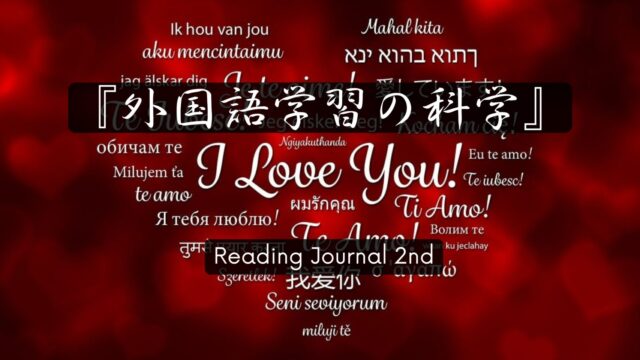 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 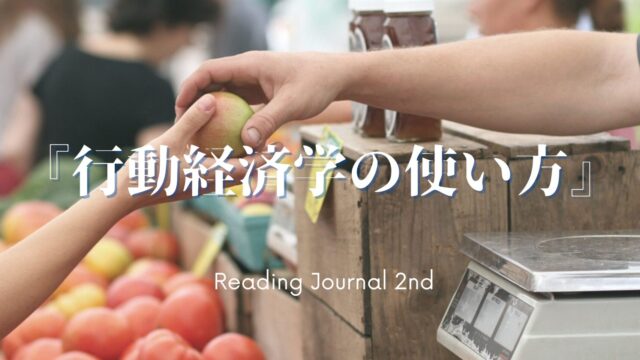 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 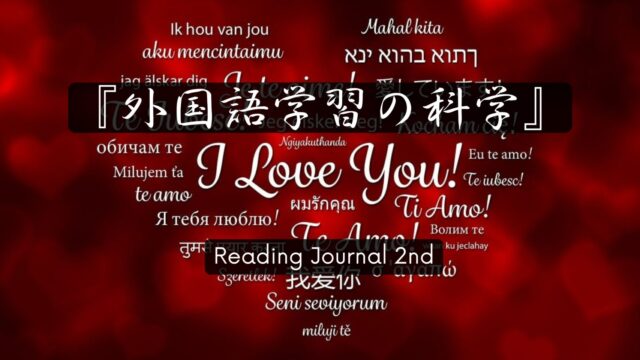 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 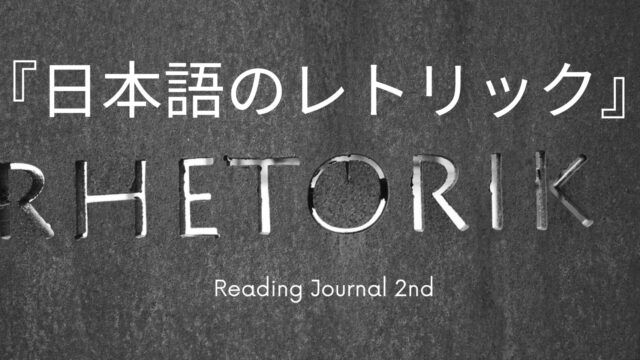 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd