 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd ミッシェル・ビュトール
ジャン=ルイ・ド・ランビュール 『作家の仕事部屋』 より
ミッシェル・ビュトールは、ヌーヴォー・ロマンの代表的作家の一人である。彼の作品はエッセーにしろ小説にしろ「人格の二重化の企て」である。仕事をするには環境に関して中性化して何も目立つものを無くし、仕事に没頭する。:『作家の仕事部屋』より
 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 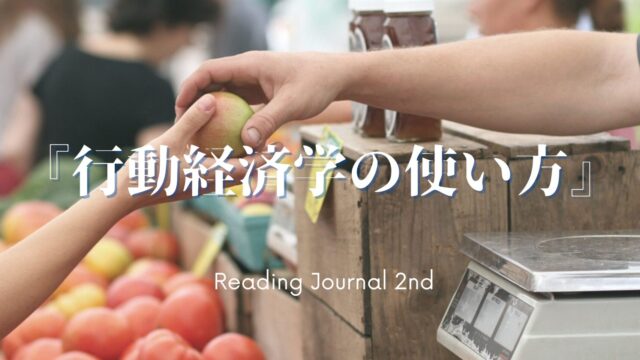 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 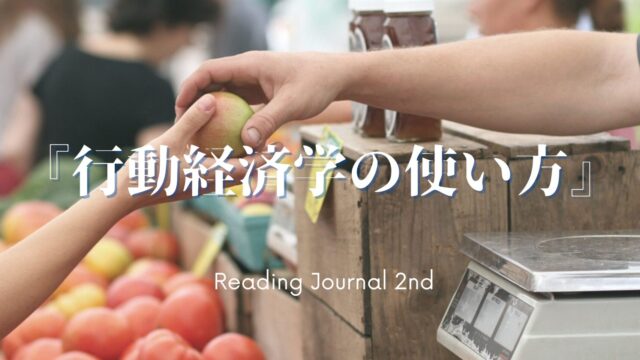 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 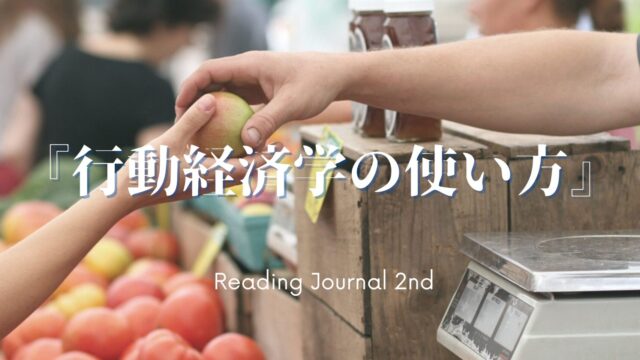 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd