 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd グローバル化するモディ政治(その1)
湊 一樹『「モディ化」するインド』より
二〇二〇年にトランプ大統領が訪印した際に「ナマステ・トランプ」という大規模な集会があり二人は親密さをアピールした。モディ外交の特徴は、このようにインドの国際的地位が高まった理由を首相個人的功績として印象付けることがある。:『「モディ化」するインド』より
 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 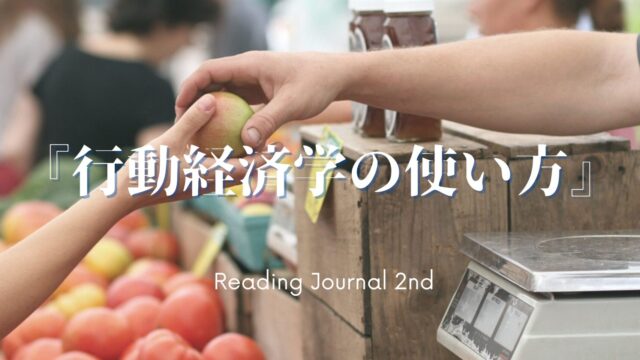 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 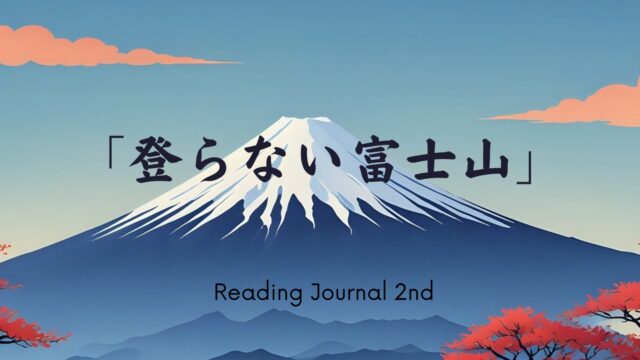 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 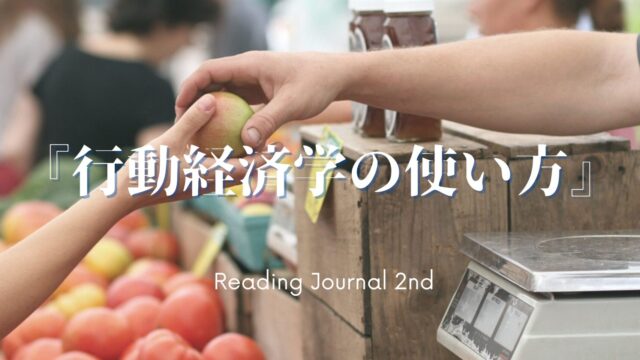 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd