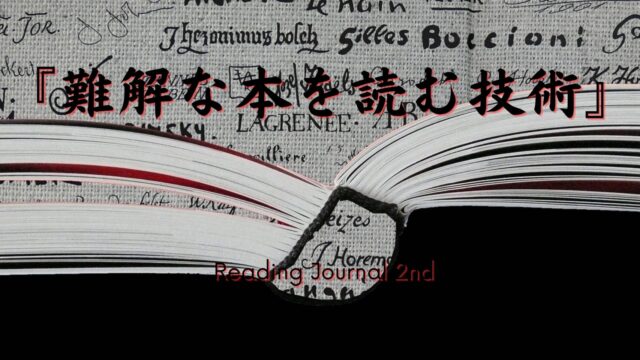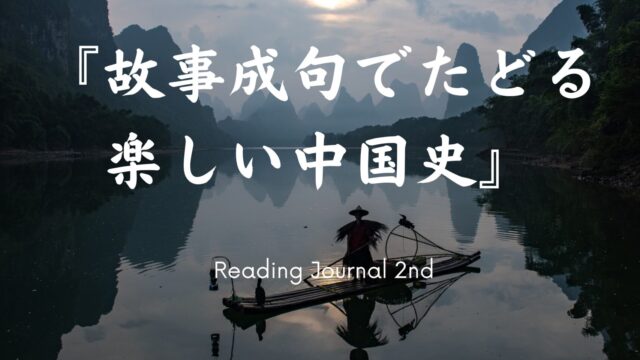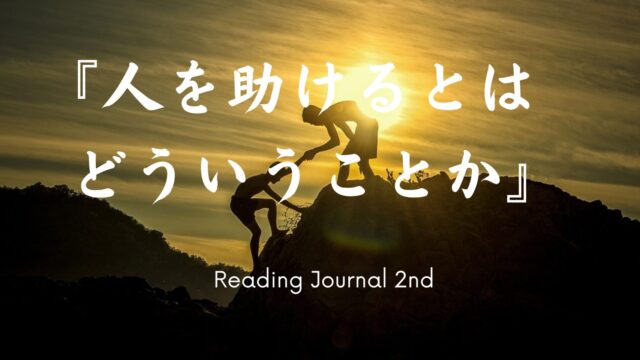 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 支援するリーダーと組織というクライアント(前半)
エドガー・H・シャイン 『人を助けるとはどういうことか』より
コンサルタントが組織を支援するとき、複雑な問題が生じる。コンサルタントを雇うのは組織のリーダーだが、究極のクライアントは組織の人たちになる。コンサルタントは、リーダーが究極のクライアントの支援者になるようにする必要がある。:『人を助けるとはどういうことか』より