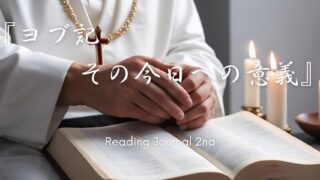 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 義人ヨブ、その試練(一)
浅野 順一 『ヨブ記 その今日への意義』より
信仰心の篤いヨブは幸せな生活をしていた。その信仰心を神は褒めたがサタンは、幸せで無くなっても神を信じましょうかという。そしてサタンはヨブの財産と家族を奪う。しかし、「ヨブは罪を犯さず、また神に向かって愚かなことをいわなかった」:『ヨブ記 その今日への意義』より
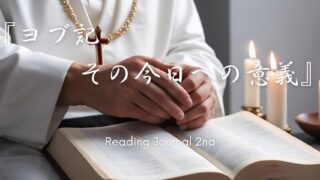 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 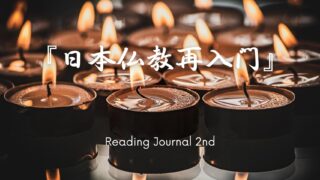 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 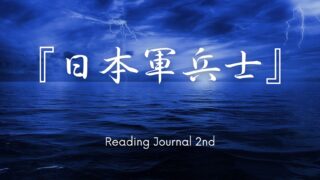 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 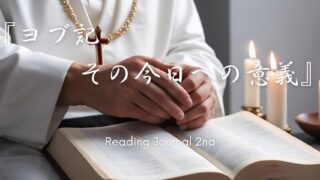 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 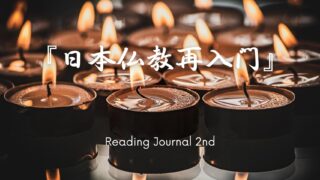 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 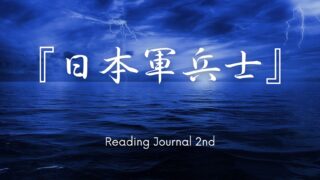 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 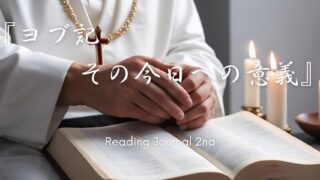 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 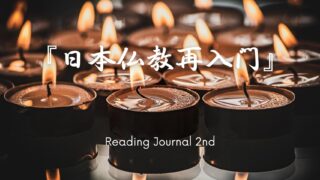 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd