 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 聞くことのちから、心配のちから(その2)
東畑開人 『聞く技術 聞いてもらう技術』 より
「わかる」にも種類があり、ここで大切なのは普通のわかるではなく、「相手がどのような世界を生きているのか」わかるという「わかる」である。この「それはつらかったよね」という「わかる」は、「世間知」によって支えられている。:『聞く技術 聞いてもらう技術』より
 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 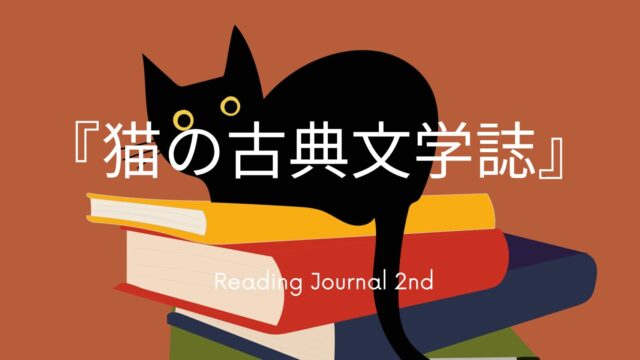 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 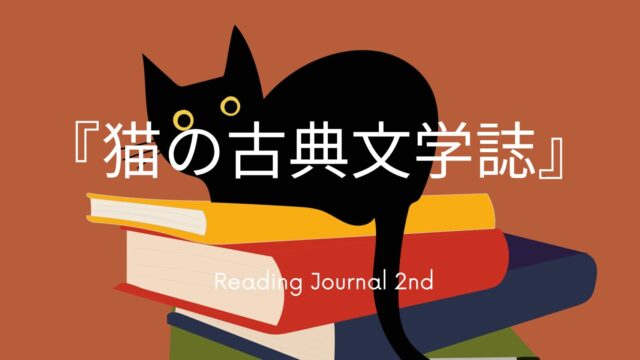 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 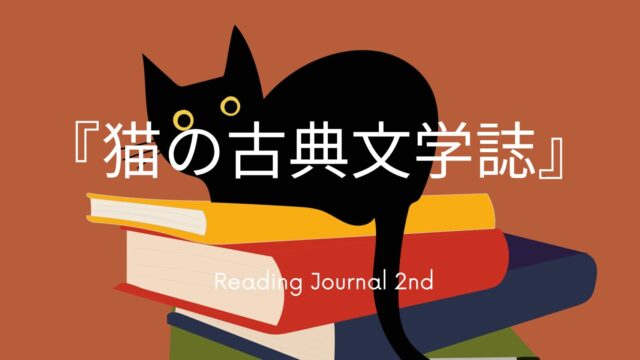 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd